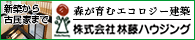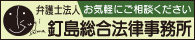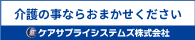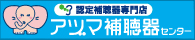本文
建設系産業廃棄物の適正処理について
1 処理責任(元請けと下請け)
廃棄物処理法では、廃棄物の排出事業者の責務として、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが規定されています。
(1)原則:元請業者が排出事業者です(法第21条の3第1項)
建設工事が数次の請負によって行われる場合は、建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理について、元請業者を排出事業者とします。
これにより、元請業者は、排出事業者として自ら適正に処理を行い、又は委託基準に則って適正に処理を委託しなければなりません。また、下請負人は「廃棄物処理業の許可業者」であって「元請業者からの処理委託契約」がなければ、廃棄物の運搬又は処分を行うことはできません。
| 建設工事とは | 土木建築に関する工事であって、建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含みます。 |
|---|---|
| 元請業者とは | 注文者(施主)から直接建設工事を請け負った建設業を営む者(間接的に請け負った者、二次的に請け負った者は下請負人となります。) |
(2)特例:下請負人の不適正保管は、元請業者と下請負人を指導します(法第21条の3第2項)
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、下請負人が現場内で行う保管は、当該下請負人もまた排出事業者とみなして、産業廃棄物保管基準及び改善命令に係る規定を適用します。
原則「元請業者が排出事業者」ですから、元請業者及び下請負人の双方に産業廃棄物保管基準を適用し、不適正な保管についても双方が改善命令の対象となります。
(3)特例:下請負人が自己排出として許可なく運搬できる例外もあります(法第21条の3第3項)
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について、書面による請負契約で「下請負の廃棄物は下請負人が運ぶ」と定め、下請負人が自らその運搬を行う場合には、下請負人も排出事業者とみなします。
この場合、下請負人は産業廃棄物処理業の許可がなくても、当該廃棄物の運搬を行うことを可能としますが、産業廃棄物処理基準及び改善命令に係る規定を適用します。
また下請負人が不適正な処理を行ったときは、元請業者及び下請負人を指導します。
※下請負人が許可なく運搬できる場合(すべてに該当した場合に限ります。)
- 建設工事(建築物等の解体、新築又は増築を除く)又は建築物等の瑕疵の補修工事であって、当該工事の請負代金の額が500万円以下であるもの
- 特別管理廃棄物以外の廃棄物であるもの
- 1回に運搬する廃棄物が1立法メートル以下であるもの
- 当該運搬の途中で保管を行わないもの
- 運搬先は元請業者が使用権限を有する保管場所又は廃棄物処理施設であって、排出場所と同一の都道府県又は隣接する都道府県に存するもの
- 事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先並びに運搬を行う期間等を具体的に記載した別紙を作成し、請負契約書の写しとともに携行するもの(省令第7条の2第3項第9号)
別紙 下請負人が運搬する時の携行書面 (Word:20KB)
(4)特例:元請業者責任と言っても、実際に不適正処理を行った下請負人も指導します(法第21条の3第4項)
建設工事に伴い生ずる廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合は、原則「元請業者が排出事業者」となるはずですが、それでも下請負人が他人に委託してしまったときは当該下請負人も排出事業者とみなします。
この場合、排出者責任は元請業者に科せられますが、建設工事の不適正処理に限っては、実際に不適正処理を行った下請負人にも排出者責任を科しますので、元請業者及び下請負人の双方に産業廃棄物委託基準を適用し、不適正な委託についても双方が措置命令の対象となります。
(5)建築物の解体時における残置物の取扱いについて
建築物の解体時における残置物の取扱いについて、環境省から通知がありました。建築物の解体業者を排出事業者にすることはできませんので注意してください。
通知(平成26年2月3日付け環廃産発第1402031号) (PDF:269KB)
【要約】
解体する建築物に残されていた廃棄物について、その排出事業者は、解体業者ではなく元々の占有者である。
【解説】
建築物の解体にあたって、あらかじめ占有者に残置物を片づけさせてください。
一般家屋を解体した場合の残置物は、すべて一般廃棄物となります。
事業用建築物を解体した場合の残置物は、元々の占有者の事業活動に従い一般廃棄物又は産業廃棄物に分類します。
一般廃棄物となる残置物の処理を請け負える者は、市町村の一般廃棄物処理業の許可又は市町村からの一般廃棄物処理の委託が必要です。
元々の占有者が倒産、夜逃げなど連絡がつかない場合、一般廃棄物となる残置物の処理を行おうとする者は、市町村からの一般廃棄物処理の委託が必要です。
一般廃棄物の処理については管轄の市町村に問い合わせ願います。
2 保管のルール
工事で生じた建設廃棄物を、排出事業者である工事業者が自己の資材置場などで一時保管するケースがあります。これは積替えを行う必要があり、かつ、運搬先が決まっている場合に限り認められています。保管量の上限は一日当たりの平均的な搬出量の7倍です。また、廃棄物の性状が変化する前に搬出しなければなりません。一時保管のはずが固定化してしまい、不法投棄と化す事例があります。一時保管した建設廃棄物は速やかに搬出しましょう。
建設事業者が産業廃棄物を生ずる事業場の外において保管する場合は届出が必要となることがあります。建設事業者あて通知 (PDF:1.15MB)
※行政書士でない者が、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として官公署に提出する書類を作成することは、法律で禁じられています。(法律で特段の定めがある場合を除く)
(1)届出制度の趣旨
不適正な保管が行われる事案の多い建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物について、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において排出事業者(元請業者)が自ら保管を行う場合、あらかじめ、その旨を都道府県知事へ届け出ることとされています。
保管場所を都道府県知事が把握できる仕組みを設けることにより、不適正な保管が行われた場合にそれを早期に発見し、報告徴収、立入検査、改善命令又は措置命令といった法律上の措置を迅速に行い、もって生活環境保全上の支障の発生の未然防止と拡大防止を確実にすることを目的としています。
(2)届出の対象となる保管(以下の両方を満たす場合)
- 建設工事に伴い生ずる(特別管理)産業廃棄物を当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において保管する場合
- 保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場合
※ なお、以下の場合は届出の対象外となります。
- (特別管理)産業廃棄物処理業の許可を受けた施設において行われる保管
- 法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設において行われる保管
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管
(3)事前の届出を要しない場合
地震や水害等の非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物の保管をした場合においては、保管をした日から14日以内に、その旨を都道府県知事へ届け出なければならないこととされています。
(4)変更(廃止)の届出等
届け出た事項を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出ることとされました。
届出に係る保管をやめたときは、当該保管をやめた日から30日以内に、都道府県知事に届け出なければならないこととされました。
(5)提出書類及び提出先
| 届出対象行為 | 届出の時期 | 届出様式 | 添付書類 | |
|---|---|---|---|---|
| 産廃 | 特管 | |||
| 保管を行おうとするとき | あらかじめ | 産業廃棄物事業場外保管届出書 (Word:27KB) | 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 (Word:25KB) | 産業廃棄物等事業場外保管届出書添付書類一覧 (Word:17KB) |
| 届け出た事項を変更しようとするとき | あらかじめ | 産業廃棄物事業場外保管変更届出書 (Word:24KB) | 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書 (Word:24KB) | 産業廃棄物等事業場外保管届出書添付書類一覧 (Word:17KB)(変更後の書類を添付してください) |
| 届出に係る保管をやめたとき | 保管をやめた日から30日以内 | 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 (Word:24KB) | 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 (Word:24KB) | なし |
| 非常災害のために必要な保管を行う場合 | 当該保管をした日から起算して14日以内 | 産業廃棄物事業場外保管届出書 (Word:27KB) | 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 (Word:25KB) | 産業廃棄物等事業場外保管届出書添付書類一覧 (Word:17KB) |
提出先:管轄の環境(森林)事務所
3 建設リサイクル法と建設系廃棄物
(1) 建設リサイクル法について
平成14年5月30日に建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)が施行されました。一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事の実施にあたり、特定建設資材については、工事現場で分別し、再資源化が義務づけられるとともに、「工事の届出」が必要となります。
-
対象建設工事
分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準については、1)建築物の解体工事では床面積80平方メートル以上、2)建築物の新築又は増築の工事では床面積500平方メートル以上、3)建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上、4)建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事では請負代金が500万円以上と定められています。 -
特定建設資材
建設リサイクル法では、特定建設資材を1)コンクリート、2)コンクリートと鉄からなる建設資材、3)木材、4)アスファルト・コンクリートを対象としています。 -
工事の届出
対象建設工事の実施にあたっては、工事着手の7日前までに発注者から県又は市へ届出をし、分別解体・再資源化等を実施しなければなりません。なお、対象工事の届出を行わなかった場合等には罰則規定が適用されます。 -
関連リンク
- 群馬県建設リサイクルホームページ
工事の届出先について - 国土交通省のリサイクルホームページ<外部リンク>
法律の条文、基本方針、政令等について
(2)再資源化の義務および再資源化施設について
対象建設工事受注者に対して、分別解体などに伴って生じた前述の特定建設資材廃棄物について、再資源化が義務付けられています。
(3)建設系廃棄物の処理について
令和5年度において全国で不法投棄された廃棄物の種類は、件数で見ると、建設系廃棄物が85件(がれき類38件、建設混合廃棄物31件、建設系木くず11件等)であり、全体(121件)の70.2%を占めています。(環境省:産業廃棄物の不法投棄等の状況(令和5年度)について<外部リンク>)
こうした不法投棄等を未然に防ぐため、排出事業者としての建設業者の役割について、次のような取り組みが必要です。
- 構造物の省資源化・長寿命化を図るよう計画、かつ廃棄物を抑制する。
- 発生した廃棄物については、再利用・再生利用の徹底し、資源循環を図る。
- 自ら処理をすることが困難な場合には、適正な委託処理を行い、排出事業者としての責任を全うする。
(4)建設汚泥について
建設汚泥の再資源化率は極めて低い水準にとどまっており、産業廃棄物の最終処分場の残余容量が逼迫している中、建設汚泥の最終処分量をいかに削減するかは喫緊の課題となっています。また、建設汚泥を含む建設廃棄物の不法投棄問題は依然として全国各地で看過できない状況にあります。
群馬県においても発生の抑制、減量化、再生利用を推進しています。県内の建設工事から排出する建設汚泥については、廃棄物・リサイクル課までご相談ください。
関連リンク
- 建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について(PDF:18KB)<外部リンク>(平成17年7月環境省)
- 建設汚泥の再生利用指定制度の運用における考え方について(PDF:142KB)<外部リンク>(平成18年7月環境省)
- 建設汚泥の再生利用に関するガイドライン等の策定について<外部リンク>(平成18年6月国土交通省)
- 建設汚泥処理物等の有価物該当性に関する取扱いについて(PDF:183KB)<外部リンク>(令和2年7月20日環境省)
- 建設汚泥処理物等の有価物該当性に係る第三者認証について (PDF:630KB)(令和3年8月19日環境省)
4 建設廃棄物の一般的な処理の流れ
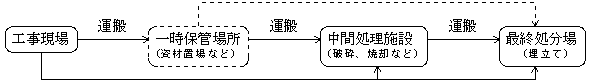
中間処理施設を経由しないで最終処分場へ運搬されるケースもあります。
中間処理施設で再資源化された場合は、処理はそこで終わります。
「焼却」は最終処分ではありません。焼却灰を最終処分場で埋め立てるなど、更なる処理が必要です。
5 自ら運搬する場合のルール
産業廃棄物を運搬する場合、運搬車両の車体の両側面に産業廃棄物の運搬車両である旨の表示をし、かつ、その廃棄物の種類などを記載した書面を備え付けることが義務づけらています。工事で生じた建設廃棄物を排出事業者である工事業者が自ら運搬する場合は、次の表示と書面が必要です。
| 車体表示の内容 | 備え付ける書面の内容 |
|---|---|
|
|
他の工事業者が排出した建設廃棄物を運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。建設廃棄物の排出事業者は、通常は工事の元請業者であるため、工事の下請業者が運搬する場合は、その下請業者が許可を持っていなければなりません。なお、請負形態によっては下請業者が排出事業者になる場合もあります。(詳しくは前記「3」参照)
6 自ら処分する場合のルール
- 工事で生じた建設廃棄物を、排出事業者である工事業者が自ら所有する破砕施設や焼却施設などの処理施設で処分する場合は、その処理施設の規模に応じて産業廃棄物処理施設の設置許可が必要な場合がありますので、事前に環境(森林)事務所に相談してください。
- 野焼きは特別な場合を除き禁止されています。廃棄物の焼却は次に示す構造基準を満たした焼却炉で行わなければなりません。この場合、焼却灰は、許可を受けた処理業者に委託するなどして適正に処理する必要があります。
- 廃棄物を燃焼室で摂氏800℃以上で燃やすことができること
- 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入できること
(1回の投入で燃やし切るバッチ炉も可) - 燃焼室の温度を測定できる構造であること
- 助燃装置があること(安定した燃焼状態が保てる廃棄物のみを焼却する場合は不要)
- 焼却に必要な量の空気が通風できること
- 許可を受けた最終処分場以外の場所に廃棄物を埋め立てることは、たとえ自分の所有地であっても禁止されています。
- 他の工事業者が排出した建設廃棄物を処分する場合は産業廃棄物処分業の許可が必要です。建設廃棄物の排出事業者は、通常は工事の元請業者であるため、工事の下請業者が処分する場合は、その下請業者が許可を持っていなければなりません。なお、請負形態によっては下請業者が排出事業者になる場合もがあります。(詳しくは前記1(3)参照)
- 地下工作物の埋め殺しは、当該地下工作物が「廃棄物」に該当し、生活環境保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められると判断された場合は、当該地下工作物の撤去等、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命せられることがあります。令和3年9月30日環境省通知(PDF:157KB)<外部リンク>
7 他の業者に処理を委託する場合のルール
産業廃棄物の処理は、ほとんどの場合、専門の処理業者に委託されているのが実態です。委託された廃棄物の不適正処理を防止するため、次のようなルールが定められています。
- 運搬については産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている処理業者に、処分については産業廃棄物処分業の許可を持っている処理業者に委託すること
- 委託契約は書面で行うこと(1回限りの委託でも必要)
- 運搬と処分を委託するときは、運搬については運搬業者と、処分については処分業者と別々に契約すること(運搬と処分が同一業者の場合は1つの契約書でも可)
- 委託契約書には許可証の写しを添付すること
- 廃棄物を処理業者に引き渡すときは、相手に産業廃棄物管理票(通称「マニフェスト」)を交付すること
- 処理業者から送付されたマニフェストの写しを確認し、委託した廃棄物が最後まで適正に処理されたことを確認すること
ルール違反の処理委託をした建設廃棄物が不法投棄された場合は、投棄した者だけでなく、委託した工事業者もその廃棄物を片付けなければなりません。また、委託のルールは守っていても、適正処理の対価とは認められないような安い料金で委託した場合は、委託した工事業者にも不法投棄の責任が及びます。委託先の処理業者は慎重に選びましょう。
〈こんな処理業者には注意〉
- 許可証を見せない
- 何でも処理できると豪語する
- 他の処理業者に比べて処理料金が著しく安い
- 敷地内に廃棄物が溢れている
8 罰則
以上のルールに違反した場合や違反状態を改善させるために行政機関が出した命令に従わなかった場合は罰則が適用されます。廃棄物処理法は他の法律に比べて量刑が重いと言われています。例えば不法投棄と不法焼却は、いずれも5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金又はこの併科です。
処罰されると金銭的にも社会的にも大きな損失を被ります。そうならないためにも、建設廃棄物は適正に処理しましょう。