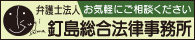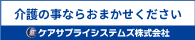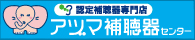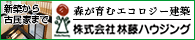本文
中間検査制度について
中間検査制度は、平成10年の建築基準法改正(平成10年6月12日公布)により創設されました。この制度は、平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災において、施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多数みられたため、施工途中で検査を実施できる制度を創設する必要があるとして新たに導入されたものです。
建築物が計画されてから工事が完了して使用開始されるまでを“フロー”の段階、使用開始されてから耐用年数を経て解体されるまでを“ストック”の段階とすると、平成10年の法改正では、建築確認業務の民間開放、中間検査制度の創設及び確認検査等に関する図書の閲覧制度の整備など、フローの対策に主眼が置かれました。これを受けて、群馬県では、平成17年7月1日から中間検査制度を導入しました。
平成17年群馬県告示第290号により建築基準法の規定による特定工程等を指定し、中間検査を行う期間を平成17年7月1日から3年間と指定しましたが、中間検査は、工事施工段階での基準不適合を発見するために有効であり、また、適正な工事監理を徹底させるためにも不可欠なものであることから、引き続き実施しています。
なお、平成19年6月20日施行の改正建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により、3階建て以上の共同住宅に係る床及び梁の配筋工事の工程(主に鉄筋コンクリート構造の建築物)については、全国一律に中間検査を実施することとされています。
建築基準法の規定による特定工程等の指定について
平成20年5月30日群馬県告示第255号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のように指定する。
なお、建築基準法の規定による特定工程等の指定の告示(平成17年群馬県告示第290号)は、平成20年6月30日限り廃止する。
1 中間検査を行う区域
群馬県の区域(法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村の区域を除く。)
2 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
(1)主要構造部の全部又は一部が木造(丸太組構法を除く。以下「木造等」という。)の一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(木造等の構造部分に限る。)が100平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの
(2)主要構造部の全部又は一部が鉄骨造(以下「鉄骨造等」という。)の建築物で、一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分の床面積(鉄骨造等の構造部分に限る。)が500平方メートル以上で、かつ、地階を除く階数が3以上のもの
3 指定する特定工程
(1)2(1)の建築物又は建築物の部分 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組工事及び耐力壁の工事)
(2)2(2)の建築物又は建築物の部分 1階の建て方工事
4 指定する特定工程後の工程
(1)2(1)の建築物又は建築物の部分 壁の内装工事、外装工事その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の建築物にあっては、屋根の小屋組及び耐力壁)部を隠ぺいする工事
(2)2(2)の建築物又は建築物の部分 耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事
5 適用の除外
(1)法第85条の適用を受ける建築物
(2)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物又は建築物の部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第6条第2項の規定に基づく検査のうち、特定工程に係る工事を終えたときに行う検査を含む検査に係る検査報告書の検査結果において、「適合」の判定を受けたものに限る。)
(3)法第68条の20の認証型式部材等である建築物又は建築物の部分
(4)独立行政法人住宅金融支援機構の融資又は証券化支援事業を利用した住宅で、適合証明検査機関が行う中間現場検査に合格したもの
附則
- この告示は、平成20年7月1日から施行する。
- この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物、法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物及び法第18条第2項の規定により計画を通知する建築物について適用する。ただし、施行日前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物で、施行日以後に当該建築物の計画を変更するものを除く。
- 施行日前に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物に係る特定工程及び特定工程後の工程については、この告示による廃止前の建築基準法の規定による特定工程等の指定の告示(平成17年群馬県告示第290号)定めるところによる。
群馬県中間検査マニュアル
群馬県中間検査マニュアル_令和7年度 (PDF:2.93MB)
群馬県中間検査マニュアルに基づく各種様式については、以下のダウンロードページをご利用ください。
建築基準法関係各種様式のダウンロードページ