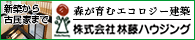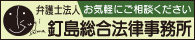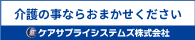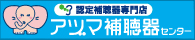本文
【BYOD】【端末購入支援金】対象世帯の確認方法について
端末購入支援金の対象世帯かどうかを確認する方法をお示しします。
ご自分が対象世帯かどうか、目安として参考にしてください。
(1)生活保護世帯とは
生活保護を受給している世帯は、補助率10/10の支援を受けられます。
生活保護受給証明書やマイナポータルで確認してください。
(1)生活保護証明書で確認する方法
(2)マイナポータルで確認する方法
マイナポータルログイン方法→デジタル庁ホームページ<外部リンク>
(2)非課税世帯とは
保護者等全員の住民税所得割額が0円又は1~99円である場合を指します。
均等割額がかかっていても対象になります。
(1)マイナポータルでの確認方法
マイナポータルログイン方法→デジタル庁ホームページ<外部リンク>
(2)納税通知書での確認方法(自営業で、非課税ではない方)
(3)特別徴収税額決定・変更通知書での確認方法(給与所得者)
(注意)複数の勤め先の給与や、その他副収入等がある場合は、通知書とは異なる課税がされている可能性がありますのでご注意ください。
(4)課税証明書での確認方法(証明書有料)
(3)年収目安350万円未満の世帯とは
保護者等全員の「市町村民税の所得割の課税標準額×6%-調整控除額」の合計が51,300円未満の場合を指します。
父母それぞれ計算し、合計額を51,300円と比較します。
エクセルで仮計算できます。→ 仮計算シート (Excel:777KB)
【計算例1】マイナポータルで確認すると、下記の計算を行う。
マイナポータルログイン方法→デジタル庁ホームページ<外部リンク>

父:課税標準額590,000円×6%ー調整控除額1,500円=33,900円…ア
母:課税標準額0円×6%ー調整控除額0円=0円…イ
ア+イ=33,900円 < 51,300円 → 計算結果:対象
※以下、計算例2及び計算例3の書類だけでは計算ができません。仮計算シートで「調整控除額」を求めることができます。
【計算例2】以下の特別徴収税額決定・変更通知書の場合は、下記の計算を行う。(ひとり親の場合)
課税標準額406,000円×6%ー調整控除額4,500円(※注)=19,860円 < 51,300円 → 計算結果:対象

(※注)「調整控除額」は仮計算シートで求めて下さい。特別徴収税額決定・変更通知書には表示されていません。
【計算例3】所得・課税証明書の場合は、下記の計算を行う。
(申請時点ではひとり親だが、今年ひとり親になったため、ひとり親控除が住民税に適用されない場合)
課税標準額1,049,000円×6%ー調整控除3,000円(※注)=59,940円 > 51,300円 → 計算結果:対象外

(※注)「調整控除額」は記載されないため、発行時に市町村窓口で調整控除額の記載を依頼してください(コンビニエンスストア発行では準非課税の計算ができないため、取り直しになります。)。証明書の発行は有料です。