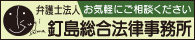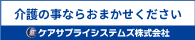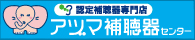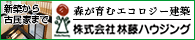本文
令和6年12月教育委員会会議定例会の会議録
1 期日
令和6年12月20日(金曜日)
2 場所
県庁24階 教育委員会会議室
3 出席者
平田郁美教育長、河添和子教育長職務代理者、日置英彰委員、小島秀薫委員、中澤由梨委員、宮坂あつこ委員
4 事務局出席者
高橋正也教育次長、栗本郁夫教育次長(指導担当)、古市功総合教育センター所長、小林謙五総務課長、高林和彦管理課長、酒井隆福利課長、西村琢巳学校人事課長、酒井暁彦義務教育課長、桑子真樹高校教育課次長、近藤千香子特別支援教育課長、星野 貴俊生涯学習課長、橋憲市健康体育課長、角田毅弘総務課学びのイノベーション戦略室長、羽鳥正総務課次長、井澤悟志総務課補佐(行政係長)、丸山裕美総務課副主幹
5 開会
午後1時00分、平田教育長、教育委員会会議の開会を宣す。
傍聴人は1名、取材者は3名であることを報告。
6 会議録署名人の指名
平田教育長が今回の会議の会議録署名人に宮坂委員を指名。
7 議案審議等の一部を非公開で行うことについて
議案審議に先立ち、平田教育長から、第42号議案は教育委員会の表彰に関する案件であるため、審議は非公開で行いたい旨の発議があり、全員賛成で議決した。
8 教育委員会の行事日程
教育委員会の主要行事日程及び次回定例会議の日程について、総務課長が説明。
9 教育長事務報告
(平田教育長)
初めに私から一言申し上げる。
12月16日、今週の月曜日に、教育委員の皆さまと地区別教育行政懇談会を行った。今年度は、沼田市立沼田小学校を会場として、「通級指導の現状と課題について」をテーマに実施した。
まず、意見交換に先だって、沼田小学校の通級指導教室、言語とLD/ADHDの2つの教室を見学することができた。いずれの教室も、児童の興味関心を引きながら、先生方が工夫して自立活動のための指導しており、児童も元気よく、そして熱心に取り組んでいる姿が非常に印象的であった。
その後、沼田小学校や沼田中学校、利根教育事務所、高校通級指導などの取組事例を発表していただき、意見交換を行った。
特別支援教育課で進めていただいている、文部科学省のモデル事業「巡回型通級指導」はもちろんのこと、沼田市におかれても、小学校から中学校への切れ目ない支援や、担任の先生と保護者との連携を重視した指導など、特色のある取組を聞かせていただくことができた。
また、沼田市の教育長をはじめ、現場の先生方と意見交換をすることができ、現場の指導の現状や課題を直接聞くことができるなど、大変参考となる懇談会であった。委員の皆さまのご感想もあるかと思うので、後ほどお願いしたい。
次に、11月25日から12月13日まで第3回後期定例県議会が開催された。一般質問では、教員の人材確保と働き方改革についての質問があったほか、第83回国民スポーツ大会における競技力向上に資する教育委員会の役割について、部活動の地域移行について、インクルーシブ教育について、非認知能力育成に向けた取組について、「つなぐんオンラインサポート」について、不登校児童生徒の健康診断について、新沼田高校開校に向けた準備状況について、などの質問があった。
また、文教警察常任委員会においては、赤城特別支援学校の群馬病院分教室の設置についてのほか、伊勢崎特別支援学校の整備について、BYODについて、デジタル教科書の有用性と現在の対応状況について、昆虫の森と天文台の来場者等について、公立学校教員選考試験について、群馬県読書活動推進計画(第2次)素案について、不登校児童生徒への支援について、嬬恋高校の今後の取組について、などの質疑がなされた。
そのほか、教育委員会が関係する特別委員会として「スポーツ・文化の振興に関する特別委員会」が12月10日に開催された。
教育委員会関係では、湯けむり国スポに係る教員の適正配置などについて、教員不足について、部活動の地域移行について、などの質疑がなされた。そのほかの特別委員会では教育委員会に関係する質疑はなかった。
なお、11月の教育委員会会議でご承認いただいた、教育委員会関係の補正予算と条例に関する議案は、原案のとおり可決された。
12月14日から15日の2日間、草津町において「湯けむりフォーラム2024」が開催され、日置委員にもご出席いただいた。
1日目は講演や知事のトークセッション、2日目は各分科会が開かれ、私はSEL分科会を聴講した。OECDの田熊美保氏や、スコットランド教育庁のオリー・ブレイ氏などの専門家とともに「自分で考えて、自分で決めて、自分で動き出す」子どもを育むための教育の在り方について、SELの視点から議論がなされた。それぞれの専門家の皆さんの意見や考えを聞くことができ、大変参考になった。日置委員からもご報告いただけると幸いである。
前回の教育委員会会議以降の主な行事については、11月20日の新田暁高校創立100周年記念式典に日置委員、11月22日の吾妻特別支援学校創立10周年記念式典に小島委員に、それぞれご出席いただいた。感謝申し上げる。
また、12月6日から10日までの5日間、県庁を会場に「ぐんまインクルーシブフェスタ2024」が開催された。担当された、特別支援教育課の皆さんには大変なご苦労をいただき、非常にすばらしい催しとなった。7日には、「共生社会って何だろう」をテーマにシンポジウムが開催され、宮坂委員が司会を務められた。大変感謝申し上げる。
私からは以上である。続いて、委員からご報告やご意見等があればお願いしたい。
(河添委員)
私は、教育長からもお話があった、12月16日の地区別教育行政懇談会で、沼田市立沼田小学校にお邪魔した。特別支援教育のうち、今回は特に通級指導の状況を学ばせていただいた。私も現場にいた身であるが、大変勉強になった。
初めに沼田小学校の通級指導教室を参観した。先生方がとても温かく、一人一人の特性に合わせた、工夫された授業で、児童たちが生き生きと、主体となって学ぶ姿が見られた。授業や温かい掲示物等も含めて、日頃からの沼田小学校や利根沼田地域の特別支援教育の充実を強く感じることができた。
その後の協議では、沼田市内の自校通級や他校通級、利根沼田地区での巡回指導による、新たな通級の取組を学ぶことができた。また、全県下の高校通級については、7年間積み上げた取組も学ぶことができた。
日頃より、通級指導の様々なニーズに合わせて体制を整え、課題解決に向けご尽力いただいているリーダーの皆さんから、詳細な資料とご説明をいただき、本当に感動した。
昨今、教育全般はもとより、特別支援教育に関わる様々なニーズは多岐にわたり、それに伴い、直接的・間接的な支援に向けた体制作りは、時に困難を極めることもあると思う。協議会では、通級指導担当者と担任との情報共有する時間的がなかなか取れないという現状と、その対応が語られていた。
やはり、教員の多忙化解消は、どの視点から見ても要の政策ではないかと感じている。そうした中で、様々な配慮を含めた日々のご尽力に対し、お会いできた皆様と、視察ではお会いできなかった、子どもたちと直接関わってくださっている全ての皆様にも、心より感謝を申し上げたい。
このような機会を設定してくださった、全ての皆様に感謝を申し上げる。今後も皆様と一緒に、知恵を絞って参りたいと思う。
(日置委員)
私はまず、11月20日に新田暁高等学校の創立100周年記念式典に出席したことを報告したい。
この高校は大正13年に村立綿打実科女学校として設立され、その後学制改革で学校名等が変わり、平成8年に群馬県内初の総合学科として新田暁高等学校となり、今に至っている。すでに卒業生は1万人を超えており、各方面で活躍されているとのことであった。
式典の後には記念講演会として、俳優でタレントの副島淳さんの講演があった。講演のタイトルは「違いを楽しむ」というものであった。副島さんはお父さんがアメリカ人、お母さんが日本人のハーフで、日本でずっと生まれ育ったわけなのだが、肌の色が黒くて縮毛ということで、多くの日本人と外見が異なるため、幼少期は壮絶ないじめを受けたというお話であった。その中で、いろいろな人と出会って、現在は「人と違うことは宝である」、「違いが多ければ多いほど新しい人である」と思うようになり、その特徴で人との距離も縮められると、前向きに話されていたことが非常に印象的であった。
次に、12月15日には、先ほど教育長からご紹介のあったとおり、草津温泉で開催された湯けむりフォーラムに参加した。私も教育長と同じように、SEL分科会と社会情動的学習に関する分科会を聴講した。
そこでは、先が読めない時代のなかで、いわゆるウェルビーイングを実現するために、エージェンシーを発揮する学習者の姿はどうあるべきかということについて話し合った。
その中で、3つのワード、「ボイス」「チョイス」「オーナーシップ」が、子どもたちに大事だということであった。ボイスは、先生が答えて欲しいということを答えるのではなく、学習者が言いたいことを言える環境であるということ。チョイスは、学ぶことや学ぶ方法を、子どもたちが選択できる環境であるということ。オーナーシップは、当事者意識を持って取り組むマインド。その3つが大事であるということだ。
それから、何度でも失敗できるような環境が大事だということで、やわらかい床の上で転ばせるような環境・教育が大事だという表現が印象的であった。
生徒エージェンシーを発揮させる、具体的な取組については、本県のSAH指定校である伊勢崎高校の高橋先生がお話された。伊勢崎高校でエージェンシーを発揮する場面は、行事や探究学習を推進する特別なプログラムだけではなく、普段の授業の中でエージェンシーを発揮させるように落とし込んでいくという取組が非常にすばらしいと感じた。教員一人一人が授業の中で、生徒エージェンシーや協働エージェンシーを発揮する場面を意識的に作ることによって、生徒の普段の様子がどんどん変わっていった実感があるとのお話が非常に印象的であった。生徒エージェンシーを育むには、まず、教員のエージェンシーを発揮させるような環境を整えるということが重要だとおっしゃっていた。
それから、12月16日には地区別教育行政懇談会に参加した。最初は通級指導の現場を見学させていただいた。授業の流れや簡単な指導案の資料を事前にいただき、それを見ながら参観した。体動かすこと、読むこと、書くこと、発音練習など、1つ1つの指導が全て意図をもって流れていると感じ、専門性の高い教育が行われていることに感心した。
その後は、通級指導の現状と課題について意見交換した。利根沼田地区は子どもたちが自校で通級指導を行えるよう、市町村を超えて巡回指導が行われているということで、利用する保護者や子どもにとっては非常に利便性が高い、すばらしい取組だと感じた。先ほど河添委員からもお話があったが、まずは、通級の担当教員に対して、通級指導教室を利用する児童が多く、継続的にきめ細やかな指導をするのが難しいとのことである。通級指導は週に大体1~2時間程度なので、通級指導を受けている子どもたちは、学校生活の大部分を在籍学級で過ごしている。そのため、在籍学級の担任の先生との情報交換や連携は非常に重要になるのだが、なかなか時間が取れず、情報共有や在籍学級での指導体制については、まだ課題があるというお話があった。
少子化の中でも、通級指導に限らず、特別支援学級等に通う児童生徒も増えており、合理的な配慮を必要とする子どもが非常に増えているそうである。もちろん、専門性の高い人材を確保することも必要なのだが、大学の教員養成課程にいる学生も特別支援の授業を受けているので、それをもっと充実させることや、特別支援教育に関する教員研修をさらに充実させていくことで、通常学級においてもきめ細やかな対応が可能になるとよいと感じた。
(小島委員)
私は11月22日吾妻特別支援学校の創立10周年記念式典に出席した。学校では皆さんが「あがとく」と言っており、最初は何のことかわからなかったが、吾妻特別支援学校の略称であった。親しみを持って呼んでいて、学校を愛している、大事にしている感じが伝わってきて、とてもよかった。
式典では、生徒たちが手話で歌っていたことが印象的であった。吾妻特別支援学校の校歌は、児童生徒を含む学校関係者で作詞したそうである。歌っているメンバーを見て、校歌にとても愛着を持っている感じがして、手話と合わせて実に楽しそうに歌う姿はすばらしかった。非常に心が温かくなって帰ってきた。大変よい10周年を迎えられたと思う。
10月には、吉井高校の式典にも参加させていただいた。それぞれ、担当課が違うということだと思うが、式典の進め方については統一したほうがよいと思うことがあるので、後で相談をさせてもらえればありがたい。
次に、地区別教育行政懇談会についてご報告したい。その場でもお話したが、いままで通級という制度そのものを全く知らなかった。非常によい制度で、きめ細かく子どもを見ているところがすばらしいと思った。
特に通級に限った話ではないと思うが、ADHD等の発達障害を持つ子どもへの教育については、少し気になるところがある。企業経営者という立場から見ると、例えば、教員にとって教えやすい子どもは、卒業した後に企業に就職しても、優秀な社員となる。
すごく気がつくし、配慮も行き届いているから、経営者側から見ると、ありがたいメンバーである。企業はそういう人たちがいるから総務などのセッションは円滑に回っている。しかし、30年とか50年というタイムスパンで見ると、企業そのものを変革するとか、大きく変えるのは、そういった「教えやすい子」ではないと思う。
つまり、学校の先生から見て「扱いづらいな」とか、「変わっているな」と思われる、言われたことを唯唯諾諾と受け入れない、ときには常識やルールからはみ出すような子どもの方が、むしろ環境や社会を改革するという点で見れば、大事にした方がよい気がしている。教員から見て教えにくい子どもの方に、もしかすると磨けば光るような人材がいるのではないか。学校現場の先生方には、「そんなに甘くない」と言われてしまうかもしれないが、私はそのように感じている。
そういう点では、少し常識から外れているような子どもも大事にしてもらいたいし、個性を消すことなく送り出してもらえれば、企業として引き受けたいという気持ちである。
(平田教育長)
子どもの困り感の問題と、子どもの個性をどう生かしていくかという問題は、特別支援教育に限らず、全ての教育にとって本質的な問題であると思う。この話題については、後で時間を取らせていただければありがたい。
(中澤委員)
私も12月16日の沼田市で開催された地区別教育行政懇談会に参加した。各委員からお話があったところだが、その時に感じたことをお話しさせていただく。
まず、通級指導の現場を見せていただいて、児童個々の特性・特徴に合った学びを、自立活動を通して学び方を教えていると感じた。着目点のヒントなど、大事ところを抽出して教えていて、担当の先生方が、とてもすばらしく工夫されていると思った。
その後の意見交換で話に出たことだが、通級という大事な場所に通っていくことが、子どもたちの負担になることなく、心地のよい場所であり、子どもが主体的にその場所に学びに行くことが負担にならなければよいと感じた。やはり、ほかの子と「違う」ところに行く、「違う」ことをするということへの受け止めが、小学校でも学年が上がるとだんだん難しくなっていく領域であると思う。
先ほどの日置委員からのお話にあった、「違う」は個性であって、先ほどの小島委員さんのお話にも通じる、「個性を大事にしてよい」、「自分の学び方はこうだ」、「通級に行くとわかりやすい」というように、学び方が違うことを受け止める土壌を作っていけたらよい。通常学級にいられないから通級に行く、行かざるを得ない、という考え方ではなく、違いを受け止めるという、大人側の意識も問われていると思う。とかく集団の中で教育を行うという閉塞的な感覚でいると、大人側が子どもの違いを受け止められない懸念がある。インクルーシブのことを視野に入れても、私たち大人の意識が問われていると感じる、とても勉強になる機会であった。
大人から子どもたちに対して、自分に合った学びを選ぶ権利が子ども自身にあるということを、メッセージとしてどのように伝えていくのか、私自身も問われたように感じた。
(宮坂委員)
私は12月7日の「ぐんまインクルーシブフェスタ2024」について、シンポジウムの司会として携わらせていただき、感謝申し上げる。シンポジストの皆さんがいろいろなルーツを持つ方で、特別支援教育にずっと携わられている群馬大学の霜田教授、現場でカウンセリングを長きにわたって続けていらっしゃるNPO法人カウンセリング&コミュニケーション・ミューの山本代表、日系三世でブラジルにルーツを持つ、株式会社アルテソリューション代表取締役の平野勇パウロ氏、車椅子で生活をされ、デンマークに留学経験がある高木氏、インクルーシブ教育モデル校の上陽小学校校長の増田先生と、「共生社会って何だろう」をテーマにお話した。私自身、ダウン症がある子どもの親と、アナウンサーとしての2つの目線でここに関わることに意義があると感じた。片方の目線だけではない、私ならではの視点で見れたと思う。障害がある子どもの親という目線だけで見ると、インクルーシブの対象は障害者だけだと、自分自身に固定観念があったが、外国籍にルーツを持つ方も、LGBTQ+の方も、いろいろなルーツ・個性を持つ方がいてもよいという考え方であると気づいた。
お話の中で特に印象に残ったのは、高木さんがデンマークに留学されて、デンマークにはそもそもインクルーシブという概念や言葉がないということである。それが当たり前だから、わざわざインクルーシブとは言わないというお話をしていて、ものすごく衝撃を受けた。そもそもインクルーシブという状態を表す言葉があり、「そうしなければ」という義務感のある今の日本の状況を見ると、そういった概念がない、共生社会が当たり前の世界では、「インクルーシブ」や「障害」という言葉自体がないということが印象的であり、自分も固定観念を持っていたことに気づかされた。
また、インクルーシブフェスタでは、先月の定例会の中でご報告のあった、特別支援学校の生徒が作ったというブランドマークを皆さんが身に着けていて、製品にも付いていた。ブランドとして価値を上げていくという考え方はすばらしいと思った。
12月16日には、地区別教育行政懇談会で沼田小学校に行った。実は、私自身も通級という言葉の概念をあまり意識せず育ってきたということを知った。思い出してみれば、自分が子どもの頃にも、特定の授業は抜けて、次の授業には教室に戻ってきている同級生がいた。こういう世界があるのに、何も知らなかった自分に衝撃を受けた。
通級指導の先生方は本当に熱心で、子どもたちも楽しそうで、そこにはすごく自然な雰囲気があった。「障害」や「通常」といった意識・枠組みを作っているのは、我々大人の方なのかと、いろいろと感じるものがあった。
また、県内では、高校生への通級支援も7年前に、たった2人の担当教諭からスタートして、現在は9人で県内の巡回指導を行っているとのことであった。これからいろいろと充実させていかなければいけない部分もあるが、一方で伸びしろがある分野であるとも感じた。
共生社会の話題に戻ってしまうが、子どもが小さいうちから、いろいろな世界に触れる機会を増やしていくことが大切だと思う。子どもが大きくなると、通級に行くのが恥ずかしくなって、その分、放課後に一生懸命学習しているという例も聞くので、そういったことをなくしていけるとよい。そのためには「何ができるだろうか」ということを、2つの行事への参加を通じて深く考えさせられた。
加えて、特別支援教育とは、言わば教育における最先端の分野ではないかと思った。人間的な根源であり、今の時代に求められているものでもあり、ますます興味が沸いてきた。
(平田教育長)
それぞれご報告いただき、感謝申し上げる。本日の委員からのご報告はいずれも深い発言であった。例えば、小島委員から、その子の持っているよさをそのまま生かしていくことが、会社や社会のイノベーションを起こすことに繋がるという視点をいただいた。それから、例えば、文字を読むことがつらい子どもであっても、読み方を工夫してあげることによって、教科書を読めるようになるなど、子どもが持っている困り感に対し、どうやって支援していくかが重要である。
もう1つは、子どもの持っている困り感と、保護者が持っている困り感がずれていることが課題となっている場合もあると考えられる。子どもが通級等に「行きたい」と思って行くことは本当に大切で、そこに行くことがとても楽しく、通常級に戻ったときに、「教科書が読みやすくなった。」とか、「友達とお話がしやすくなった。」とか、それぞれが繋がっていくことが大切である。多くの委員から重要なご発言をいただいた。
それから、「当たり前が変わる」という言葉がキーワードで、宮坂委員をはじめ、皆様がおっしゃっていたことは、障害の有無だけではなく、言語であったり、LGBTQ+であったり、性別も年齢も含めてインクルーシブであるということ。インクルーシブというと、障害の有無だけで語られがちだが、それだけではなく、デンマークで当たり前になっている、インクルーシブという言葉もないような社会の実現に向け、自分にとって当たり前が当たり前でなくなるように、様々なものと触れ合う機会を増やすことが大切であるとのご発言もいただいた。
多くの大切なご発言を全てまとめられなくて申し訳ない。本日は提起型のご発言が多かったが、何か重ねてのご発言やご質問等はあるか。
本日も事務報告が多いので、議案審議等が終わった後で、もし時間が少し残っているようであったら、先ほどの内容を深めていきたいと思う。今後も、こうした大事なことについて、事務局各課の課長等も含め、議論できればありがたい。
ほかに委員から意見等があるか。なければ、関係所属長から報告をお願いする。
(1)非認知能力の評価・育成事業におけるスコットランド共同研究に係る教職員の海外渡航報告について
総務課学びのイノベーション戦略室長、資料1 (PDF:272KB)により報告。
(2)国際生徒・教員サミットへの県立伊勢崎高等学校参加について
総務課学びのイノベーション戦略室長、資料2 (PDF:223KB)により報告。
(3)県立学校のコミュニティ・スクール導入事業におけるモデル校の追加について
高校教育課長、資料3 (PDF:341KB)により報告。
(4)令和6年度第2回中学校等卒業見込者進路希望調査結果
高校教育課長、資料4 (PDF:447KB)により報告。
(5)「ぐんまインクルーシブフェスタ2024」~ちからあわせる190 マンパワー~について
特別支援教育課長、資料5 (PDF:149KB)により報告。
(6)「子どもたちに音楽を届けるプロジェクト」の開催結果について
特別支援教育課長、資料6 (PDF:165KB)により報告。
(平田教育長)
ただいまの報告について、委員から意見・質問等はあるか。
(河添委員)
2点、質問がある。まず、スコットランドとの共同研究について、ご説明いただき感謝申し上げる。すばらしい取組であると思い、期待をしているところである。この共同研究は、非認知能力の評価育成事業が、やがて「ぐんまモデル」として繋がっていく要素の1つであると解釈をしている。そういった場合に、高校教育に焦点を絞って進めていくのか、それとも、この研究をもとに、小・中学校、幼児教育等にも広げていくのか、教えていただきたい。
もう1点は、感想であるが、生涯学習課の「音楽を届けるプロジェクト」や、特別支援教育課の「ぐんまインクルーシブフェスタ2024」は、どちらも本当にすばらしい取組だと思っている。特に、インクルーシブフェスタについては、開催すること自体が意義のある取組であると思うが、インクルーシブ教育等を広く県民等に周知することも大事な目的の1つであるように思える。今後、こういった取組の実施について、どのように周知していくのか、見通しを教えていただければと思う。
(総務課学びのイノベーション戦略室長)
スコットランドの対象校は英語表記上は「High School」だが、日本でいう中等教育学校であることから、中・高校生が対象となる。こちらの対象校は伊勢崎高校ではあるが、総合教育センターの研修員にも協力いただき、中学校段階も研究対象としている。
小学校段階については、スコットランドの対象校の中に小学校も入っているので、その取組も参考にさせていただきたいと思っている。
「ぐんまモデル」については、幼稚園段階まで対象とすることは今のところ難しいと考えているが、幼稚園から小学校への連携、連続性について、盛り込んで反映させたいと考えている。
スコットランドの教育については、湯けむりフォーラムで、幼児期からの遊びや自然体験を通した学びを、小中高の学びにつなげていくところが特徴であると伺った。そういったことも含め、この共同研究によって吸収できるところは吸収し、反映させていきたいと思っている。
(河添委員)
スコットランドは小学校と中等教育学校が対象となっている一方、群馬県は高等学校しか関わっていないという印象を受けてしまった。
群馬県も、総合教育センターなどを通じ、小中高それぞれの段階で関わっていくと理解した。大変期待している。
(特別支援教育課長)
インクルーシブフェスタ2024の周知については、報道機関で多く取り上げていただけたことで、効果的に周知できたと思っている。
また、これが単発のイベントで終わらないよう、来年度以降も理解啓発の周知は継続していこうと思っている。県庁ではない場所でのイベント開催も検討している。また、イベントだけではなく、継続的な取組について、来年度へ向けた課題として検討している。
(河添委員)
どの取組も、事務局のすばらしい努力があってのことだと思う。本当に感謝申し上げる。今後も期待している。
(日置委員)
スコットランドとの共同研究に関して、先日、湯けむりフォーラムでは、生徒のエージェンシーをどんどん育んでいくためには、教員のエージェンシーが重要だという話があった。OECDの田熊氏も、教員のエージェンシーの向上について、戦略を練っているとお話されていた。
ご説明では、スコットランドでの教員研修会に参加されたとのことであったが、この研修は日本の研修とはどのような違いがあったのか。今はまだわからないかもしれないが、教員のエージェンシーを育てていく方針等について、わかる範囲でお伺いしたい。
(総務課学びのイノベーション戦略室長)
まだ、具体的な研修の中身までは把握できていないが、教員用の研修資料は入手しているので、これから分析を進めていく。
教員のエージェンシーの向上については、湯けむりフォーラムでも話のあったとおり、スコットランドも教育改革を始めて十数年ということで、まだまだ従来型の思考の教員もいらっしゃるとのことである。研修では、完全な一斉型授業から、完全に生徒主体で自由に学ばせる授業までの段階があるが、それぞれの教える場面において、どのくらいの主体性の段階を当てはめるべきかの議論を行っていたと報告を受けている。要するに、全てを自由に学ばせればよいという話ではなく、やはり強弱が必要だというところで、先生同士でも、場面・場面によって、どういったエージェンシーを発揮させるべきか、教員としての指導スタンスも課題として、研修のなかで話し合っていた。
我々が今後進めていく中でも、画一的な指導モデルを作るとか、完全に子どもたちの自由に学ばせるというものではなく、場面・場面によって生徒が主体的に考えて動けるよう、一人一人の生徒の特性に応じた多様な学び方を考えていくのだろうと思っている。今後、いただいた資料もあるので、参考にしながら進めていきたい。
(平田教育長)
教員のエージェンシーとは、何が生徒のエージェンシーを上げていくのかということを、教員自身が考えて、そしてやりがいを持って働いていくためにはどうすべきかを議論することだと思う。
今、スコットランドの研修についてお話があったところだが、学びのイノベーション戦略室長はスコットランドに行っていないので、実際に出張した職員に直接話を聞くのがよい。総合教育センターから何か補足はあるか。
(総合教育センター所長)
河添委員からのご質問にも関連するが、当センターの長期研修員が、藤岡市立西中学校の2学年の生徒を対象に、SELプログラムの実践研修を進めている。
その長期研修員は理科の教員であるが、数学・国語・英語・社会の教科での研究、そして、目玉になっているのが、SELプログラムによる、生徒だけでの合唱コンクールの練習という内容である。
教員のエージェンシーについて、この研修のなかでは、児童生徒を主体とした授業の様子を、学年の先生全員に見てもらった。子どもを主体にしたときには、教員としてこういう学びがあるというところを実感してもらうことで、授業観が少し変化してくるそうである。教員のエージェンシーというと、かえって教員が主体というように誤解されそうであるが、子どもたちが主体になることで、教員が得られるものが今までと違うという感覚が、教員のエージェンシーの卵であると感じたようだ。
そういった目線で、この研修員や指導主事がスコットランドに行き、湯けむりフォーラムにも参加させていただいた。SELの場合は、コンピテンシーが明確で、非認知能力というよりは、自己への気づきや、対人関係という視点がはっきりしているので、研究や実践の場面でも踏み込みやすいという要素はあるようだ。
(日置委員)
来年2月のぐんま教育フェスタで、そのお話が聞けることを楽しみにしている。
(平田教育長)
スコットランドで何を得たかについては、あらためて実際に行った者に報告させる。
(中澤委員)
子どもたちに音楽を届けるプロジェクトについて、こちらは東横インと一般財団法人との連携で、県内のフリースクール等に通う児童生徒が対象となっている。フリースクールが多様な学び方の1つとなっている中で、いろいろな文化的な活動体験の機会を得ることがなかなか難しいのではないかと思っていたところであり、こういった機会があることはすばらしいと感じた。今回のような取組を進めていただけることは大変ありがたいと感じる。
フリースクール等の生徒たちを対象とした経緯や、ほかにも似たような取組があるのかを知りたい。
(生涯学習課長)
群馬県内でこの取組を行うことになったきっかけは、フリースクールの支援の目的で、東横インから寄附をいただいたことである。東横インは、一般財団法人100万人のクラシックライブの活動の場づくりをサポートするアレンジャーとして名を連ねており、これまでも同様の取組をされている。
これまで、企業版ふるさと納税で、東横インと群馬県との関わりがかなり深くできていることや、当課に派遣されている専門的人材の発意で、昨年度から始めたという経緯がある。
「子どもたちに音楽を届けるプロジェクト」については、同一般財団法人が全国的に展開していると承知している。
(平田教育長)
多様な学び方においては、フリースクールや社会教育、学校が連携していかなくてはならない。そのなかで、東横インのご協力により、子どもたちと社会や文化との大事な接点が生まれることが本当にありがたいと思っている。
総合教育センターと義務教育課はMANABIBAネットワークという事業を進めているが、フリースクールが行っている文化的活動について、補足等はあるか。
(総合教育センター所長)
当センターでは、ぐんまMANABIBAネットワーク構築事業のなかで、今年度は県内のほぼ全てのフリースクールを訪問したところである。その際の聞き取りによると、それぞれフリースクールによって、自然体験会であったり、フリースクール主催のイベントとであったり、小さい規模で様々な行事が行われていることは把握している。
ただ、子どもが一堂に会するイベントや、文化面で本物に触れるような機会は、学校に通う子どもたちに比べると少ないという印象である。そういった面で、今回の取組はよい機会であると感じた。
(中澤委員)
ご回答いただき、感謝申し上げる。今後もこういったイベント等を行うことで、フリースクール等に通う子どもたちの機会を増やしていけるよう、ご検討いただけるとありがたい。
(平田教育長)
ほかに質問等はあるか。なければ、教育長事務報告は以上とする。
10 議案審議
第40号議案 群馬県公立学校職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則について
学校人事課長、原案(第40号議案) (PDF:366KB)について説明
異議なく、原案のとおり決定
第41号議案 群馬県教育職員免許状に関する規則の一部を改正する規則について
総務課長、原案(第41号議案) (PDF:247KB)について説明
異議なく、原案のとおり決定
11 議案審議(非公開)
ここで、平田教育長から、これからの審議は非公開で行う旨の発言があり、傍聴人及び取材者は退室した。
第42号議案 令和6年度「群馬県教職員表彰」について
総務課長、原案について説明
異議なく、原案のとおり決定
12 教育委員会記者会見資料について
教育委員会記者会見資料について、総務課長が説明。
13 閉会
午後2時33分、平田教育長、教育委員会会議の閉会を宣す。