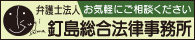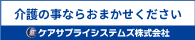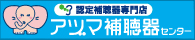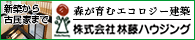本文
令和6年11月教育委員会会議定例会の会議録
1 期日
令和6年11月18日(月曜日)
2 場所
県庁24階 教育委員会会議室
3 出席者
平田郁美教育長、河添和子教育長職務代理者、日置英彰委員、小島秀薫委員、中澤由梨委員、宮坂あつこ委員
4 事務局出席者
高橋正也教育次長、栗本郁夫教育次長(指導担当)、古市功総合教育センター所長、小林謙五総務課長、高林和彦管理課長、酒井隆福利課長、西村琢巳学校人事課長、酒井暁彦義務教育課長、高橋章高校教育課長、近藤千香子特別支援教育課長、星野 貴俊生涯学習課長、橋憲市健康体育課長、角田毅弘総務課学びのイノベーション戦略室長、羽鳥正総務課次長、井澤悟志総務課補佐(行政係長)、丸山裕美総務課副主幹
5 開会
午後1時00分、平田教育長、教育委員会会議の開会を宣す。
傍聴人は1名、取材者は3名であることを報告。
6 会議録署名人の指名
平田教育長が今回の会議の会議録署名人に中澤委員を指名。
7 議案審議等の一部を非公開で行うことについて
議案審議に先立ち、平田教育長から、第32号議案から第34号議案は議会に提出する案件であるため、第35号議案及び第36号議案は教育委員会の表彰に関する案件であるため、第37号議案から第39号議案は人事に関する案件であるため、審議は非公開で行いたい旨の発議があり、全員賛成で議決した。
8 教育委員会の行事日程
教育委員会の主要行事日程及び次回定例会議の日程について、総務課長が説明。
9 教育長事務報告
(平田教育長)
11月11日に教育委員の皆様と、藤岡市立北中学校と県立藤岡北高等学校を訪問した。
まず、藤岡市立北中学校について、藤岡市では、小中一貫教育の充実とコミュニティスクールを推進する教育に取り組まれており、北中学校でも、コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育の充実を推進している。授業見学では、いずれの授業も生徒が主体性をもって考え、行動する場面を見ることができ、大変すばらしいと感じた。家庭科の授業では、ボランティアの方が数名、授業の補助に入っており、きめ細かで手厚い、生徒一人一人にあわせた指導がなされていた。
また、生徒会役員の生徒たちとも意見交換をしたが、皆自分の考えを自分の言葉で発し、元気でハキハキと受け答えをしていて、とても頼もしい子どもたちであった。特に、先輩の考えや行ってきたことを基礎として、自分たちが新たに取り組むことは何なのか、伝統を大切にしながら、前に進もうとする考えをもっていることに非常に感動した。
続いて、県立藤岡北高等学校を訪問した。藤岡北高等学校は、学科で「農業」を主とする専門高校で、生物生産、環境土木、ヒューマン・サービスの3科があり、地域との連携や地域貢献の活動に積極的に取り組んでいた。当日は、実習授業の見学をさせていただいたが、大根の収穫、花の栽培、パン作り、ガーデニングなど、将来を見据えて、生徒たちが真剣に実習に取り組んでいる姿を間近で見ることができ、本当によかった。
また、それぞれの学科の取組について、生徒からプレゼンをしてもらったが、取組の内容はいずれもすばらしいものであった。きちんと目標を立て、それに対してどのようにアプローチしていくのか、そのためにはどのような努力が必要なのか、地域の人や専門家も交えて検討していることが本当によく伝わってきた。生徒の皆様がエージェンシーを発揮して、積極的に取り組んでおり、先生方もそれをしっかりと支援している様子がわかり、今後の実業系県立高校の在り方の参考になった。
次に、県内市町村の教育長に御出席いただき、県市町村教育長協議会の第2回定例会を11月13日に開催した。会議では「教育ビジョンの取組について」、「部活動の地域連携及び地域移行について」などを報告し、情報共有を図った。
11月15日には、沼田市で行われた県市町村教育委員会連絡協議会の全体研修会に出席した。研修会では、共愛学園前橋国際大学学長である大森先生の「予測困難な時代を幸せに生きてほしい~Agency、Well-being、そして探究から PBL へ~」と題した講演を聴講させていただいた。大森先生には、「群馬県教育ビジョン」の策定懇談会の座長として、非常に参考となるご意見・ご発言を頂戴したが、今回も、今後の教育ビジョンの理念や取組の参考になるようなお話を伺うことができた。
前回の教育委員会会議以降の主な行事については、11月1日の県立吉井高等学校創立50周年記念式典に小島委員、11月8日の県立太田フレックス高等学校創立20周年記念式典に河添委員、11月13日の令和6年度1都9県教育委員会教育長協議会に私の代理として河添委員に、それぞれご出席いただいた。お忙しいところ、本当に感謝申し上げる。
私からは以上である。次に、教育委員からご報告等があればお願いしたい。
(河添委員)
私からは4つご報告があり、申し訳ないが、少しお時間をいただきたい。
まず10月21日には、前回の定例会の後に、二葉高等特別支援学校を視察させていただいた。限られた時間の中であったが、校長先生をはじめ、関係者の皆様に本当にお世話になった。生徒の状況に合わせた、教育環境整備がよく整えられていることが、説明から伝わった。今後のインクルーシブ教育の群馬ビジョンに向けて、大変参考となる視察となった。
次に、11月8日には、大田フレックス高校の創立20周年記念式典に参加した。フレックスとは、英語で「しなやか・柔軟」という意味があり、生徒一人一人の個性に寄り添い、自分のペースで学ぼうとする生徒の意思を最大限尊重するという教育理念を表している。20年前からその理念のもと、多様な学び方の先駆者として、それぞれの持つ個性に応じ、自分で時間割を作り、定時制・通信制の2つの課程を持つ先進的な高校である。生徒の皆様が、学ぶ意味を本当に大切にして、学校生活を充実させていることがわかるひとときであった。
中でも、生徒会長のスピーチの中で、「私にとってこの高校は単なる学び舎ではなく、大切なコミュニティーである。高校生活で、かけがえのない自分の個性に気づいた。」という思いに触れ、本当に感動した。サヘル・ローズさんの講演も、一人一人の心の奥深くに響く、すばらしい内容であった。講演には質問の時間が設けられており、心を開いて涙ながらに話した生徒に、とても優しく言葉を返してくださり、聞いている皆様も涙を浮かべていらっしゃった。参加させていただき、本当に感謝申し上げる。
続いて、11月11日には藤岡北中学校、藤岡北高等学校を視察させていただいた。藤岡市では、田中教育長のもと、小学校から中学校の縦の繋がり、空間の繋がりを大切に、一貫した教育が全市を挙げて行われていることに大きな価値を感じた。コミュニティスクールや学校運営協議会等がよく機能し、皆で子どもたちを支えているということがわかった。子どもたちも大変活気があり、生徒会の取組も、教育長がおっしゃったように、先輩たちが築いてきた伝統を受け継ぎ、さらにみずからのエージェンシーを発揮しながら、学校をより高めていく当事者となって、成長していることがわかった。
藤岡北高等学校では、たくさんのすばらしい学科・コースで、専門性の高い学びと、さらに探究を進めている姿に感動した。特に、地域の協議会を生徒みずから立ち上げていたことは本当にすごいと思う。大学や行政の専門の方々ともよい関係を築き、より精度と実現度の高い取組につなげようと探究する姿は、すでにプロ意識と確かな実践力を持っているとすら感じられた。まさに、エージェンシーを発揮し、みずから考えを深め、動き出している高校の取組は、群馬県が目指す教育の姿だと実感して参った。2校とも大変お世話になった。
最後に、11月13日には、1都9県教育委員会教育長協議会に、平田教育長の代理として参加させていただいた。協議内容は、「スクールカウンセラーの対応状況について」であった。各県の取組や課題と今後の展望を出し合い、協議を行った。協議に先立ち、文科省初等中等教育局児童生徒課の千々岩課長より行政説明があった。複雑化、多様化する学校の現状に向け、アセスメントを初めとする専門性を生かした対応ができるよう、研修等の機会や、児童生徒と関わる時間の確保、それに伴う予算の確保等について、活発な協議が行われた。加えて、教職調整額の増額の関係など、来年度予算の喫緊の話題についても、担当課より詳細なお話があった。今後とも、よりよい環境教育環境を整えるべく、力を尽くして参りたいと思った。
(日置委員)
私もほかの教育委員と一緒に、10月21日に二葉高等特別支援学校を視察した。生徒はすでに帰宅している時間で、授業は見られなかったが、校長先生から学校の概要を伺い、教室や施設などを見学させていただいた。訪問教育も含め、5つの類型の教育課程を編成しているということで、教室はその生徒の実態に合わせた異なる場づくりができていて、生徒たちが学習しやすい環境を確保しているということがわかった。
その後、寄宿舎を見学させていただいた。そこでは大学受験に向けて勉強している生徒もいれば、全国大会に向けてeスポーツの練習をしている生徒もいて、皆それぞれ目標に向かって、一生懸命頑張っている様子が見て取れた。大変勉強になり、感謝申し上げる。
教育長や河添委員からもお話があったが、11月11日には、藤岡市立北中学校と藤岡北高等学校の視察に行った。
藤岡市は田中教育長のもと、小中一貫教育とコミュニティスクールを強く推進しているということで、興味深く拝見させていただいた。まず、ボランティアの方が多く、ミシンの授業だけでも5人以上のサポートに入っていた。そのほか、書道や郷土教育など、どの授業を見てもたくさんのサポートが入っていた。お話の中で、地域の探究学習では、引率等の関係上、なかなか子どもたちの行きたいところに行けないという課題があったが、これだけたくさんのサポートがいるので、子どもたちが主体的にいろいろな活動ができるようになったとのことである。子どもたちの主体的な学びが、地域の力にしっかりと支えられていることがわかった。
その後、生徒会役員の生徒とお話をさせてもらったが、生徒主体の校則改訂や、毎年、自分たちでスローガンを決めて体育祭を作り上げるとのことで、まさに自律した学習者ということを念頭に置いて、学校全体が動いている様子がわかった。そういった成功体験が「また次をやろう」という、好循環を生んでいると思える。話からは、北中学校の生徒であることに誇りを持っていることが伺え、ここまで意識醸成が進んでいることに少し驚いた。例えば、校則を改定する際にも、中学生が自発的に地域の意向を聞くというような考え方が完全に根付いていて、学校と地域と保護者も皆一体となって、学校を盛り上げていこうという雰囲気が感じられた。働き方改革とも関わるかもしれないが、学校の中だけではなく、地域の人と一緒に学校を作っていこうという、群馬県のよいモデルになると強く感じた視察であった。
藤岡北高等学校では、実習コースの授業を見た後、探究のことをいろいろ聞かせてもらったが、河川のモニタリングを行って、外来生物のザリガニを駆除するための方法を見つけたとか、公園づくり協議会を立ち上げたとか、幼稚園児の芋掘り体験で、幼児の創造性を育むにはどうしたらよいかを考え、最初に幼児に芋掘りの絵を描いてもらい、実際に芋掘りをした後に描いた絵と比較するなど、サポーターの人たちとヒアリングを行って、データ分析や統計的な手法を使っていることも踏まえ、かなりハイレベルな探究をしていたことに非常に驚いた。
SAHやSSHなどの指定校は探究レベルが高いところもあるが、探究学習をもう少し工夫したいと頭を悩ませる普通科高校もあると思う。藤岡北高等学校のような専門高校は30年以上前から課題研究が必修になっていて、ここまで進んでいることを知って、普通科の総合的な学習で困っている先生方にも紹介したいと思った。
(小島委員)
私も皆様と同様の視察をさせていただいた。最初が10月21日の二葉高等特別支援学校の視察であった。もう、20年以上前になるが、重度障害を持った子どもの母親に、通所施設を作るお手伝いをしてもらいたいと言われ、お手伝いをしたことがある。頼まれたときはわからなかったが、障害のある子どもが高等学校を卒業した後、行くところがなくなってしまうので、子どもたちの面倒を見られる施設を作ってもらいたいというお願いだった。当時はイメージが沸かなかったが、今回の視察で、子どもたちの日中の過ごし方や、支援の充実した学びができていることを知ることができた。改めて、特別支援学校の卒業後も支援の継続が必要であるという思いを持った。
また、山本知事が力を入れていることもあり、eスポーツの設備がかなり整っていることが印象的だった。実は、かつてeスポーツには偏見を持っていて、テレビゲームで遊んでいることを、言い訳で「スポーツ」と名付けたと思っていた。しかし、寄宿舎でハンディのある子どもたちが、あれだけ一生懸命に練習している様子を見て、確かにeスポーツという言い方で正しいと、考え方が変わった。すごく参考になった視察であった。
それから、11月1日に、吉井高校の創立50周年記念の式典に参加をさせていただいた。同窓会長が1期生の方で、非常に感慨深い様子でお話をされてたことが印象的であった。
その後、「パックンマックン」というお笑いコンビのマックンが吉井高校のご出身だそうで、二人で式に参加していた。漫才でもやるのかと思いきや、1時間みっちり、国際コミュニケーション力の育成というテーマで、おもしろおかしく話をしていた。その中で、生徒会長を壇上に上げ、英語で「頭」や「目」を何というか聞くと、生徒会長は答えられた。しかし、フランス語やロシア語では何と言うのか知らなかった。そのことから、多くの人が「英語は話せない」というが、頭の中にはすでに多くの英語のボキャブラリーが入っていて、それを並べるだけでも会話に繋がるというような話をされていて、非常に面白かった。
それから、11月11日の学校訪問について、私は企業人として、どうしても生徒を採用するような頭で見てしまうのだが、藤岡北高等学校の生徒は本当に考え方がしっかりしていて、大学受験のことしか考えていなかった自分の高校時代と比較しても、今の段階で十分、企業で通用すると感じた。そのように生徒の成長を促す制度になっているということが印象的で、むしろ、普通科高校で受験勉強だけやっている生徒に比べたら、はるかに大人で、多くのことを考えていると思う。それはすごく大事なことである。私は「とにかく大学に行かなければ」という考え方自体、おかしいと思っている。そういった意味でも、実践的な学習をしている藤岡北高等学校の生徒やその教育に驚きを覚えた。
そのようなすばらしい環境があるにもかかわらず、今年度の倍率が1.0倍に満たないということで、是非周りに宣伝したいと思う。知り合いの子どもが中学校卒業を機に就職先を探しているらしく、自分の会社を紹介しようかと思っていたが、それよりも藤岡北高等学校を紹介しようと思える。それくらい、すばらしいと感じた。
藤岡北中学校は地域との連携が印象的であった。部活動の地域移行やコミュニティスクールには、地域から協力をしてくれる人がどれだけいるかが課題となる。自分は前橋の旧市街に住んでいるが、町内会などの地域集団が昔ほど機能していないと感じている。藤岡北中学校のように、コミュニティスクールという形で、皆が協力して、地域の方々も参加する体制を作っていることが、非常に印象に残った。
(中澤委員)
私もほかの委員と同じく、各学校の視察についてお話させていただきたい。
11月11日の藤岡地区への視察の関係では、藤岡北中学校のコミュニティスクールがすばらしいと思っている。コミュニティスクールの中で、地域の方が運営している「ポラリス」という協議会の活動で、いじめ対策について年間何回か会議を設けているとのことであった。そのように、地域の方がいじめ問題について活動されることはとても大事だと思っている。学校だけの問題ではなく、地域で子どもたちを見守っていく社会があり、いじめの問題をこれだけしっかり考えるという姿勢を大人が見せていることがすばらしい。いじめなどは、学校の中の問題ということで捉えられがちだが、やはりもう少し広く、社会的に見ていく問題である。地域の大人の、子どもたちをそういうことから守っていきたいという思い、しっかりと取り組む姿勢が見られ、大変感激した。
もう1つは、藤岡北高等学校の関係で、先ほどから話が出ているが、専門性の高さにとても驚いた。昆虫のことや環境デザインのことなど、いろいろな専門分野を大学のゼミのように学習していて、すばらしいと思った。加えて、公園を見に行った生徒たちが、子育てという視点で見たり、バリアフリーという視点で見たり、環境のデザインという視点で見たり、外来種の問題として見たり、たくさんの視点で見ることができていた。視点を増やしていくということは、大学に行くにしても、就職するにしても大事である。自分が生きている社会や地域を、これだけたくさんの視点で見られるということが、学んでいる生徒たちのすばらしさだと感じた。実際に体を動かして現地に行き、自分の目で見ているので、体験と考えが繋がっていくことが、藤岡北高等学校における教育のよいところである。
社会を見る視点を増やすということは、いわゆる進学校の生徒にこそ身につけて欲しいし、その視点を持って大学に進学して欲しい。もちろん、実業高校の生徒も含め、誰もが身につけていって欲しいことなので、非常に印象に残った。
(宮坂委員)
私もほかの委員と同じく、10月と11月に学校の視察をさせていただいた感想をお話ししたい。
始めに、10月の二葉高等特別支援学校について、自分の子どもにも知的障害があるので、特別支援学校にお世話になっているということもあり、やはり、学校ごとに特色が違うのだと感じた。一番大きな違いを感じたのはeスポーツの取組で、実際に私とほかの委員も、視線で動かすeスポーツを体験した。自分自身にその知識はあっても、実際にやってみると感動するものであった。本当に少し視線を動かすだけで、カーソルが動くという反応の速さや、そういう方法で子どもたちが学んでいることに驚いた。誰もがITの力で、能力を発揮できる可能性を感じた。同時に、動かないからといって諦めるのではなく、「動かせるところをどう使っていくか」という工夫を改めて感じた。
寄宿舎も視察させていただき、私も初めて見たのだが、今は寄宿舎のように、生活と学びが一体となっている場所は県内にあまりないとのことであった。障害のある人にとって、社会に出てからも引き続き、途切れることなくこういった場所があるとよいと思った。また、寄宿舎には専属の指導員の先生がいて、すごく楽しそうに子どもたちと過ごしていて、先生方も「楽しい」とおっしゃっていたことがとても印象的であった。
11月の藤岡市への視察では、まず、藤岡北中学校に行った。コミュニティスクールのメリットだと思うことは、そういった活動に参加をすれば、保護者が学校で普段の子どもの姿を見られることである。学校の中での子どもの様子は、親でもなかなか見ることができないので、すごくよい機会である。ボランティアとして活躍されている保護者の方も多いと伺った。親の立場として、そういった姿が見られることは幸せだと思う。
授業の中で、藤岡市が共通して取り組んでいる、誰の発言かわかる授業について、授業のフォーマットがしっかり決まっていて、最初に授業の目的を示して、そこに向かって皆でやっていくことが可視化されていることが印象的であった。誰の発言かわかるようになっていることはすごくよいと、委員の間でも話をしていた。
次に、藤岡北高等学校では、自分自身と比べてしまうのだが、自分が高校生のときには、これほどまでに視野が広くなかったと思う。生徒の視点の多さや、視野の広さに感動した。大体の人は社会に出ると、同じ道ばかり通ることが増えると思う。そうではなく、いろいろな道を通ることや、いろいろな人やジャンルと触れ合うことで、可能性がすごく広がると感じた。生徒たちが楽しそうに学んでいて、先生たちもすごく楽しそうな姿であったことが印象的であった。
今回、視察した学校に共通して言えることは、子どもたちが大人に聞きたいときにすぐ聞けるような、関係性、環境があるということである。それはとても大切なことであると思った。
(平田教育長)
ほかに委員から意見等があるか。なければ、関係所属長から報告をお願いする。
(1)インクルーシブ教育推進に係る海外視察等報告
特別支援教育課長、資料1 (PDF:3.29MB)により報告。
(2)「ぐんまインクルーシブフェスタ2024」~ちからあわせる190 マンパワー~について
特別支援教育課長、資料2 (PDF:190KB)により報告。
(3)ハートフルアート展(第30回群馬県特別支援学校児童生徒作品展)の開催について
特別支援教育課長、資料3 (PDF:655KB)により報告。
(4)令和6年度 特別支援学校作業製品のブランド化に係る統一ロゴマーク付与製品の発表について
特別支援教育課長、資料4 (PDF:3.03MB)により報告。
(5)令和6年度群馬県読み聞かせボランティア顕彰について
生涯学習課長、資料5 (PDF:167KB)により報告。
(6)学校部活動の地域連携及び地域クラブ活動への移行に向けた取組について
健康体育課長、資料6 (PDF:86KB)により報告。
(平田教育長)
ただいまの報告について、委員から意見・質問等はあるか。
(河添委員)
2点の質問がある。1点目は、インクルーシブ教育について、実現はもう少し先になると思うが、大変期待をしているところである。デンマークとスウェーデンの取組を、そのまま群馬で行うというわけではないと特別支援教育課長からお話があったが、それぞれの国の1クラスあたりの人数、教員や支援員などの職員数、それから設備も含め、すばらしい環境であると感じた。
そこで、基礎的な教育環境整備について質問したい。これから群馬県がインクルーシブ教育を目指していく方向の中で、どの程度の規模の取組をしていくのか。設備や人の配置も含め、大きく変えようとしているのか。それとも、群馬ならではの取組をお考えなのか、今わかる範囲で教えていただきたい。
(平田教育長)
できるところをできるところから、少しずつ理解を得ながら進めていくという方向であると思う。特別支援教育課長に補足をお願いしたい。
(特別支援教育課長)
ご期待の言葉をいただき、感謝を申し上げる。今、教育長がおっしゃったとおりで、少しずつ進めていく予定である。群馬県で行うにあたっては、どのような環境が必要で、どのような人的支援が必要なのか、これから検討していく。
有識者会議の委員にご意見を伺いつつ、様子を見ながらという方向である。具体的にお話ができず、申し訳ない。
(河添委員)
海外の先進的な取組を、その環境ごと取り入れることができれば、インクルーシブ教育に近づくということはイメージできるが、通常業務もある中で変革を行うのは大変なご苦労であると思う。資料2から資料4の統一ロゴマークの作成等もすばらしい取組である。ご尽力に感謝したい。
2点目は、部活動の地域移行について、資料の中に、保護者や地域住民の深い理解に課題があるというような記載があった。
今後、シンポジウム等を開催予定であるとお示しがあったが、なかなか保護者の方に来ていただくことが難しい場合もあると思う。シンポジウムに来られなくても情報が得られる工夫があるのか、その辺りを教えていただきたい。
(健康体育課長)
シンポジウムの具体的な時期や内容は検討中であるが、シンポジウムの場に来なくても、同様の情報が得られるように工夫はしていきたい。
例えば、リーフレットの作成・配付によって、参加者以外にも情報を発信する予定である。昨年度もリーフレットを作っており、保護者や地域の方々に向けた内容も記載した。今年度も様々に工夫し、部活動の地域移行というものの本質、意義的なものを伝えられるよう取組を進めていきたい。
(河添委員)
保護者や地域住民の理解促進はとても大切なところで、大変な作業だとは思うが、思った以上に、こちらの意図を正しく伝えていくことは難儀であると感じられる。今後ともよろしくお願したい。
(平田教育長)
ひとつの方法だけでは、なかなか保護者や地域の方々に伝わらないので、いろいろなチャンネルで発信していくことが大事である。部活動の地域移行は、教員の多忙化解消のためという理由もあるが、少子化の中で、子どもたちの文化・スポーツ活動をどう維持していくか、どう豊かなものにしていくかという視点の方が大事である。そういった考え方も含め、ご理解をいただけるよう、工夫しながらお伝えしていきたい。
それから、「インクルーシブ教育を進める」ということと、教育ビジョンにうたう、自律した学習者を育成していくために、子どもたちや先生方が「エージェンシーを発揮できる環境を作っていく」ということは、実は同じ方向である。
インクルーシブ教育についても、「インクルーシブ」という言葉から、障害のあるなしだけではなくて、国籍であったり、性別であったり、あるいは経済的な状況など、様々な要素を「含んだ」意味を持つ。いずれにしても、子どもたち一人一人が、その子の持っているよさを、エージェンシーを発揮できるような環境の構築を、少しずつかもしれないけれども、決して止まることなく進めていきたい。時には、三歩進んで二歩下がるかもしれないが、前を向いていきたいと思う。皆様には今後とも、ご指導・ご協力のほど、よろしくお願いしたい。
(日置委員)
この海外視察の件について、日本では不登校の子どもたちがどんどん増えているが、資料に出てくる「不登校対応校」というものは、日本で言えば「学びの多様化学校」のような施設になるのだろうか。
説明の中で、スウェーデンでは、小学校5年生まで不登校の子どもは、地元の学校で対応するということであった。不登校の子どもは、学校に行きたいけど行けない子もいれば、学校の枠を超えて勉強するような子もいて、大きく2つのタイプがあると思う。海外の取組のなかで、日本でも取り入れられそうな取組や、ヒントになりそうなことがあれば教えていただきたい。
また、スウェーデンやデンマークでも、日本と同様に不登校の子どもが増えている状況があるのか、わかる範囲で教えて欲しい。
(義務教育課長)
スウェーデンで実際に視察したのは、ルンドという都市の不登校対応校である。人口約10万人で、桐生市くらいの規模の都市である。不登校の子どもがどれくらいいるかということは、私も一番興味があった。実際には、日本ほど数が多いわけではなかった。ただ、集団教育に馴染めない子が一定数いて、10万人規模の都市でも、不登校対応校が6校もあるということであった。今回視察したのは、そのうちの2校である。
1校は子どもが数人だけの、小さな不登校対応校、もう1校は子どもが15から16人くらいの、少し大きめの不登校対応校であった。日本で言うと、教育支援センターに近い機能を持っているが、スタッフの数や設備はすごく充実はしているという印象であった。
それぞれの対応校が特色を持っており、不登校の子どもがどの対応校に行くかは、校長と教育委員会で相談して決めている。子どもが高等学校に進学しやすいよう、プログラムを重視しており、例えば、対人関係の課題がある子どもは、小さな対応校から始めるなど、不登校の子どもの事情に応じて選んでいる。そのため、途中で対応校を変える場合もあり、私たちが現地で会った子どもは、以前は大きな対応校に行っていたが、合わなかったので、小さな対応校に移動してきたとのことであった。
このように、ルンド全体で不登校の子どもたちに対応するような仕組みができていると感じた。ただ、日本に比べると不登校の子どもの数は圧倒的に少ないので、その分、手厚い対応ができているという印象もある。
(日置委員)
日本の不登校調査では、指導によって学校に戻ることができた児童生徒の割合は何%といった数値を出している。山本知事は、学校に戻ることがゴールではないし、「不登校」という言葉自体も変えるべきというお考えのようだ。
スウェーデンでは、不登校の子どもを学校に戻すことを目的としているのか。
(義務教育課長)
やはり、最終的には学校に戻すということを目標にしながら進めているようである。しかし、日本と同様、無理強いはしないとのことであった。できるだけ、子ども自身が進路を選択できるような形の支援を、本当にチームでやっていると感じた。
(平田教育長)
栗本教育次長から補足等はあるか。
(栗本教育次長)
やはり、不登校対応の最終的なゴールは自律だと思うので、根底の部分は日本と同じであると思う。通常の学校での集団の学びも大事にしながら、可能であれば学校に戻って、一緒に学ぶのもよいし、自分で道を開いていくという子どもにも、適切な進路選択ができるような支援がはすばらしいと思う。不登校対応校ごとに特色があり、それを子どもや保護者が選択できて、さらに途中で変更もできる、とても柔軟性があるという部分は、非常に参考になる。
(平田教育長)
前提として、スウェーデンにおける通常学級での学び自体が、カリキュラムで縛りすぎず、個に応じたものであるということが大事である。多種多様な子どもがそれぞれ、自分たちで学びの場を選んだり、学びの方法を選んだり、そのことをほかの子どもたちが否定せず、お互いを認め合っているところが大きいと思う。
資料1の5ページ右側に記載されているとおり、通常学級の子どもたちも、授業ごとに別室や不登校対応校に行けるというような、柔軟に学びの場所を行き来ができる仕組みがある。いろいろな学びの種類が用意され、いろいろなところで学べるというところに強い特徴があると思った。
(日置委員)
通常の学校が多様化しており、柔軟な学び方ができることで、小学校5年生までは地元の学校で不登校に対応できているのだと理解した。感謝申し上げる。
(中澤委員)
デンマークやスウェーデンは、「インクルーシブ」を意識しているのか、そもそも文化的にそういう視点があるのか。
(特別支援教育課長)
基本的に、当たり前の認識、方針として「インクルーシブ」という視点がある。「多種多様な子どもたちが一緒に学ぶことは当然」という立ち位置から出発している。
(中澤委員)
そうすると、インクルーシブ教育を視察したい言っても、現地の先生方には伝わらないのだろうか。「インクルーシブ」は共通言語として通じるのか。
(特別支援教育課長)
現地の先生方も、「インクルーシブ」と捉えて進めているようである。
(平田教育長)
スウェーデンやデンマークは、社会の構造から相当にインクルーシブが進んでいると感じる。そういった国でも、昔はインクルーシブではなく、社会の構造がインクルーシブになっていくのに従い、学校もインクルーシブになっていったのだと想像できる。
スウェーデンやデンマークでは、以前からインクルーシブ教育であったのか、情報はあるか。
(特別支援教育課長)
教育長のおっしゃるとおりで、始めからというわけではなく、社会等の状況に応じて、意識的に変えてきたという話であった。
(河添委員)
海外の不登校対応校について、対応校ごとに特色があるとのことであったが、具体的にはどのような特色か。
(義務教育課)
今回、全く違うタイプの対応校を視察させていただいた。最初に行ったところは、数人の生徒しか受け入れない、普通の民家のような雰囲気だった。教室が1階と2階にあって、1階が2部屋、2階が3部屋の、日本の教育支援センターに近い施設であった。対人関係が苦手な子でも、安心して来られるような工夫がなされていた。
もう1つのところは、自然環境豊かな立地で、いろいろな体験ができるプログラムがあり、様々な専門家がスタッフとして働いていた。木工や金工、屋外での動物との触れ合いや養蜂など、とにかく体験をたくさん用意していた。スウェーデンは多くの種類の専門高校があるので、子どもたちがそれぞれ、工業系や農業系など、専門の道にも進めるようなプログラムがしっかり組んであることに感動した。
予算的な問題もあるが、いろいろな体験ができる施設を日本でも少しずつ増やしていけると、子どもの選択肢が増えるのでよいと思う。
(平田教育長)
つなサポで、地域機関と繋がる取組の報告があったと思う。おそらく、子どもの体験ということにも少し関わると思うが、総合教育センター所長から補足等はあるか。
(総合教育センター所長)
つなサポの取組状況をご報告させていただく。つなサポは人数がどんどん増えており、今では18市町村、先週末時点で54名の子どもたちが参加している。午前中は15から16名程度、午後は17から18名程度が入室している状況である。
いろいろな企画がスタートしていく中で、今進めているのは、自然史博物館、ぐんま天文台、歴史博物館などの県有施設から、それぞれの職員に総合教育センターへ来ていただき、つなサポと県有施設をカメラで繋ぐような取組である。「バーチャル歴史博物館見学会」や、「天文台で昼間の星を見よう」というような授業で、ある意味、通常の学校の子どもよりも、バーチャルでいろいろな体験ができていると思う。このように、つなサポのスタッフ以外との交流もできるようになってきたところだ。歴史博物館との取組の中では、自分で声を出しで質問できた子もいて、そういう場を踏んでいくことで、刺激を受けて、コミュニケーション能力を発揮できるようになってきたという手応えがある。
愛媛県が群馬県より1年先行して、同じような事業を進めているが、先日、愛媛県と群馬県の子どもたちがバーチャルの中で集まり、合同ゲーム大会を開催した。児童生徒が36名、スタッフ含め50名くらいが参加し、他県の子どもたちとも交流することができた。いろいろな形で、体験や交流が進められている状況である。
(平田教育長)
子どもたちがいろいろな体験をできるようにしたい思うが、1つの方法で用意するのは難しい。オンラインも含め、いろいろな方法でいろいろな場所と繋がることによって、多くの体験できる可能性が高くなると思う。
ほかに質問等はあるか。なければ、教育長事務報告は以上とする。
10 議案審議(非公開)
ここで、平田教育長から、これからの審議は非公開で行う旨の発言があり、傍聴人及び取材者は退室した。
第32号議案 臨時代理の承認について(令和5年度群馬県一般会計補正予算(教育委員会関係)について)
総務課長、原案について説明
異議なく、原案のとおり承認
第33号議案 臨時代理の承認について(群馬県公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について)
学校人事課長、原案について説明
異議なく、原案のとおり承認
第34号議案 臨時代理の承認について(群馬県青少年会館の指定管理者の指定について)
生涯学習課長、原案について説明
異議なく、原案のとおり承認
第35号議案 令和6年度優良図書館群馬県教育委員会表彰について
生涯学習課長、原案について説明
異議なく、原案のとおり決定
第36号議案 令和6年度優良PTA群馬県教育委員会表彰について
生涯学習課長、原案について説明
異議なく、原案のとおり決定
ここで、平田教育長から、これからの審議は教員の人事に関する案件である旨の発言があり、関係課長以外の課長は退室した。
第37号議案 教員の人事について
学校人事課長、原案について説明
異議なく、原案のとおり決定
第38号議案 教員の人事について
学校人事課長、原案について説明
異議なく、原案のとおり決定
第39号議案 教員の人事について
学校人事課長、原案について説明
異議なく、原案のとおり決定
11 教育委員会記者会見資料について
教育委員会記者会見資料について、総務課長が説明。
12 閉会
午後2時35分、平田教育長、教育委員会会議の閉会を宣す。