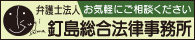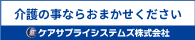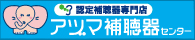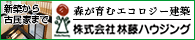本文
令和7年1月教育委員会会議定例会の会議録
1 期日
令和7年1月20日(月曜日)
2 場所
県庁24階 教育委員会会議室
3 出席者
平田郁美教育長、河添和子教育長職務代理者、日置英彰委員、小島秀薫委員、中澤由梨委員、宮坂あつこ委員
4 事務局出席者
栗本郁夫教育次長(指導担当)、古市功総合教育センター所長、小林謙五総務課長、高林和彦管理課長、酒井隆福利課長、鈴木智行学校人事課人事主監、酒井暁彦義務教育課長、高橋章高校教育課長、近藤千香子特別支援教育課長、星野貴俊生涯学習課長、橋憲市健康体育課長、角田毅弘総務課学びのイノベーション戦略室長、羽鳥正総務課次長、井澤悟志総務課補佐(行政係長)、丸山裕美総務課副主幹
5 開会
午後1時00分、平田教育長、教育委員会会議の開会を宣す。
傍聴人は1名、取材者は3名であることを報告。
6 会議録署名人の指名
平田教育長が今回の会議の会議録署名人に河添委員を指名。
7 議案審議等の一部を非公開で行うことについて
議案審議に先立ち、平田教育長から、第43号議案は審査請求に対する処理方針に関する案件であるため、審議は非公開で行いたい旨の発議があり、全員賛成で議決した。
8 教育委員会の行事日程
教育委員会の主要行事日程及び次回定例会議の日程について、総務課長が説明。
9 教育長事務報告
(平田教育長)
まずは、うれしい話題から報告する。
第103回全国高等学校サッカー選手権大会において、前橋育英高校が見事優勝した。1月13日(月曜日)に国立競技場で行われた、流通経済大学附属柏高校との試合では、前半・後半、延長戦でも決着がつかず、PK戦も10人目まで行い、本当に激闘を制しての優勝だった。両校の選手とも、最後まで諦めずにボールを奪い合う、手に汗握る、大変すばらしい試合だった。なお、先日の知事記者会見でも発表があったが、前橋育英高校には、県民栄誉賞特別賞が贈呈されるとのことである。
そのほか、第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会が1月5日から開催され、男子は26年ぶりに県立高崎高校が、女子は高崎健康福祉大学高崎高校が出場したが、両校とも惜しくも1回戦で敗退となった。
また、第104回全国高等学校ラグビーフットボール大会が12月27日から開催され、本県からは明和県央高校が出場したが、惜しくも2回戦で敗退だった。
年末から年始にかけ、情熱を傾け、まっすぐに取り組む高校生のスポーツ大会を見ることができ、胸が熱くなった。
また、スポーツ以外でも、県立桐生工業高校の「建築甲子園」全国優勝や、県立吾妻中央高校の農業クラブ全国大会「平板測量競技会」最優秀賞受賞、県立尾瀬高校の「ディスカバー農山漁村の宝アワード」優秀賞受賞など、各校の生徒がさまざまな分野において、全国レベルで活躍している姿に深く感銘を受けるとともに、大変心強く感じているところである。
次に、前回の教育委員会会議以降に、各委員に出席いただいた行事について報告する。1月8日に行われた「令和7年群馬県議会新春交流会」に小島委員と私が、1月10日に行われた「令和7年群馬県高等学校長協会新年会」に各委員と私が、1月17日に行われた「令和6年度都道府県・指定都市教育委員研究協議会」に中澤委員と宮坂委員に出席いただき、感謝している。中澤委員と宮坂委員には、ぜひ協議会の報告をいただければと思う。私からは以上である。
続いて、教育委員から意見や報告等があればお願いしたい。
(河添委員)
サッカーの決勝戦はテレビで拝見していた。ほかの高校生も全員だが、群馬の子どもたちが一生懸命頑張っている、また、それを支える先生方や保護者の皆さん、本当に喜びが大きいと感じた。
1月10日に開催された県高等学校長協会の新年会に参加させていただいた。日頃から群馬の教育を支えてくださっている、たくさんの皆さんと交流する機会をいただいた。挨拶とともに直接話を伺うことができ、示唆をたくさんいただいた。大変お世話になった。
(日置委員)
私も県高等学校長協会の新年会に参加させていただいた。いろいろな高校の校長先生方から、課題などについてもさまざまな話を聞かせていただき、勉強させていただいた。感謝申し上げる。
(小島委員)
1月8日に、県議会新春交流会に出席させていただいた。一昨年に参加したときは、ほとんど教育委員として認識されていなかったが、今年は県の名札を付けて行ったので、実は教育委員をしていることを説明することができた。教育委員会会議の場では一番年齢が上だが、県議会新春交流会の中にいると、まだ若いという印象を得られた。
それから、1月10日に皆さんと同じく県高等学校長協会の新年会に出席させていただいた。記念式典等に出席した各学校の校長先生から当時の話を伺うなど、いろいろな先生方と話ができ、有意義な場であった。感謝申し上げる。
(中澤委員)
1月10日に皆さんと一緒に県高等学校長協会の新年会に出席させていただいた。心理や特別支援教育の分野で、以前関わった先生方と久しぶりに話をすることができ、今では校長として各方面で活躍され、学校をどのようにしていこうかと本当によく考えておられることが伝わってきて、とてもエネルギーをいただいた。感謝申し上げる。
もう一つ、全国の新任教育委員が参加する、令和6年度都道府県・指定都市教育委員研究協議会に出席したので、報告させていただく。
はじめに、文部科学省から、初等中等教育施策の動向について行政説明があった後、各分科会に分かれてグループ協議が行われた。テーマがいくつかある中、私はGIGAスクール構想についての分科会に参加させていただいた。
このテーマは、今まで私が携わってきた分野と全く違うものであり、知らないことも多かったが、いろいろと事前勉強もさせていただいて、大変勉強になった。その分科会の中で出た話を、少しさせていただく。
群馬県の取組として、このGIGAスクール構想が令和元年度に文部科学省から出たときに、一人一台端末という形ですぐに動き出し、令和3年度からはICT教育推進研究協議会を立ち上げ、県内でいろいろな立場の関係者が集まって協議を行っているという話を事務局から事前に伺った。また、ほかの自治体と少し違う取組として、教育DX推進センターを立ち上げて、教育DX推進リーダーを5名配置、アシスタントを25名配置している。各教育事務所に配置することで、県内の地域間格差の解消に努めているという話を事前に伺っており、これらの取組について、分科会で話をさせていただいた。
分科会のグループには、鹿児島県や滋賀県、大阪市、堺市など計5県2市の委員が参加していたが、話をする中で、三つの共通課題が上がった。
一つは、格差の問題である。地域間、学校間での格差のほか、教員によっても利用頻度や利用の仕方が異なっている。この格差について、いろいろな自治体で課題として上がっていた。
分科会では、ICTを使うことにクローズアップするよりは、授業をどのように充実させていくか、また、授業づくりの中で、ICTを自然と使っていけるような流れができるとよい、という話が出た。群馬県でも、同じ考えに沿って格差是正に取り組んでいるので、非常に期待しているところである。
二つ目は、校務DXの問題である。今は地域によってシステムが異なるため、児童生徒が転校したり、教員が異動したりすると、全然違うシステムを使うことになり、どの自治体でも頭を悩ませている。国の方針に合わせ、都道府県共通のシステムをどう作っていくかということが今後の課題であり、校務支援システムがスムーズに使われていくと、学校の中の校務が効率化されるので、働き方改革にも直結する大変重要な問題であるという共通認識だった。
三つ目は、ネットリテラシーの問題である。ICTが進むことにより、児童生徒がそれに触れる頻度が多くなる、まさに待ったなしの大事な問題であると、どの委員も話していた。
興味深い取組として、大阪市では、情報モラル教育の年間計画が作られていて、例えば国語の授業のある単元の学習の中で、引用元や参考文献の著作権についての話を盛り込み、別のある単元では、IDやパスワードの管理についての話を盛り込む。正しく管理しないと流用されたときや使い回しているときのリスクがあることなど、ほかの授業の単元と紐づけて学習しているという話があった。時間の都合で詳細は聞けなかったが、単発の研修だとそれを受けると終わってしまうが、日常的な学習と紐付けることがとても興味深く大切だと思ったので共有させていただいた。
分科会を通じて、課題の共有のほか、ほかの自治体の教育委員と交流することができ、大変参考になった。
(平田教育長)
紹介いただいた三つの共通課題について、一つ目と二つ目は、群馬県も一生懸命取り組んでいると思うところである。三つ目のネットリテラシーについては、大変大事なことで、ほかの教科と結びつけて学習するというところが、とても面白いと思った。
このことについて、事務局から何か補足があるか。
(義務教育課長)
群馬県でも、令和2年度に、年間計画のどこにネットリテラシーを入れるかということを考えた。市町村でも年間計画を作っているところもあると思うが、実際にそれをどのくらい使っているかということが課題だと思っている。やはり毎日の授業の中で、どういうふうに取り入れていくかが、とても大切なことであるため、単発で終わらないような取組を検討し、資料を市町村に周知していきたい。
(平田教育長)
インターネットが使われるようになったからこそ、より取組が必要な時期になっていると思う。義務教育課、高校教育課でまた検討したい。感謝申し上げる。
(宮坂委員)
私も中澤委員と一緒に、1月17日に、新任の教育委員として、令和6年度都道府県・指定都市教育委員研究協議会に参加させていただいた。
分科会は、不登校対策・いじめ対策をテーマにした二つのグループのうちの一つに参加させていただき、山形、富山、和歌山、高知、福岡の5名の委員と一緒に、各県の取組について話をさせていただいた。各県とも、一人を除いて、私と同じく昨年の10月に就任した方ばかりで、ほとんど同じスタートの新任委員だった。精神科医の先生や、弁護士の方、会社役員の方など、さまざまな職業の方々が務めていた。
いろいろな取組の話を伺う中で、やはり全国的にも、いじめ・不登校という問題に皆さん悩まれて、真剣に向き合って活動していることがわかった。
その中で、富山県がフリースクールなどに通う児童生徒に月額の補助金を出しているという話がとても印象的だった。
ほかにも、SOSの出し方の教育推進にも力を入れて取り組んでいる県もあった。
福岡県では、最近、実際に学びの多様化学校を設置し運営しているとのことで、とても先進的で興味深いと思って話を聞いていた。
私からは、群馬県の取組として「つなぐん」を紹介させていただいたが、皆さんにとても好評で、ワンストップで相談だけでなく支援機関にもつなぐことができ、横断的な「ぐんまMANABIBAネットワーク」で、各機関が官民関係なくつながっていることをとても評価していただいたことが印象的だった。「つなぐん」という名称も好印象だった。
知人のお子さんが最近不登校になり、ちょうど「つなぐん」と「つなサポ」を紹介した。知人は「つなぐん」と「つなサポ」について知らなかったということなので、私自身も普及させていきたいと思った。以上である。
(総合教育センター所長)
「つなぐん」という名称について、各方面からも本当になじみやすい名称であると言っていただいている。「つなぐん」という名称になったことで、非常に周知されてきたと実感している。
一方で、特定の子だけでなく、すべての児童生徒への周知という部分については、課題として認識しており、今後また検討したいと思う。
(平田教育長)
フリースクールの支援については、群馬県では、児童生徒に補助金を出すのではなく、フリースクールに対して支援を行っている。
SOSの出し方の教育についても、群馬県でも取り組んでいるところである。富山県では具体的にどのような取組の紹介があったか。
(宮坂委員)
「SOSの見つけ方・受け止め方事例集」を作成・活用し、サインを見つける資質や能力の育成に取り組んでいるようである。
(平田教育長)
高校教育課、義務教育課から補足はあるか。
(高校教育課長)
群馬県でも、SOSの出し方の教育については、義務教育課と連携しながら、小中高で以前から取り組んでいる。SOSの出し方だけではなく、SOSに気づいた子どもの受け止め方についても一緒に教えていることが一つの特徴だと思っている。
(義務教育課長)
SOSの出し方の教育については、令和元年度くらいに文部科学省から通知があり、各県で取組を始めた。群馬県でも、知事部局のこころの健康センターと連携してプログラムを作成し、公開授業を行ったり、テレビ放映がなされたりした。とても大切な教育であり、毎年同じプログラムだと単発になってしまうという課題が生じるため、総合教育センターの長期研修員と協力して、新たに違うアプローチや見直しを行いながら取り組んでいるところである。
(平田教育長)
総合教育センターの長期研修員は、学校から1年間、教員が総合教育センターに行き、指導主事と一緒に、県が進めたいと考える事業や課題について、テーマに基づいて研究を行っている。また、事務局各課では対応しきれない研究課題にも先駆的に取り組んでもらっており、大変助かっている。
ほかに委員から意見等があるか。なければ、関係所属長から報告をお願いする。
(1)市町村立幼稚園の廃止及び設置について(榛東村)
義務教育課長、資料1 (PDF:45KB)により報告。
(2)市町村立学校の廃止について(安中市)
義務教育課長、資料2 (PDF:43KB)により報告。
(3)市町村立学校の廃止及び設置について(川場村)
義務教育課長、資料3 (PDF:46KB)により報告。
(4)令和6年度いじめ防止ポスターコンクール結果及び表彰式について
義務教育課長、資料4 (PDF:2.51MB)により報告。
(5)令和6年度県立学校卒業式の期日について
高校教育課長、資料5 (PDF:87KB)により報告。
(6)令和7年度県立学校入学式の期日について
高校教育課長、資料6 (PDF:88KB)により報告。
(7)群馬県インクルーシブ教育推進有識者会議(第2回会議)結果について
特別支援教育課長、資料7 (PDF:392KB)により報告。
(8)令和6年度「ぐんま教育フェスタ」~「マナビの一歩」を踏みだそう!~開催要項
総合教育センター所長、資料8 (PDF:92KB)により報告。
(9)第22回ぐんま教育賞 杉の子賞表彰について
総合教育センター所長、資料9 (PDF:88KB)により報告。
(平田教育長)
ただいまの報告について、委員から意見・質問等はあるか。
(河添委員)
市町村立学校の廃止及び設置(川場村)について、川場村立川場学園の前期課程の子どもたちは、徒歩かスクールバスで通うということだが、スクールバスが何台になるか、わかったら教えていただきたい。
(義務教育課長)
1台と聞いている。
(河添委員)
いじめ防止ポスターコンクールについて、1年間の取組の中での位置付けについても説明いただいたところだが、子どもたちが一生懸命、思いを込めながら作品を仕上げたことがとてもよくわかる。最優秀賞の小学3年生の作品が、来年度、いろいろなところでポスター等で活用されるとのことだが、先ほど紹介いただいた、この作品に込められた子どもの思いがとてもすばらしかったので、その思いについてもコメントのような形で一緒に掲載されるようなアイデアはあるか。
(義務教育課長)
事務局としても、この作品の絵はもちろんすばらしいが、標語についても、今県教育委員会が目指そうとしている教育ビジョンの中にも入っているものなので、いろいろなところで標語についても使わせてもらいたいと思っているところである。おそらく、来年度のいじめ防止フォーラムの中でも、この標語が使われていくのではないかと思っている。いじめ防止ポスター単独だけでなく、年間のいじめ防止活動の中で活用していけるよう、この作品が選ばれたということもある。
(平田教育長)
スペースの都合上小さくなってしまうかもしれないが、ポスターの一部に、作品に込められた思いや意図を記載することはできるのか。
(義務教育課長)
ポスターについては、すでに作成を業者に依頼しているところなので、どこまで反映が可能か確認したい。のぼり旗も作っているが、今回工夫して、いろいろな色のものを敢えて使い、多様な人々と一緒に協力し合って、学び、活動していくことを表現している。例えば、のぼり旗の中にこの標語を入れられるか、工夫できる範囲で検討したい。また、ポスターやのぼり旗以外でも、周知する機会がいろいろとあるので、そうしたところでこの標語を大切にしたいと思う。
(平田教育長)
受賞した子どもたちにどこが大変だったかを聞くと、標語を考えるのが大変だったと答える子どもが結構多いので、相当思いを込めて考えてくれているのだなと思っていたところだった。質問いただき、感謝申し上げる。ほかに何かあるか。
(中澤委員)
インクルーシブ教育推進有識者会議について、委員からの「モデル校において、子どもたちはダイナミックに変わり始めている。先生方は、子どもたちが変化していることで手応えを感じている」という意見を拝見し、すごいことだと思った。会議の中で、子どもたちにこういう変化が見られたとか、変化がどのような形で出たかなど、そうしたことが話し合われたのであれば、教えていただけるとありがたい。
(特別支援教育課長)
この意見はモデル校の校長先生から出たものである。報告にあるように、現在、知的の特別支援学級の児童と知的の特別支援学校の児童との交流及び共同学習を授業研究しながら行っているが、これについては、子どもたちが関わりながらというところに教員を据え置いて、子どもの主体的な動きを尊重できるようにしている。教員が手を出しすぎない、子どもが主体的に学びに向かう姿が見られ、今後の授業研究に結びつけたいと思う。また、学校全体の中では、ブロックチーム担任制やYUMEルームという自由に出入りできる部屋を設けているので、そうした新しい取組に対して、子どもたちが前向きに変化に応じようとしているという話があった。今まではずっと同じ先生が学級担任をしていたが、例えば週替わりなどになることにより、いろいろな先生と関わる機会ができたことに、とても関心を持っている子どももいれば、最初は不安に思っていたが、だんだん慣れてそれを楽しめるようになる前向きな姿が見られた子どももいて、互いに認め合うことや、さまざまな人が関わるということに結びつけていけるといいと思う。
(中澤委員)
子どもたちが変化に応じていく、呼応している様子がよくわかった。感謝申し上げる。
(平田教育長)
ほかに質問等はあるか。なければ、教育長事務報告は以上とする。
10 議案審議(非公開)
ここで、平田教育長から、これからの審議は非公開で行う旨の発言があり、傍聴人及び取材者は退室した。
第43号議案 審査請求に対する処理方針について
学校人事課人事主監、原案について説明
異議なく、原案のとおり承認
11 教育委員会記者会見資料について
教育委員会記者会見資料について、総務課長が説明。
12 閉会
午後2時1分、平田教育長、教育委員会会議の閉会を宣す。