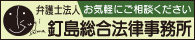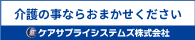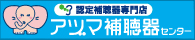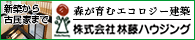本文
令和6年9月教育委員会会議定例会の会議録
1 期日
令和6年9月17日(月曜日)
2 場所
県庁24階 教育委員会会議室
3 出席者
平田郁美教育長、沼田翔二朗教育長職務代理者、代田秋子委員、河添和子委員、日置英彰委員、小島秀薫委員
4 事務局出席者
高橋正也教育次長、古市功総合教育センター所長、小林謙五総務課長、高林和彦管理課長、酒井隆福利課長、西村琢巳学校人事課長、藤村正博義務教育課次長、高橋章高校教育課長、上原ひとみ特別支援教育課次長、星野貴俊生涯学習課長、橋憲市健康体育課長、角田毅弘総務課学びのイノベーション戦略室長、羽鳥正総務課次長、井澤悟志総務課補佐(行政係長)、丸山裕美総務課副主幹
5 開会
午後1時00分、平田教育長、教育委員会会議の開会を宣す。
傍聴人は2名、取材者は3名であることを報告。
6 会議録署名人の指名
平田教育長が今回の会議の会議録署名人に日置委員を指名。
7 議案審議等の一部を非公開で行うことについて
議案審議に先立ち、平田教育長から、第25号議案は議会に提出する案件であるため、審議は非公開で行いたい旨の発議があり、全員賛成で議決した。
8 教育委員会の行事日程
次回定例会議の日程について、総務課長が説明。
9 教育長事務報告
(平田教育長)
初めに私から一言申し上げる。
9月4日に教育委員と学校訪問を行った。今回は、南牧村立なんもく学園と上野村立上野小学校を訪問した。
なんもく学園は、今年4月に開校したばかりの義務教育学校で、真新しく、様々な工夫がなされた素晴らしい校舎を見学させていただいた。私が特に素晴らしいと感じたのは、校舎の真ん中に、デンやボルダリング設備が設置されている図書館があり、9学年の子どもたちが自ら自由に学習ができる工夫がなされている点である。全校児童生徒20名の小規模校ならではの取組等について、学校関係者や村の教育委員会の方々と意見交換をすることができ、さらに、子どもたちと一緒に給食を食べることができた。非常に楽しく、有意義な時間であった。
上野小学校は、単元の中で一部分を子どもたちそれぞれの自由進度で行う、自由進度学習を取り入れている授業を実際に見学させていただき、その後、6年生の児童から話を伺うことができた。自由進度学習の時間では、子どもが教室以外の場所で自ら学んでいる姿に感動した。また、意見交換でも、自由進度学習により子どもたち自身も「物事に積極的に取り組めるようになった」と発言していたことを聞いて、非常に頼もしく感じた。
次に主な出席行事について、報告する。
8月21日は、経済産業省主催の「学校活動支援サービス体験&研修会 群馬」のトークセッションに参加した。
さいたま市の細田前教育長、経済産業省の五十棲教育産業室長と「働き方改革と民間サービスの活用」をテーマに、今後の展望などについて話合いをした。数多くのご経験をされているお二人の示唆に富んだご発言を伺いながらの話合いから、大きな刺激を受けることができ、また、本県の取組は間違っていないと感じる機会となった。
8月23日には、沼田委員が会長を務める「群馬県地域づくり協議会」主催の講演会等が、県庁32階のネツゲンで開催され、当日、会場で聴講した。加賀市の島谷教育長の「自分事、当事者になるってどういうこと?」というテーマの講演、その後の島谷教育長と藤岡北高校及びぐんま国際アカデミーの生徒たちとのトークセッションは大変興味深く、また勉強になった。
そのほか、8月29日~30日に長野市で行われた、令和6年度1都9県教育委員会教育委員協議会に河添委員に出席いただいた。
私からは以上である。次に教育委員からご意見、ご報告があればお願いしたい。
(沼田委員)
私は9月4日の教育委員学校訪問でなんもく学園と上野小学校を訪問した。
今回の訪問先は、群馬県の中ではとても小規模な学校であったが、10年後の教育や学びの、当たり前の姿を感じることができた貴重な学校訪問になった。
なんもく学園の子どもたちに、「新しい学校になってどうか。授業はどうか。」という質問をしたところ、子どもたちからは「異年齢の人たちとも関わりやすくなり、過ごしやすくなった。それが毎日楽しい。」という回答があった。
なんもく学園は義務教育学校なので、1年生から9年生、それぞれがそれぞれに学んでいるわけだが、その特徴を生かして、異年齢の子ども同士が当たり前に関わっている姿があった。
振り返ってみると、自分の小学校時代には、普段の授業において他学年の子どもと関わることは少なく、先輩や後輩と関わる場面は学校行事が主であった。しかし、なんもく学園の子どもたちにとっては異年齢の子どもたちと学ぶ事が当たり前であり、これは恐らく、人が人として成長していく上で非常に重要な環境なのだろうという事を彼らから学んだ。
上野小学校の子どもたちは、「自ら学習に取り組み、友達と相談しながら授業を受けられるのが楽しい。」と話していた。新しいことを発見したときの喜びや、あるいは難しい問題に出会ったときに、その場で友人と共有することができる授業もまた、子どもたちが人として成長する上で非常に重要であるということを、上野小学校の児童たちから学ばせてもらった。
また、先生たちの声も伺った。どちらの学校の先生も、「新たな取組に挑戦し、試行錯誤できるのが楽しい。」と、口をそろえて話していた。先生たちの挑戦は、それを支える管理職やその自治体の事務局の存在が非常に重要であるということも同時に学んだ。
群馬県の教育ビジョンの最上位目標には「自律した学習者の育成」と表記されているが、私は「自律した学習者」というものを遠い存在に感じており、関係者が協力して目標達成のために取組を積み重ねていくことが、目標の達成に繋がるものと考えていた。しかしながら、上野小学校の児童たちは、既に自律した学習者であったと感じた。つまり、「自律した学習者」とは、既に子どもたちの日常にあり、今の子どもたちにとっては当たり前になっていく姿であるということを、今回の訪問で学んだ。現在のなんもく学園と上野小学校の取組が、群馬県におけるひとつのスタンダードになると思えば、そこから学びたいと思う教職員や、地域住民は数多くいると考えられる。県教育委員会としては、これらを紹介していくことも、役割のひとつではないかと思った。
私からの報告は以上となる。
(代田委員)
私も9月4日に、なんもく学園及び上野小学校を訪問した。
なんもく学園では、校舎が綺麗で、自然の中で育っている子どもたちを見て、自分もここで学びたいという気持ちになった。
学園の職員に、コミュニティスクールのことについて質問したが、なんもく学園が開校する前から、収穫祭であったり、防災キャンプであったり、年に4回から6回ほどの行事をしていたということで、委員は8名いるそうだ。私の感覚では、コミュニティスクールの委員数としては多い方で、地域一体となってなんもく学園を支えていく姿が少し見られたと思う。
課題として、少人数学習のため、自分の考えを言うことや、他者の意見を聞く機会が少なく、競う気持ちが足りないとおっしゃっていた。
私が思うに、競う気持ちが足りないというよりも、少人数学習で育った子どもたちが、なんもく学園で育ったこと、学習したことを自分たちの魅力や強みとして考え、外部に発信してもらえたらよいと思った。
また、上野小学校で特に気になったところは、6年生の算数の授業で、4人の児童が図書室で並び、それぞれ勉強していた姿に大変興味を持った。1人は、自分の大事な受験勉強のために持参したワーク、1人は漢字練習、他の2人は互いに教え合いながら問題を解いている姿から、それぞれ自分が今、何をしたらよいのか、責任を持って学習をしていると感じられた。学校で学んだことを家庭に持ち帰って、自分で決めて、自分から学習したいという気持ちを高めているのだと思う。それぞれ子どもたちが自立していく姿が見られた。簡単だが、以上である。
(河添委員)
私は8月21日に、「学校活動支援サービス体験&研修会 群馬」にオンラインで参加させていただいた。感謝申し上げる。
また、8月29日には1都9県教育委員会教育委員協議会、そして9月4日には学校訪問に参加し、大変貴重な経験をさせていただいた。
その中から、本日は1都9県教育委員会教育委員協議会についてご報告をさせていただきたい。
今回、分科会での協議テーマは、「非認知能力と認知能力をバランスよく育むための取組について」であった。
私が提案したテーマを開催県である長野県が採用していただいたことから、本県の取組状況や、取組には環境づくりが大切であるという自らの思いを含め、提案理由を全体会でお話させていただいた。
群馬県教育ビジョンでは、自分で考え自分で決めて、自分で動き出す「エージェンシー」を発揮する自立した学習者の育成を目指しているということ、非認知能力は自立した学習者のベースとして考えていること、自ら伸びゆく力を発揮しやすい取組とともに、環境づくりについても、群馬県は大切にしていくということ等をご紹介させていただいた。
教育は「人」であるから、子どもたちのよさを引き出していく伴走者である教員のよりよいコンディションを作っていくため、学校の働き方改革をさらに推進していく必要があるという観点も含めて協議をした。
各都県の優れた取組等を会議資料、分科会、情報交換会等でたくさん知ることができたので、少しお時間をいただき、2つ報告をさせていただきたいと思う。
まず1つ目は、これまでも報告させていただいているが、山梨県の25人学級について、その経過も含め、子どもたちにも、教職員にも、保護者にも、とてもよい効果があるというご報告をいただいた。やはり学級の少人数化というのは、今後大切なポイントの1つになるのかではないかと思っている。
2つ目は、今回非認知能力と認知能力をバランスよく育むために行っている埼玉県の取組が大変興味深く、自分の現場経験からも「そのとおり」と思った視点があり、ぜひ皆さんと共有したい。
埼玉県教育委員会は独自で平成27年度より、小学校4年生から中学校3年生までの学力検査を行い、非認知能力や学習方法などの質問調査を行っている。そのデータを研究機関に委託して分析した結果、主体的・対話的で深い学びの実施に加え、大切な要素がわかったとのことである。それは、「学級経営」が子どもの非認知能力や認知能力を向上させ、子どもの学力向上にも繋がるということであった。
これは義務教育のみにおける結果だが、私も今まで、学級経営が子どもたちの非認知能力、認知能力の育成に最も大切なことの1つであると感じてきた。学級開きから始まり、よりよい集団づくりを子どもたちと学級担任で1年を通して、継続的に日々育んでいく営みは、何より子どもたち一人一人のよさを伸ばしていくために、大切な学校や教員の役割だと思っている。
学級経営が学びやエージェンシーの土台として大切であることは、教員経験者の全員が共感することなのではないかと感じている。最近は学級経営があまりクローズアップされていない感覚もあったが、やはり重要であったという分析結果である。伴走者としての教育や、自由進度学習も含め、その土台が大切になると思っている。
埼玉県教育委員会はこの結果に基づき、児童生徒の学力と自己効力感に大きな伸びが見られた学級の担当者にインタビューして具体的な指導方法を掴み、研修等で活用したり、学級経営のリーフレットを作成して全教員に配布したり、優れた指導技術の普及に向けて授業を撮影し、解説付きの研修資料を作成して授業改善に努めたり、今後、学級経営にかなりの力を入れていくというお話であった。私も埼玉県教育委員会の委員に後日詳細を教えて欲しいとお願いしたが、可能でれば事務局の皆さんも情報収集していただき、群馬県の非認知能力向上に向けた参考になればよいと感じている。
他都県のよい取組を学び合えることは、こうした協議会に参加する意味の1つである。もちろん、今回紹介させていただいた群馬県の取組も、他県からお褒めの言葉をたくさんいただいた。さらに、他県のよさを取り入れていけたらよいと思う。
文部科学省初等中等教育局の武藤教育課程課長からも、大変貴重な行政説明をいただき、情報交換会で色々なお話ができた。先ほど、なんもく学園や上野小学校のお話で、自由進度学習等の話題も出たが、新任教員が一斉授業や学級経営にしっかり取り組むという経験により、伴走者としての役割や、子どもたちに任せられる部分がわかり、手だてにも実践にも繋がるのではないかという話題や、これから採用される教員にとって、いきなり自由進度学習などの授業形式になると、むしろ大変なのではないかという話題で意見交換をした。
令和の日本型教育に示されているように、授業の形態や発達段階、その他状況に合わせ、一斉授業や自由進度学習も含め、二項対立で議論するのではなく、価値やよさを生かしながら組み合わせていくことが最善だと感じている。今後に生かして参りたい。
今回、参加の機会をいただき、皆様に感謝申し上げるとともに、これまで以上に頑張っていきたいと思う。以上である。
(日置委員)
私も、教育長と教育委員の皆さんとともに、9月4日の学校訪問に参加させていただきいた。
なんもく学園は、先ほどもお話があったが、学校と言われないとわからないような、非常に開かれた空間で、子どもたちの自由な発想が自然に出てくるよう、校舎設計を工夫したということであった。
全校児童生徒が20名に対し、教員と支援員が26名在籍しているということで、クラスによっては教員と支援支援員の方が子どもよりも多く、まさに個に応じた指導がなされているということである。一方で、前期課程(小学校課程)は各学年1名から3名ということで、協働的な学習はどう工夫しているのかと、非常に興味を持って視察してきたが、総合的な学習の時間などでは、万場小学校とオンラインで繋ぐなど、工夫されているという話であった。しかし、学年を跨いで行うことができないような教科もあり、開校してまだ数ヶ月しか経っておらず、手探りといった状況のようであった。これからは少子化もあり、次々と同じような学校が増えてくると思われる。この先、そういった学校のモデルとなるような活動が行われていくことを期待したい。
また、現在、中学校部活動の地域移行を進めているが、その理由の1つが少子化で、1つの学校だけでは部活動ができない競技もあり、この学校はどうしているのか非常に興味を持って視察してきた。後期課程の8年生(中学校2年生)は5人中4人がテニス部に入っているということであった。9年生(中学3年生)はバスケットボールをやっているとのことだが、学校の部活動にはないので、スクールバスで自宅に帰ってから保護者に送ってもらい、地域のクラブチームで活動しているという話だった。地域のスポーツクラブ等の受け皿があれば、こういう小さな学校でも色々な部活動をできるようになったことは非常に素晴らしい。一方で、やはり保護者の負担は大きいことは課題であり、子どもがやる競技によっては、仕方のないことなのかもしれないと思いながらお話を伺っていた。
もう1つは、子どもを中心に村を活性化したいという、村の強い要望もあり、地域の大人たちの学び場として、学校で料理教室や俳句講座を開催しているとのことであった。学校が地域の力を借りるだけではなく、地域のための学校を目指していく姿勢も、これからの学校のモデルになっていくのではないかと思った。
上野小学校では、自分で考え、判断し、自分から行動するという、群馬県教育ビジョンに記載された「エージェンシー」の育成に特に力を入れている学校であった。
各学年の授業を視察したが、まさに子どもたちが能動的に動いていると感じた。例えば、小学校4年生の理科の授業では、「雨が降ってできた水たまりの水はどこに行くのだろうか」という問いに、子どもたちが自分で仮説を立て、実験計画を作って検証するという場面だったが、子どもたちは皆それぞれ、校庭に行っている子もいれば、ベランダにいる子、教室で実験器具を作っている子もいた。自分で考えた仮説を証明するために、一生懸命、目を輝かせながら取り組んでいる姿が印象的であった。普通の授業であれば、児童が立てた仮説がある程度集約され、一斉に検証するという進め方だと思うが、そういった予定調和的な部分は全く見られなかった。学校の目標である、自分で考え、判断し、自分から行動するということを、しっかり授業に落とし込めているという印象であった。他の学校にとっても、非常に参考になる授業であると感じた。以上である。
(小島委員)
私も、8月21日のGメッセで開催された、「学校活動支援サービス体験&研修会 群馬」に参加させていただいた。参加した理由は2つあり、1つ目は、労働時間の短縮に関わるツールや教育のツールは今、どうなっているのかという疑問である。2つ目は教育産業の会社はどういうことをしているのかを知りたかったという理由である。教育長も出席されたトークセッションを聞いていて、働き方改革における様々な工夫がよくわかった。その後は展示を見たが、軽く見ただけではツールの中身まで詳しくわからず、どのくらい役に立つのかは、今ひとつわからなかった。
このイベントの主催は経済産業省の商務・サービスグループ教育産業室である。このグループの主な目的は、教育産業の会社に需要や採算が成立し、経営が立ち行くのかというところにある。少なくとも、働き方改革、労働時間を短縮するためにどのようなツールがあるのかというスタンスには立ってないと思う。本来ならば、文部科学省が主導となり、働き方改革のスタンスに立った上で、ツールを調べるというのが筋である。このイベントに参加する前から、文部科学省の名前が少しも出ていないところは疑問で、少し気になったところである。
それから、9月4日の学校訪問は私も参加し、南牧村と上野村それぞれの義務教育学校、小学校を見せていただいた。
非常に参考になり、個別で色々な授業を受けたり、小学校と中学校の枠にとらわれない勉強ができたりする点はメリットがあると思った。
なんもく学園で先生や教育委員会の方々と話をして気になったのは、学習指導要領が小学校と中学校と分かれていて、一緒にできる部分がないとおっしゃっていたことである。義務教育学校として指導していて、不都合が生じる部分や改善が必要な部分があるのであれば、その点を文部科学省等に要望していただいた方が今後のためにもなる。改めて、学校や教育委員会が声を上げるべきであるという印象を持った。
また、60数年ぶりに給食を食べた。自分は前期課程(小学校)の児童と、後期課程(中学校)の生徒とご一緒させていただいた。一緒に食べていた小学生は味噌汁をご飯にかけて、一気に掻き込んでいた。自分が小さいときには、そういう食べ方をすると怒られたが、その場で注意した方がよいか迷い、誰も何も言っていなかったので、何も言わないでおいた。面白い食べ方をしているなと思いながら、給食の時間を過ごした。自分が学校に通っていたときの給食はパンしか出なかったが、初めてお米の給食を見て、大変印象深かった。
上野小学校では、既にほかの教育委員からもお話が出ていたが、自由に勉強をさせているところが印象に残った。特に6年生の授業では、代田委員のおっしゃっていたように、図書室に行って3人で相談しながら勉強している子や、教室の中に残っている子、隣の教室に行っている子もいて、完全にフリーな授業に驚いたとともに、大変興味深かった。
授業が終わった後に、児童を含めて会話した中で、授業でわからないことがあったとき、最初に誰に聞くのか尋ねたところ、「友達に聞く」という答えが返ってきたのがとても印象的で、よい傾向だと思った。昔の授業は生徒対先生のようなイメージであったが、そうではなく、一緒に勉強している児童同士で相談することで学んでいくということ自体が自立的な学習につながる。例えば、算数の答えは1つだが、答えにたどり着くまでには色々な考え方がある。そういうときに、先生から教えてもらうのではなく、子ども同士で考えるという姿勢は大変素晴らしいと思った。
日置委員のおっしゃっていた理科の実験では、降った雨がどこ行くのかを探しに、皆が出かける中、教室に一人残っていた男の子に「君は行かないの。」と聞いたら、「皆が外へ行ったから、自分はここにいればよい。」という答えが返ってきて、「なるほどな。」と思った。児童がそれぞれ色々なことを考えながら、生き生きと勉強している姿が非常に印象に残っている。こういうやり方が全体に広がれば、子どもたちもよりよい方向に変わってくるのではないかと考えていた。以上である。
(平田教育長)
委員それぞれからご報告、ご意見等いただいたところである。ご質問や補足等があれば、お願いしたい。
河添委員から、埼玉県教育委員会にかかるお話があった。義務教育課、総務課学びのイノベーション戦略室、高校教育課等で話し合い、情報収集していただけるとありがたい。
小島委員からお話のあった、経済産業省の商務・サービスグループ教育産業室は、例えば、「未来の教室」など、教育に関する多くの事業を行っている。昨年度、高校教育課の職員を教育産業室に1名派遣した。同じように、各都道府県の職員や、文部科学省の職員も数多く派遣されていると聞いている。文部科学省とは別の視点から教育を見ていくという色合いが強い部署であると理解している。
(高校教育課)
イベントを担当した経済産業省の部局には、昨年度、当課から職員を派遣した。経済産業省の職員をはじめ、文部科学省から出向した職員、全国各地の教育委員会から出向した職員が協力し、様々な視点からイベントを開催していると聞いている。
(平田教育長)
もちろん、こういったイベントの目的として、1つの商品の売り上げをどのように安定させるかというような視点もあると思う。ただ、どちらかというと、産業のベースも人づくりであるから、産業の観点からも人づくり、すなわち、教育に関わっていこうという考えがあるのではと考える。
ほかに委員から意見等があるか。なければ、関係所属長から報告をお願いする。
(1)第6回OECD2030年の教育と技能の未来に向けたグローバルフォーラム」の群馬県での一部開催について
総務課学びのイノベーション戦略室長、資料1 (PDF:291KB)により報告。
(2)「不登校児童生徒の学びを考える会」の実施について
総合教育センター所長、資料2 (PDF:165KB)により報告。
(3)生成AIの活用にかかる教職員研修の実施について
総合教育センター所長、資料3 (PDF:225KB)により報告。
(平田教育長)
ただいまの報告について、委員から意見や質問があるか。
(代田委員)
質問は特にないが、不登校児童生徒の学びを考える会について、分科会の保護者の繋がり部会は素晴らしい取組だと思う。やはり、不登校児童生徒を抱える保護者の方は孤立してしまう人も多く、こういった繋がりはとても大事になる。
これからもどんどん、まずは群馬県内から発信していただけると、本当に助かる人が多いのではないか。
(河添委員)
代田委員のご発言と同じ部分になるが、今回、不登校児童生徒の学びを考える会に、31名もの保護者の方が参加していただいたことは、大変よいことであると思った。
今まで、保護者の参加がなかったことをかえって不思議に思うくらいであるが、今回、保護者に参加していただくことになった経緯について教えていただきたい。
(高校教育課長)
代田委員、河添委員からご発言をいただき、大変ありがたい。ご質問の件については、実は少し苦労した部分もある。十分ご承知のとおりかと思うが、不登校児童生徒を抱える保護者にとって、なかなかこういった集まりやイベントに出ること自体、かなりハードルが高い。実際、自分ひとりの意思で申し込めるかというと、かなり困難な状況であると思われる。
今回、保護者にご参加いただくことに決めた経緯で大きかったのは、伊勢崎市内の中学校に伝統的にある、不登校生徒の保護者同士の繋がりの会に接触できたことである。つなサポ、つなぐんの校内研修でその中学校に行く機会があり、お話ができた。そこで、保護者の方々に相談したところ、さらに保護者の繋がりができると嬉しいという声を聞き、核となる方々に参加していただけた。
加えて、今回参加していただいたうち、3名の保護者の方が、関わりのある保護者の間に広めていただいたことや、つなサポ、つなぐんを活用して周知できたというところで、「知っているところに出かける」ような意識が生まれたと同時に、周りの方の多くが参加するのであれば、参加しやすいという状況も生まれたと思う。
そういった面でも、つなぐんで相談機能を集約し、相談から支援を一体的に行っている効果が出たと感じている。
(河添委員)
31名の方に出ていただいたということ、参加者からよい反応があったということを踏まえると、次回は、これだけの方が参加したという評判が広まり、さらに参加しやすくなるという好循環が生まれる期待感がある。非常に素晴らしい取組である。感謝を申し上げる。
(平田教育長)
これがはじめの1歩ということである。なるべく参加しやすい環境を整え、全県に広まっていけばよいと思う。
(日置委員)
生成AIの活用に関連して、これからは授業や業務において、AIをうまく使えば、作業が楽になったり、通常では考えつかないような発想が生まれたりすると思う。例えば、社会の授業では、AIを活用した情報取得を紹介していたが、自分としては、出典がはっきりしないので、なかなか使いにくい部分もある。研修では学べる教職員にも限りが出てしまうので、どういうときにAIを使うのが効果的なのか、指導プラン等にも記載していただけると、多くの教職員の助けになるのではないか。以上、感想である。
(小島委員)
生成AIについて、例えば、読書感想文を作らせてしまうような、先生が活用するよりは、児童生徒が便利に使っている可能性があるという気もする。そういった状況への対策はどのようにしているのか。小中高の各段階で、児童生徒による生成AIの使われ方等は、ある程度把握されているのか。宿題や課題などに、どうにでも使える感じがする。
(高校教育課長)
生成AIは使い方を間違えると、感想文等の作成にも活用できてしまうという課題もある。
高等学校の場合には、情報の授業の中で、インターネットの使い方を含めた情報リテラシー教育の中において、生成AIの使い方も扱っている。
加えて、日々の授業で基本的に1人1台端末を使っているので、日頃から教員がモラル的なことも含め、しっかりと指導している。
(小島委員)
とても難しいテーマである。例えば、電卓を使って計算した方が圧倒的に早いわけで、電卓を使うこと自体を悪く言う必要もない。生成AIも使いようによっては、大いに役に立つ。ただ、自分で考えなくても、簡単に答えが出てきてしまうところが、少し問題となる気もする。
こういった問題の、学校における指導の仕方が気になった。おそらく、学校もまだ混乱している状況なのかもしれない。どうしたらよいのか、私も明確な答えを持ち合わせていない。
(平田教育長)
この問題は、発達段階によってもかなり指導の仕方が違ってくると思う。
例えば、小学校の時点では、作文を書くことで論理性が育まれていく。素敵な文章を作ることだけを目的にするのであれば、生成AIが作ればよいかもしれない。そうではなく、本来、文章を書く力を身につけるとともに、そのベースにある論理性などの思考力等を身につけ、自分自身を磨くという部分を考えるべきである。発達段階によって、生成AIに任せてよい部分と、自力で考えなければならない部分はあると思う。
個人的には、高校生くらいになれば、生成AIを活用する場面があってもよいと思う。出典なども理解し、自分が誰かの著作権を意図せず犯してしまう可能性もあるので、そういったことも勉強した上であれば、使うことができるのではないか。
義務教育段階、特に小学校低学年については、まだAIの使い方を覚えるのではなく、自分で文章を考えることによって、能力を身につける方を大事にする必要があると考えている。
(総合教育センター所長)
高校教育課長からも話があったが、義務教育においても、情報モラルの分野で、生成AIにできること、できないことというような内容を指導している。
生成AIで特に話題になったのは昨年の夏休みの時期で、宿題の読書感想文などを作れるということがかなり問題視されていた。これについてはもちろん、生成AIの利用は避けるよう指導は行っている。その上で、夏休みの課題には図画、工作、作文、研究など様々であるが、応募要件で生成AIのものは認めないと明記されているものもあるが、逆に認めているものもある。そういった点では、棲み分けされ始めていると思う。
もう1点は、保護者が生成AIを利用して、子どもの読書感想文を書くことについてである。これは昔から生成AIがない時代も含め、保護者が子どもの宿題をやるということは問題であった。その部分については、教員がしっかりと目を通して、見極めて指導することは必要であると考える。
それから、平田教育長からのご発言に補足させていただくと、小学校高学年から中学校にかけて、国語の学習では推敲という分野がある。現在、国語の指導では、既にできている文章等に自分の考えを足す、変えるということも、国語の力として重要視されている。そのような考え方では、生成AIを作らせたものに自分で手を加える能力も必要なのかもしれない。例えば、修学旅行のプランを子どもたちが立てるときも、自分で調べ、考えるからこそ意味があるものだと思っていた。しかし、効率が重視される今の時代、既に作られたものを、自分たちで見極めてどう直していくか、使いやすくしていくかという観点など、求められている能力が少しずつ変わっているのかもしれないと、個人的には感じている。
(平田教育長)
資料1のOECDのグローバルフォーラムには、何名程度の生徒たちが参加する予定であるか。
(学びのイノベーション戦略室長)
県内の高校生が50名以上参加する予定である。海外からの生徒等の参加数は、現時点ではわからない。
(平田教育長)
OECDの素晴らしいと思うところは、何か物事を考えるとき、必ず生徒等も入れて、教員、学術的専門的知識を持っている方、行政の方も含め、対等な立場で話し合うところである。
本県の生徒たちが50名以上参加をする中で、教育委員がご参加いただける場合は、いくつかのグループに別れて、生徒と同じテーブルで議論していただくということになる。もし、お時間があれば、ご参加いただけると大変ありがたい。
やはり、一番の当事者は生徒である。生徒も一緒にこれからの学びを作っていくために、先生の教え方や指導、支援の仕方という議論にも生徒が加わることは大変素晴らしい。これを通じて、すてきな提案が生まれたり、本県の生徒たちが力をつけたりしていくと思う。大変楽しみにしている。教育委員の皆様にも参加について、是非ご検討をお願いしたい。
ほかに何か意見等はあるか。なければ、以上で教育長事務報告を終了する。
10 議案審議
第23号議案 群馬県公立学校職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則について
学校人事課長、原案:第23号議案 (PDF:333KB)について説明
異議なく、原案のとおり決定
第24号議案 令和7年度群馬県立特別支援学校高等部生徒募集定員について
特別支援教育課長、原案:第24号議案 (PDF:94KB)について説明
異議なく、原案のとおり決定
11 議案審議(非公開)
ここで、平田教育長から、これからの審議は非公開で行う旨の発言があり、傍聴人及び取材者は退室した。
第21号議案 臨時代理の承認について(令和6年度群馬県一般会計補正予算(教育委員会関係)について)
総務課長、原案について説明
異議なく、原案のとおり承認
12 教育委員会記者会見資料について
教育委員会記者会見資料について、総務課長が説明。
13 閉会
午後2時18分、平田教育長、教育委員会会議の閉会を宣す。