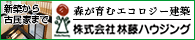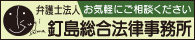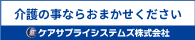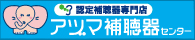ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
令和7年度群馬県食品衛生監視指導計画(案)に関する意見の募集結果について
更新日:2025年3月28日
印刷ページ表示
県では、令和7年度群馬県食品衛生監視指導計画(案)について、令和7年2月19日(水曜日)から3月20日(木曜日)までの30日間、インターネット(ぐんま電子申請受付システム)、郵便、ファクシミリ、電子メール、持参により、広く県民の皆様から意見の募集を行いました。
このたび、寄せられた御意見(延べ13件)及びそれに対する県の考え方を下記のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
今回、御意見をお寄せいただきました方々の御協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後とも、県行政の推進に御協力を賜りますようお願い申し上げます。
政策等の題名及び施行日
令和7年度群馬県食品衛生監視指導計画
施行日:令和7年4月1日
意見の提出数
合計 3通
(ファクシミリ 1通、電子メール 2通)
(意見の延べ総数 13件)
提出された意見及び意見に対する考え方
| 番号 | 提出された意見の概要(要旨) | 意見に対する考え方 |
意見の採択により改正した箇所の有無 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 |
監視指導の実施体制に関する事項、食品衛生に係る人材の育成及び資質の向上対策に関する事項 |
今年度も様々な食の安全確保の取り組みが計画されています。 コロナウイルス感染症への対応は収束したものの、食中毒発生が続いていることや、豚熱や鶏インフルエンザ発生時の対応などによる自治体職員の負荷が危惧されます。食品の安全確保の役割を果たすためにも、担当する部署の体制や人材の確保、予算の確保を要望します。 |
食の安全確保に係る取組を計画に沿って実行できるように体制確保に努めて参ります。 | 無 |
| 2 | 食品関係営業施設等への監視指導に関する事項 | ノロウイルスは、令和5年度3件・令和6年度4件と毎年発生しており、食中毒発生件数の約半数を占めていますが、ノロウイルス対策部分の記述は変わっていません。対策の有効性を評価し、見直しの検討を要望します。 | ノロウイルス食中毒は、従来どおり調理従事者の健康管理、手洗いの徹底が予防に重要と考えておりますが、引き続きノロウイルス食中毒対策の情報収集にも努めて参ります。 | 無 |
| 3 | たびたび食中毒のニュースが流れるたびに、店が営業停止3日間とかで済ませていたり、また、同じ店が報道されたりすることもあるようだが、もっと厳しくしないとなかなか再発が防げないのではないかと思うときがあります。店を守る事も大切なので、その辺の兼ね合いももっと検討する必要があると思います。 監視目標件数Aランクをもっと増やすべき(行政処分を受けない施設も危ない施設があります) |
食中毒を発生させた施設については、監視指導計画における監視目標件数のAランクに位置づけ、通常より監視頻度を高めております。Aランク施設の選定については、より効果的な監視指導が可能となるように他の自治体の取組も参考に研究していきます。 | 無 | |
| 4 | 食品ロスを考え持ち帰りを実施しても大丈夫と思われる場面でも、持ち帰り駄目といわれることが時々ある。規準が難しいと思われるが、はっきり規準ができているのか、店の判断なのか、規準ができていないのならつくるべき。 | 消費者庁及び厚生労働省が「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン ~SDGs目標達成に向けて~」を作成し、飲食店における食品の持ち帰りについて考え方が示されました。同ガイドラインを踏まえ、事業者等に適切に助言を行って参ります。 |
無 | |
| 5 | 食品等の検査に関する事項 | 微生物検査数は増えていますが、その他の検査は年々減少し合計で814件→735件→716件となっています。特に食物アレルギーは人命にも関わる事項です。計画の目的にも記述されている“食品衛生を確保し健康の保護を図るため”現行の水準が後退しないよう検査を実施していくことを要望します。 | 食品等の検査については、本県及び全国での健康被害や違反の発生状況を踏まえ、効果的な検査が実施できるよう努めて参ります。 | 無 |
| 6 | 食品におけるPFASの濃度についても積極的に測定を実施することを求めます。各浄水場では、原水、浄水の定期的な水質検査を行い、PFASの濃度について調査していると思いますが、食品についてのPFAS濃度の測定はされていないと思います。 | 食品中の有機フッ素化合物(PFAS)については、食品の基準値設定など国の動向を注視し、適切に対応して参ります。 | 無 | |
| 7 | 残留農薬に係る食品衛生確保も大切な事で、無農薬を徹底すべき。やればできるはず。 | 御意見として承りました。 | 無 | |
| 8 | 違反事実確認時の対応に関する事項 | いわゆる「健康食品」による健康被害発生時の対応について、インターネットや通販でも「健康食品」や「機能性表示食品」等は多く扱われており、購入した消費者はこれらの食品を継続して摂取することが想定されます。積極的に情報提供を行い、学習、意見交換の場を増やすことを要望します。 また、万一異変があったときの対応等の周知をお願いします。 |
様々な機会を捉えて、いわゆる「健康食品」に関する正しい情報をより多くの消費者が得られるように取り組んで参ります。 | 無 |
| 9 | 情報提供及びリスクコミュニケーションに関する事項 | 第9-2県民及び食品等事業者とのリスクコミュニケーションにおいて、昨年 まで計画にあった「群馬県食品安全県民会議の開催」「消費者団体等とのリスクコミュニケーション」「消費者と食に関わる様々な事業者との相互交流の促進」が削除されています。「群馬県食品安全県民会議の開催」「消費者と食に関わる様々な事業者との相互交流の促進」の見直しは理解するところですが、第9-1監視指導計画のリスクコミュニケーションでは、「監視指導計画の策定にあたっては、消費者団体等との意見交換会、群馬県ホームページその他広報媒体等を通じて広く県民の意見を聴取し、計画に反映させる。」とありますので、第9-1との関連においても「消費者団体等とのリスクコミュニケーション」は残す必要があると考えます。 |
ご意見を踏まえて、「消費者団体等とのリスクコミュニケーション」について追記いたします。 | 有 |
| 10 | 第9-2県民及び食品等事業者とのリスクコミュニケーション(2)ぐんま食の安全・安心県民ネットワークとの協働事業の実施において、引き続き当ネットワークとの協働事業の実施が計画案に含まれていることに感謝いたします。県民が関心の高いリスクコミュニケーション事業を協力して進めていきます。 | 今後とも群馬県のリスクコミュニケーション事業の実施に御協力をお願いします。 | 無 | |
| 11 | 第9-2県民及び食品等事業者とのリスクコミュニケーション(3)「施策の申出制度」の活用で県民意見の反映を図る。令和7年度も引き続き計画されていますが、令和6年に申し出制度を活用した意見は何件あったのでしょうか。また、どんな意見があったのでしょうか。差し支えなければ教えてください。 | 施策の申出制度を活用した意見の申し出は、ございませんでした。 | 無 | |
| 12 | SDGs目標達成に向けて食べ残しによる持ち帰り促進ガイドラインが制定されましたが、飲食事業者はもちろん、消費者に向けても「食べ残しによる持ち帰り」の注意事項について注意喚起を行うことを計画化してください。 | 引き続き、SNS等で「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」の消費者に対する啓発について、取り組んで参ります。 | 無 | |
| 13 | その他 | 消費者が見学し、食品の安全について学べるような県内の施設がありましたら、施設情報の提供をお願いします。 | お問い合わせいただけましたら、個別にご相談させていただきたいと思います。 | 無 |
意見の採択により改正した箇所の有・無
有(別紙のとおり)
別紙_令和7年度群馬県食品衛生監視指導計画原案に対する意見の概要、意見に対する考え方及び修正した箇所 (PDF:166KB)