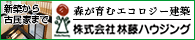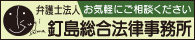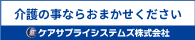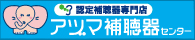ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
平成26年度第2回群馬県産業教育審議会概要
更新日:2014年10月2日
印刷ページ表示
1 日時
平成26年9月12日(金曜日)13時30分から16時00分
2 場所
群馬県立渋川工業高等学校
3 出席委員
5名(原委員(会長)、遠藤委員、今井委員、松村委員、太田委員)
※欠席委員 7名(宝田委員、鈴木誠委員、茂木委員、鈴木宏子委員、朝岡委員、木村委員、松本委員)
4 次第
- 開会
- 群馬県産業教育審議会長あいさつ
- 群馬県教育委員会教育長あいさつ
- 学校概要説明(群馬県立渋川工業高等学校長)
- 活動発表「特色ある教育活動」
「自動車科の生徒活動報告」 - 授業・施設・設備等視察
「自動車実習」、「課題研究」、「実習」 - 審議
「社会の変化に対応した産業教育の在り方について」
~次代を担う職業人材をどのように育成するか~ - 閉会
議事概要
会長
- 本日、見学していただいての質問や感想、地域の産業から必要とされる人材の育成について意見をいただきたい。
A委員
- 生徒一人一人が一生懸命取り組んでいる。
- 自動車科や自動車研究部が特徴的だと感じた。特にエコカーが参考になった。
- エコカーを作製していて、高度な加工技術や忍耐力が身に付くと発表があった。指導者は教員なのか、それとも外部の指導者なのか。
- また、インターンシップに対する取組がしっかりしていると感じた。短期・長期の受入企業の開拓は、どのようになっているのか。
校長
- エコカーの指導は、教員が担当している。それにより技術力が向上し、エコカーについての愛着も湧く。
- インターンシップの受入企業の開拓は苦労している。自動車科については、自動車整備協会が後援をしている。しかし、他の3科は、メーカーに依頼する必要や、指導を行う現場とのギャップがあり、受入先の確保が難しい。
B委員
- インターンシップの受入企業の開拓は、我々も行っている。先日、渋川地域の企業が高校生の受入れについて承諾してくれた。今後は、渋川地域の受入企業の開拓に力を入れていきたい。
- 発表を見学して、技術系の先生の熱心さを感じた。
C委員
- 初めて工業高校を見学した。最初は自動車に興味がある生徒が工業高校へ進学すると思っていた。
- 発表の中で、皆勤や精勤が多いとのことだが、それはなぜか。
校長
- 3年間で欠席が2桁になると就職に影響する。学校全体で、簡単に休まないように指導に取り組んでいる。
D委員
- 女子生徒が、しっかり挨拶ができていた。
- また、教室や廊下がきれいで、エレベータ、合宿所等もあり、設備面で充実している。
- 定時制の生徒は、昼間働き、夜勉強することで、頑張っている様子が伝わってきた。
- 生徒に一人一台のパソコンが用意され、インターネットが利用できる環境であるが、費用についてはどうしているのか。
校長
- 設備面については、県からの予算で行っている。また、生徒が活動する上で、一部生徒会費やPTA会費等を利用している。
会長
- インターンシップを受け入れた経験について伺いたい。
A委員
- 高校生を受け入れたことがあるが、流れ作業ではないので危険が伴う部分が多く、本質的な業務に関わらせることができない。
会長
- 受け入れる側と受ける側双方のマッチングが重要である。
B委員
- インターンシップは、企業として、大学生を25年間受け入れてきた。学校の都合等の要因はあるが、一週間程度の実施ではお客様になってしまう。
- 期間については、学校はどのように考えているか。
校長
- 県教委は、6日間以上をトライワークということで推進している。
- 学校としても夏休み期間中は、一週間程度実施した方が良い経験ができると思う。現実は、一週間を超えて受け入れていただける企業がない状況である。3日間が限度である。
- 本校では、この現状を踏まえて来年度から短期インターンシップを実施し、その中で希望する生徒を長期で実施していく予定である。
C委員
- 農家では、この7月~9月の間に30人程度を受け入れた。具体的には、中学生は短期で4名、高校生は21日間、大学生では長い人で28日間のインターンシップを行っている。
- 農業はあまり危険ではないので、今回の皆さんのお話を伺って、職種によって状況が大きく違うことを改めて感じた。
- 数日前に山岸製作所に伺ったが、高度な機械化が進んでおり誰でも作業できる。また、人が必要ない様子がうかがえ、今後の職業の様相が変化していく気配を感じた。
- インターンシップは、受け入れられる職種と受け入れられない職種がはっきりしていると思った。
会長
- 農業は、ものづくりの最たるものであり、力を入れていかなければならないところである。更に高収入を上げる方法があるのではないかと思った。
- 校長先生より技術力と人間力の両方を磨いていくとの話をいただいた。
- 特に挨拶、清掃、身だしなみ及び時間を守れる生徒の育成は大賛成である。
- 我が社も毎日、挨拶について耳にたこができるくらい伝えている。
- 挨拶は、形ではなく相手に気持ちが伝わることが大切である。
- 本校でも技術力に加え気持ちが伝わる挨拶ができる生徒を育成していただきたい。
- 教育長からもあったが、先日富岡製糸場を訪れその賑やかさ等を見ていると、群馬が更に一段二段と飛躍するチャンスがあると改めて感じた。
- 群馬のものづくりにも勢いを付ける方向付けができると思っている。
- 群馬はものづくり県としての認識が高い。
- 先日、知事とも群馬をもっとアピールしていくことで意見を同じくしたが、この世界遺産の効果が更に波及していくことを期待し、それぞれの立場で頑張っていていただけたらと思う。
- ものづくり群馬のリーダー校として、今後も一段と頑張っていただき、いろいろな人材を輩出していただけるようお願い申し上げる。