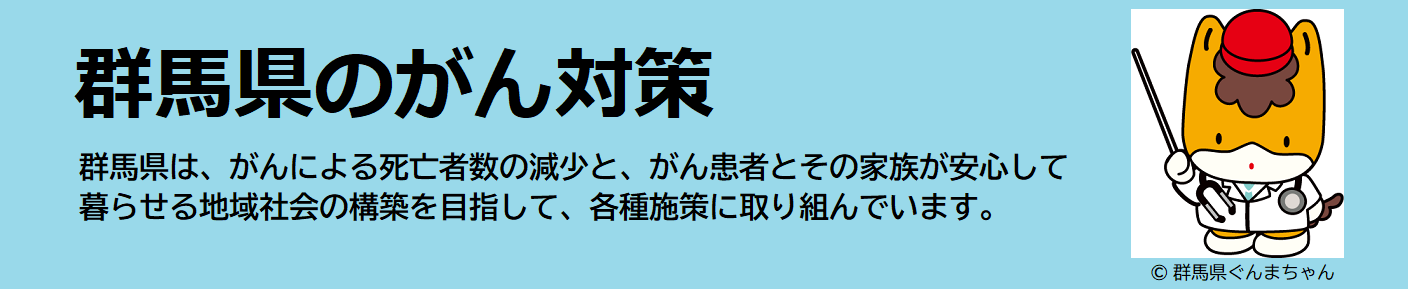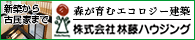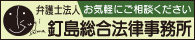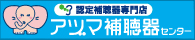ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
在宅で看取った家族の方々の体験談
更新日:2022年11月7日
印刷ページ表示
- 一日が長い日もありましたが、そこには、当たり前の日常生活があったという事です。夫はベッドの上に寝たままの状態でしたが、朝、目がさめれば、庭の小鳥の鳴き声、可愛がっていた犬の鳴き声がありました。そして子供達は「パパ行ってきます」と、夫に言い、夫は「気をつけてね」と、いつもの夫の子供達への気遣いの言葉が家の中で交わされました。
夫の人生の一番大事な時期を、住み慣れた我が家で共に過ごせた事は、何よりも夫の望む事でした。(御主人を看取ったAさん) - 病院には来られなかった孫たちが顔を見せるたび、母は本当に嬉しそうでした。家族がつきそうにしても余計な気を使う必要はないし、普通の家のことをしながら看られるので、病院に通って看病するより身体も楽だったと思います。
周りの人たちの助けがあって、家で看取ることができました。達成感がありました。(お母様を看取ったBさん) - 母は、最期まで在宅で過ごす事を希望し、家族全員も賛成しました。「少しでも母と一緒にいたい」という思いが、家族みんなにありました。しかし一方で、色々な葛藤があり、自問自答しながら母と接していたのも事実です。迷いがある中、私たちを救ってくれたのは、死を目前に前向きに生きる母の姿勢と、母を支え続けて下さった方々でした。心から感謝しています。皆様のお力を借りたお陰で、母も私達家族も大きな壁を乗り越えてこられたと思います。(お母様を看取ったCさん)
- 妻は生前、草木、木々の四季の変化を楽しみ、また夕日にしばしば感動するという生活を送っていました。外出がままならぬ闘病中は、部屋の障子、カーテンをいっぱいに開け、庭の木々の効用と夕陽をベッドの上から眺め、二人で唱歌を歌い気を紛らわせていました。
不思議にもそのとき、私は涙が出ませんでした。これで妻は、告知以来の闘病の辛さ、苦しみから楽になれたと思うと共に、多くの方々の支援を受けながら、妻の希望どおり最期まで家で看てやれたとの安堵の気持ちに包まれていました。(奥様を看取ったDさん) - そんなある日、親戚の人がお見舞いに来て「こんな重病人を入院もさせないで、可哀相だ」と強く言われ私も悩んだ。妻は家に居たいというが、周りから見ればその通りだ。思いあぐねた末、妻の兄と一緒に医師に相談に伺った。「本人を寂しくさせないようにと望んでいるのであれば、今のままが一番よいのではないですか」と言っていただき在宅介護を決断した。
病気を治してやれなかったことは今でも悔やまれる。しかし家にいたいという望みをかなえてやれたこと、そして入院患者としてではなく最後まで人格をもった主婦として皆さんと接することが出来、心安らかに逝けたことが私にも救いである。(奥様を看取ったEさん) - この頃一日中うとうとと眠っていることの多くなった夫でしたが、夜目を覚ますと思い出話などいつまでも話したりしました。家だからこそ与えられた夫婦だけの時間。数々の夫の言葉、いつまでも忘れません。(御主人を看取ったFさん)
- 10月になってから家で腹水を抜いていただくようになり楽になりました。「癌の末期に笑って過ごせるとは思っていなかった」と言っていました。中旬以降だんだん体力が落ちてきました。が、子供達に支えられて、いつものように庭で日光浴をしながらタバコを吸ったり、お風呂にも入りました。
8カ月間、親子で病と真っ正面から向き合い、主人のイライラやわがままは病気からきていると、すべて受け入れる事ができ、強い絆ができました。(御主人を看取ったGさん) - 夫は、父を家で看取ることによって「人が死ぬ時を見届けられ、死を考えられる機会を与えられた。子供達と看取ったことで家族愛も感じたし、死を目前にして、プロセスを通して感動(表現が変かもしれませんが)さえ覚えた。最後まで悔いなく看病できたので、自分の満足感も得られた」と話していました。(お父様を看取ったHさん)
- 「俺の死に様をよくみておいてくれ」と、ホスピスケア研究会の活動を共にした友人2、3人に電話で連絡、話し相手をしてもらうことはしばしばあったが、必要以上に他人に頼ることはなかった。もう一人の友人と偶然同じ日、彼は旅だった。潔い、見事と言えばそれは見事な最期をみせてくれた。独居でも、がんでも在宅の最期を迎えられるという事を私たちに実証して見せた。これからの高齢化、核家族化する団塊の世代の私たちへ力強くも少し哀しいメッセージを遺してくれた。ハンチング帽を冠り、パイプを咥え自宅前にたたずむダンディーだった彼の姿が今も瞼の奥に残る。(御友人を看取ったIさん)
(群馬ホスピスケア研究会会報「ねがい」より、許可を得て抜粋掲載)
(更新日:平成26年1月15日)