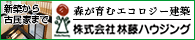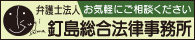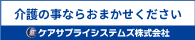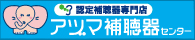本文
上野国分寺跡(こうずけこくぶんじあと)・上野国分尼寺跡(こうずけこくぶんにじあと)
更新日:2025年2月18日
印刷ページ表示
(上野国分寺跡 1926年(大正15年)国指定史跡)
(上野国分尼寺跡 2024年(令和6年)国指定史跡)
1 所在地
高崎市東国分町・引間町~前橋市元総社町
2 性格
741年(天平13年)に聖武天皇が発願し、全国68ヶ国で建立された官立寺院のうちのひとつです。造営は国司の監督のもと、地元豪族が協力して実施されました。
3 年代
国分寺は聖武天皇発願から間もなく造営着手と推定され、国分尼寺の着手時期もそれほど隔たった時期ではないと考えられます。文献史料によると、11世紀前葉には国分寺の金堂・塔などは残存していたようです。
4 内容・特色
(1)上野国分寺(僧寺)・上野国分尼寺の立地
- 上野国分寺(僧寺)と上野国分尼寺は、律令制下の群馬郡に所在し、現在においても群馬県のほぼ中央部にあります。
- 上野国分寺(僧寺)と上野国分尼寺は、約300メートルの間隔をおいて、東(尼寺)西(僧寺)に並び立つように計画されました。
(2)上野国分寺(上野国分僧寺)
- 1980年(昭和55年)から9年間の調査を経た上での2012年(平成24年)以降の発掘調査により、南大門跡・塔跡・金堂跡・講堂跡など伽藍の概要が、ほぼ判明しました。なお、寺域は、東西約220メートル・南北約235メートルです。
- 七重塔跡の規摸は、基壇の規模が1辺64尺(19.2メートル)で、高さは60.5メートルと推定されており、全国の国分寺の中で最大規模です。
(3)上野国分尼寺
- 2016年(平成28年)からの発掘調査により、金堂跡・尼坊跡・回廊跡などの伽藍の概要が判明しました。なお、寺域は、約160メートル四方です。
- 尼が日常的な生活を送る尼坊跡は東西約45メートル・南北約11メートルで、調査で内容が判明している尼坊跡としては国内でも最大級です。


史跡上野国分寺跡 航空写真 史跡上野国分尼寺跡 航空写真


史跡上野国分寺跡 七重塔跡 史跡上野国分尼寺跡 礎石列


史跡上野国分寺跡 七重塔復元模型 史跡上野国分尼寺跡 軒丸瓦
(史跡上野国分寺跡ガイダンス施設展示) (国分尼寺の画像は高崎市教育委員会提供)