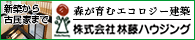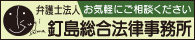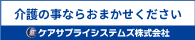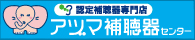本文
第12回ぐんま子ども・若者未来県民会議結果の概要
更新日:2025年4月3日
印刷ページ表示
1. 日時
2025(令和7)年3月21日(金曜日)14時00分~15時30分
2. 場所
群馬県庁第1特別会議室
3. 出席者数
委員12名
事務局(生活こども課)8名、関係部局 13名 計21名
4. あいさつ
(生活こども部長)
- 当会議では、新こども計画「ぐんまこどもビジョン2025」の完成を目指して皆様のご意見を聞きながら作業を進めてきた。
- 前回の会議では素案をお示ししたところだが、パブリックコメントを12月から1月にかけて実施したところ、47件ものご意見をいただいた。こどもの意見を聴くという取組を進めてきたなかで、こどもからも意見をいただくことができた。ご意見を踏まえて修正した計画案が先の県議会で承認されたため、本日は完成版として皆様にお届けする。
- 同時に県議会で承認を得た来年度予算は「こどもまんなか推進&新産業創出加速予算」と題し、同時に「こどもまんなか推進プログラム」という群馬モデルとなる施策パッケージをまとめている。こどもの育ちをライフステージを通じて切れ目なく支援していくという考えを盛り込んでいるものになっており、ぜひご覧いただきたい。
- 皆様からは、この「ビジョン」や「プログラム」、新年度予算が実効性のある取組として進められるよう、ご意見をいただきたい。
5.議題
(1)ぐんまこどもビジョン2025完成版について
※資料に基づき、事務局説明
(会長)
- 前回の会議で、特に働き方改革の観点からも産業界に意見を求めるべき、との発言があったかと思うが、その後具体的に意見をいただいたところはあるか。
- また、部活の地域移行に関する指標の算出根拠が実態を反映したものになっていないという意見もあったが、その後の検討状況はどうか。
(事務局)
- 産業界に絞った意見ということではないが、前回会議後にパブリックコメント等で各関係団体に計画の内容を周知し、ご意見を募集した。
- 部活の地域移行の指標については、前回は地域移行・地域連携に取り組んでいる学校が市町村内に1校でもあればカウントし、全35市町村のパーセンテージを算出していたが、ご意見を踏まえ、地域移行・地域連携それぞれに取り組んでいる市町村数を数字でお示しするように修正した。
(委員)
- こどもビジョン2025のやさしい版はこどもにもわかりやすい内容となっており良いと思う。
- 「5つの大切なこと」のうち、「こどもを育てる大人も応援する」ということも大事であり、このようなことを示していくことが非常に重要。
(委員)
- 資料の中の「こども意見の反映状況」などを見ると、こどもの切実な意見や悩み、家庭状況などをつぶさに聞き取っており嬉しく感じる。
- 4月以降計画を実施するにあたり、意見聴取の結果を受けてどのように改善されていったのか、さらにフィードバックいただけるとありがたい。
(委員)
- こどもの意見聴取については、当事者に意見を聴くという点で非常に良い取組と感じた。
- 「こども意見聴取フィードバック資料」についても、こどもの目に触れる機会や、配布したりする予定はあるか。
(事務局)
- こどもたちが意見を出したことに充実感を感じてもらえるよう、意見をくれたこどもたちに直接返すほか、県ホームページに掲載し、県教育委員会にも協力を依頼して学校を通じて周知できるようにしたいと考えている。
(会長)
- 今後の意見聴取は、どのようなスパン・イメージで実施する予定か。
(事務局)
- 来年度事業でもこどもの意見を聴く取組は継続して実施していく予定。
- こども基本法の中でも、こども施策の策定・実施のほか評価にあたってもこどもの意見を反映する旨が規定されているため、今後の取組内容は検討していきたい。
(委員)
- 小児医療についても具体的に書かれており、この通りこども達が健康を保てるとよい。
(2)令和7年度当初予算・群馬県こどもまんなか推進プログラムについて
※資料に基づき、事務局説明
(委員)
- 切れ目のない産後支援を行う中で、母子保健は市町村事業となるため、市町村によって対応に格差が出てくると思う。
- 計画の実行にあたっては、市町村の体力を勘案し、小さい市町村については支援をいただきながら進めていただきたい。
(委員)
- 市としても、県の支援を受けながら、しっかりこどもたちを育成し、保護者を支えられるようにしたい。
- 特にマススクリーニング検査や保育の充実についてはありがたいと思っている。
(委員)
- 先ほどの委員の指摘のとおり、小さい町村は財政的に厳しい面もあるため、県の支援をいただきながら全県で同様の事業ができるよう協力をいただきたい。
(会長)
- 県においては、今後どのように市町村と連携・調整を図っていく予定か。
(事務局)
- 昨年8月と、県予算案発表後の2月に市町村への情報共有を目的としたウェブ会議を開催したところ。
- また、先進的な取組をしている市町村の情報を照会し、それを他の市町村に還元・共有することで県全体で取組が進むよう調整したいと考えている。
(委員)
- 養育費等確保支援事業について、町村部は申請できるが大きな市では申請できないという話を聞いたがどうか。
- 補助を受けられない、ということではなく、窓口が県か市かということか。
(生活こども部長)
- 事業の中には、国が県に財源を渡して県内一律に行うもののほか、先ほどお話のあった母子保健など、市町村が事業主体となり、県はバックアップを行うものなどがある。
- 委員からお話のあった養育費等確保支援事業については、各市が独自に行い、県は町村部を補助する形をとっている。
- 事業の目的や位置付けによって異なり、財源の問題もあるが、例えば来年度事業の「朝の居場所づくり」など、県として県内全体のレベルアップを図るべきと考えるものについては、一歩踏み出してやっていくという形で予算の中に盛り込んでいる。
(関係課)
- 養育費等確保支援事業について補足すると、県で町村部在住者に対して補助をしているほか、市はそれぞれの市の判断で取り組んでいるところ。
- 県事業の場合は、(一財)群馬県母子寡婦福祉協議会が窓口となり、町村部にお住まいの方について相談支援をしていただいている。
(会長)
- かつては高齢者や障害者福祉を含めて全国の市町村で一律の施策が行われてきたが、限られる財源の中で、例えば給食費無料化、保育料完全無償化など、それぞれの市町村が状況に応じて独自に取り組んでいる状況。
- ただし、全体で進めたい部分は県がしっかり対応いただくものと考えている。
(委員)
- プログラム等でこどもに色々な経験をさせても、群馬を出てしまって戻ってこない若者が多いと感じている。Uターンをしないことには人口やこどもも増えないため、こどもたちに群馬っていいなと思ってもらえることが重要。若者にとっては賃金も低いという印象がある。
- また、自分の職場でも産休育休を終えて復職する職員のうち、土曜日保育がなくなって働きにくいとおっしゃる方がいた。安心して仕事をするという意味で、保育士不足も大きな問題だと感じている。
(関係課)
- 保育士の確保という点では、昨年保育士就職支援センターを社会福祉協議会の中に設立し、保育士の求人・求職の相談なども増えている状況。
- 潜在保育士の就職支援のため、カフェ方式の相談支援やインターンシップの実施を行っているほか、新卒保育士の確保については、養成校の訪問等にも力を入れている。中高生については、バスツアーなどで魅力の発信に取り組んでいる。
- 土曜日保育については、その園の事情は個別にあるかもしれないが、個別に教えていただければ確認したい。
(会長)
- 今回県では4:1の保育士配置を行う保育所のうち、非認知能力の育成やインクルーシブ保育等に取り組む保育所に補助を行うとのことだが、今の保育士不足の中でどのくらいのイメージで可能なのか。
- また、非認知能力の育成やインクルーシブ保育とは、何をもって補助対象となるのか。
(関係課)
- 全てを確認しているわけではないが、様々な資料から、現状では6割ほどが4:1配置を行っていると推定している。来年度からは国が5:1の加算を行うため、保育所にはその加算をしっかりと確保していただいた上で、県のほうで4:1の補助を上乗せしていく。
- 非認知能力の育成とインクルーシブ保育については、1歳児クラスに限らず園全体の取組を推進するという形で行う。あまり難しい形で実績を上げていただくのではなく、非認知能力については日頃の遊び活動や自己肯定感を向上させるといった園の目標、インクルーシブ保育についてはすでに外国人や医療的ケア児の受け入れ、それに関する研修会などにも個別に取り組んでいる園もあると思うので、現状やっていることを報告していただき、それを県全体で普及させる形で進めていきたい。
(会長)
- 若者のUターンについて、先日、移住希望地ランキングで群馬県が全国1位になったと聞いているが、こういった取組を前面に出していくことが必要だと思うがどうか。
(生活こども部長)
- 来年度当初予算案の中で、「ぐんま賃上げプロジェクト」として賃上げに取り組んでいただいた中小企業向けに支援をする予定。
- 若者世代に対しては、移住を促進するために、群馬の保育所を体験してもらって群馬の良さを知ってもらうような取組を、予算やこどもまんなか推進プログラムの中に組み入れている。
(会長)
- 先ほど委員からお話のあった賃金も非常に大事なファクターかと思うので、よく検討いただきたい。
(委員)
- こどもビジョン2025のやさしい版について、保護者や子育てに関わる方、出産したばかりの方などには、5つの大切なことといった理念が十分に理解されていないと感じたため、そのあたりの年齢層の方にも周知を検討いただきたい。
- 町村と県との違いというところでは、山間部に住んでいる人にとっては手の届かないものが多いと感じているので、市町村でこのようなことをやっていただけたらという市民目線の意見を聴取するような場を作っていただけるとありがたい。
(会長)
- 市町村間の格差については、小さい自治体では逆に無料化の取組が進んでいるという実態もある。
(委員)
- 無料化などの支援が充実した町村部を見ると、同じような取組を都市部でやったら立ち行かないのでは、というのが率直な感想。
- ただ全ての市町村がこういった充実した取組ができているというわけではないので、できない市町村に対しては、県と歩調を合わせながら、県内の市町村が同じような水準の事業ができるようにサポートしていただきたい。
(委員)
- 住みやすさによって特定の地域に若い世代が偏在している実態があるため、各市町村でまんべんなく支援が行き届けばよい。
- また、昔に比べて営業センターの規模縮小化等に伴い、職場自体が特定の市町村に集中してしまっているので、それに伴い所帯を持っていない若者などは特に偏在してしまっている。
(委員)
- 地域でこどもを育てる取組をする中で、働いているから忙しいとボランティアなどの担い手を引き受けない若い世代が増えており、活動が立ちゆかなくなってきている。親に教育が足りないのではと感じている。
- もう1点は、国によっては日本語を勉強せずに日本に働きに来る外国人がいること。外国籍のこどもが増加する中、学校でも1対1の指導はとてもできなくなっている。日本語ができないと仕事も低いレベルのものしかできない傾向にあるため、市町村に県からも働きかけてもらいたい。
(会長)
- ボランティアの高齢化は課題だが、一方で高齢者の8割以上が元気だということもあり、ぜひ元気な高齢者が地域を支えられるとよい。先ほどの部活の地域移行についても、高齢者でもしっかりと指導できる方はたくさんいる。
- 外国にルーツを持つこどもについては、しっかりと日本語を学んでから日本に来ている方ばかりではない中、どのように支援していくのかは重要な課題である。
(委員)
- 地域の取組について、そもそも地域に馴染んでいないなど、参加しない・したくない保護者は増えている現状であると感じている。
- 自治会を中心とするこども会はうまくいく傾向にあるが、学校単位・複数学校単位と規模が大きくなると意思統一が図れない、など構造的な問題もありながら、親も仕事が忙しくてできなくなっている背景もあるかと思うので、温かく見守っていただきつつ、そういう親たちを地域で取り込むような活動をしていくことは大事だと思っている。
(会長)
- 自治体や行政が主導すると持続可能にならず、ボランティアの方に自主的に考え、行動していただくことが大事な部分もあると思っている。また、女性だけでなく男性にも積極的に地域活動に関わっていただくことも重要。
(委員)
- 高齢者も、70歳を過ぎても働いている方も増えてきているので、地域のつながりよりも、個のお付き合いの方が増えてきてしまっている印象。
- やはり時間と気持ちに余裕のある年齢の方というと75歳を過ぎている方が多い。活動を絶やさないようにバックアップをいただきたいと思うと同時に、関わっている我々も、小学校を通じてなど工夫しながら周知や声かけをし、楽しく活動できて地域が元気になれるような役を担えたらいいなと思っている。
(委員)
- こどもまんなか推進プログラムの「複合的な社会課題に対してこども施策起点のアプローチ」という点は地域のあり方に非常に関係していると思っている。
- 妊娠中に色んな課題を抱えているお母さん、先天性代謝異常を抱えた赤ちゃん、重篤な障害を持っているお子さんを地域でどのようにケアするかということは、保育の充実に関連するし、インクルーシブ保育はインクルーシブ教育につながっていく。まさに複合的な社会課題に対してのこども施策起点のアプローチになっていると感じた。
(会長)
- おっしゃる通り、妊娠から誕生・幼児期、そして小1の壁を乗り越えて小学校・中学校・高校という展開がまさに一体的に進められるのかという期待がある。
- その中で妊産婦支援の充実、産前産後ケアの充実はこれまでも大きな課題であったが、産婦人科も偏在が進み、地域によっては出産もできなくなる中で委員の見解を伺いたい。
(委員)
- 群馬県の小児医療は、高校生まで医療費無料や先天性代謝異常検査助成など、非常に充実していると思っている。小児医療センターの移転も決まったが、そのことによって北毛の医療がどうなるか、病院の連携ということも今後は課題になってくる。
- また、温泉地域で開業している医師が保育園の健診に行くと、半分は外国人のこどもたちであり、予防接種の説明にも難儀するような状態で、今後大きな課題になると思っている。
- 障害のある方については、医療的ケア児等支援センターの開設に伴い、少しずつ充実するものと考えている。発達障害のスクリーニングとなる5歳児健診についても、全県的に進めて行く必要がある。
(委員)
- 妊娠から切れ目のない支援をということで、群馬県でも妊娠出産連絡票を活用し、医療機関と行政で連携が取りやすい状況になっているが、今回の制度改正で流産・死産も対象となることから、相談件数の増加が予想される。十分に対応ができない小さい市町村への補完をどのように行っていくかということが課題。
- 産後ケアは非常に充実しているが、総合病院等で産む方が多い中で、助産師が色々な市町村の妊婦ごとに、このサービスは使える・使えないと指導するのが大変だということと、できればどの妊婦に対しても同じように支援してあげたいと現場では感じている。
(会長)
- 市町村ごとに差があるのは仕方がない部分かもしれないが、全体として底上げしていくことが群馬県の魅力につながっていくと思う。Uターンの関係でも、働く場所や教育・医療はアンケート結果でも重要なファクターだと思うので、ふるさと回帰センターなどでの窓口でもしっかりとPRしていくことが大事。
(委員)
- こどもまんなか推進プログラム搭載事業のうち「アート教育」が気になった。予算額としては割とコンパクトな印象もあるが、市民1人1人が手を差し伸べにくいところであり、国や県が本気にならないとなかなか取り組めないところである。近隣では、栃木県・宇都宮市の美術館などは全国から人を集められるような質の高い展示会を開くなど、非常に盛んな取組を行っている。非認知能力を高める上でも、それなりの予算をかけて一気に進めることも必要なのではないかと感じた。
- また、非認知能力について、今後こどもたちが生きていく社会においては生成AIの活用は外せない。併せて検討を深めていくことが必要と思う。
(会長)
- 限りある時間の中で貴重なご意見をいただきありがとう。
- 事務局においても、本日の意見を踏まえ、計画の推進・来年度予算の執行を適切に進めるようお願いする。