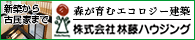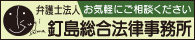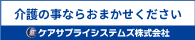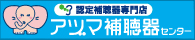本文
第11回ぐんま子ども・若者未来県民会議結果の概要
更新日:2025年3月12日
印刷ページ表示
1. 日時
2024(令和6)年11月15日(金曜日)13時15分~14時45分
2. 場所
昭和庁舎3階 35会議室
3. 出席者数
委員13名
事務局(生活こども課)9名、関係部局 19名 計28名
4. あいさつ
(生活こども部長)
- 前回会議では、現行計画「ぐんま子ども・若者未来ビジョン2020」における実績の評価を行っていただくとともに、来年4月からの新たな計画である「ぐんまこどもビジョン2025」の骨子案について審議いただいた。
- 本日は、いただいた御意見を踏まえ、骨子案の具体的内容の検討を進めた結果を計画の「素案」としてお示しする。
- この素案では、目指す社会の姿として「こどもたち一人ひとりが大切にされ、全ての人がこどもの育ちを支える社会」としているが、この点を含め、委員それぞれのお立場から、忌憚のない御意見をいただきたい。
5.議題
(1)「ぐんまこどもビジョン2025(仮)」の素案について
※資料に基づき、事務局説明
(委員)
- 群馬県青少年健全育成審議会からの主な委員意見を報告する。
- 資料5・6ページ「計画策定の趣旨」について、パブリックコメントでは、ホームページに載せるだけでなく、声掛けをして各団体から意見を出してもらえるようにして進めてほしい。
- 8ページ「目指す社会の姿・基本理念」については、こどもの権利が最優先と明記されたが、大人に喚起できるような文言を入れてほしい。
- 23ページの基本方針1では、「ウェルビーイング」を県としてどのように定義しているのかということと、教育振興基本計画でも重視されている「エイジェンシー」という言葉を前面に出してほしい。
- 54ページの「自殺や犯罪からこども・若者を守る」では、犯罪被害防止に闇バイトについて触れ、こどもの命や安全を災害や事故からいかに守るかの視点も入れてほしい。
- 58・64ページの「基本方針2」について、離職率の高い保育士の処遇改善のためには直接支援が必要ではないか。保育士養成機関がなくなっていくので、直接支援が必要。
- 66・68ページの教育に関するところでは、先生の環境整備は急務で、国の基準にプラスした配置がほしい。教師が授業に専念できる体制が必要。
- ページの「学びと地域の連携」について、学校と児童委員などの地域とのコミュニケーション、多忙な親に代わって、地域のシニア世代が活躍できる場が必要。
- 84ページ「高等教育に係る経済的負担の軽減」については、県立大学や私立専門学校について記述があるが、国立・私立大学についての記載がない。少子化のなか、県として地域の大学を支えるという意識で、もう少し書き込んでほしい。
- 計画全体に対しては、県民との意識の共有という点で、計画を広報する項目を加えてはどうか。動画はぜひ作ってほしい。こどもの気持ちを受け止める体制などについて記載があるとよい。カタカナ語が多いので注釈を入れて欲しい。困ったときの相談窓口が分かる記載がほしい。計画はよくできているが、予算化され実効性が出てくるかがポイント。
(会長)
- まずは、資料1の「新しい計画で目指す社会の姿と基本理念」についてご意見を伺ったのち、各論、基本方針等についてご意見を伺います。
(委員)
- ライフステージの分け方について、学童期と思春期を一緒にすることに違和感がある。義務教育と思春期ということで、今後はもう少し細分化してもよいのでは。
(事務局)
- 基本方針3にあたる「学童期・思春期」については、基本目標を設定する中でさらに5つに分け、丁寧に記述をして参りたい。
(委員)
- 思春期と青年期の基本方針を厚くする必要性がある。中学・高校時代を指すと思うが、受験期などをはさむと、青年期に必要な教育を施される機会が少ないと感じる。
- 高卒で就職する若者もいる中、キャリアプランについての教育を受ける機会が少なく、人材育成が充実している企業も稀である。このことから、特に基本方針4(1)2「高等教育段階で必要な教育の充実」を具体的に示し、厚く、期間をかけて取り組んでいく必要がある。
(会長)
- ご指摘のとおり、乳幼児期については福祉、母子保健等で手厚い支援がなされているが、青年期についてもしっかり検討していただきたい。
- 続いて、各論、基本方針1~5および、完成後のことについて触れていきたい。
(委員)
- 基本方針5「こどもを育てる大人への支援」が今後ますます必要になると感じる。
- 基本目標(1)「子育て当事者の不安や負担の解消」は基本方針2~4とも重なるが、こうしたことと、基本目標(2)「共働き・共育ての推進」を今後さらに厚くしていくことが必要。
(会長)
- 「こどもを育てる大人への支援」は、当事者だけでなく社会全体で支えていくという意味で重要。高齢者からも、世代を超えて連携して社会貢献したいとの話を聞いている。
(委員)
- 基本方針3の基本目標(1)「安心して過ごし学べる学校生活の充実」の数値目標「栄養教諭による地場産物を活用した食に関する指導の平均取組回数」の現状値10.6回というのは、1学校あたりのものなのか、それとも、群馬県全体の合計か。
- 同じく、「学校部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行に取り組んでいる市町村数」の現状値94.0%は非常に高い水準だが、算出根拠を教えてほしい。本当に喜んでいい数字なのか、受け止めが難しい。
(関係部局)
- 栄養教育指導回数については、各学校の栄養教諭において年間54時間を目安に取り組んでおり、回数に変換すると1学校あたり10.6回となる計算。
- 部活動の地域移行については、担当課からおって回答したい。
(会長)
- 地域移行については、市町村として何らかの対応をしている割合が94%なのではないかと推察する。
- 地域によって、移行ができるところと、中山間地などで専門性が維持できず難しいところがあると思うので、限られた環境・限られた人だけでなく、障害者・特別支援学校を含めて全ての児童生徒が対象となるようよく検討する必要がある。
(生活こども部長)
- 群馬県青少年健全育成審議会でも同様のご意見をいただいている。今いただいたご意見も原課に伝え、目標値が実情を表したものとなるよう検討したい。
(委員)
- 基本方針5「こどもの育ちを支える大人への支援」については、親権者以外の周りの人にも関係すると思う。
- 以前、ひとり親家庭のこどもの帰宅後に家庭に入って支援をしてもらえないかとの相談を受けたことがあったが、高齢者と異なり、大人がいないこどもだけの家庭に入ることはきちんとした資格等の後ろ盾なしには難しい。先ほどシニア世代からの支援といった話もあったが、そのあたりの体制を整えていただきたい。
(委員)
- 基本方針5「こどもの育ちを支える大人への支援」に関して、重要なのはやはり人手である。相談先はもちろん必要であるが、相談して「大変ですね、頑張ってください」で終わりでは意味がない。
- 縦割りではなく、各家庭のニーズを柔軟に取り入れて、経済的に負担なく支援が受けられるよう制度が整っていくとよい。
(委員)
- お話のあったとおり、自宅に入っていくことはデリケートな問題なため、個別にお話をききながらという形になる。市においては、ヤングケアラー支援などをはじめ少しずつ支援を拡充していく方針。
(委員)
- 看護、母子保健については、市町村単位で色々なサービスが行われているが、小規模な地域・団体のサービスの充実について、県に中心となって指導していただけるとありがたい。
(委員)
- 児童養護施設においても、入所する児童の養育だけでなく、地域支援も求められてきており、公的機関からの依頼を受けて訪問支援事業等を実施しているところ。非常にニーズは高いと感じている。
- 発達障害傾向のお子さんや、育てにくさを感じるお子さん、レスパイトを必要とするお母さんを、一時的にでも虐待予防のためにお預かりできるような団体が増えていかないといけない。
- もう一点、思春期・青年期の支援のところで、高校生になって居場所がなく、学校に行けなくなってしまう若者も多い。自分自身のキャリアデザインだけではなく、そもそもそういう考えに行き着かない若者への支援が必要。
(委員)
- 今議論しているような子育ての問題について、もっと企業側を巻き込む手段をとった方がよいと思う。
- 産業界としては、こういった子育ての問題に関してほとんど情報が来ていない印象。企業間でも温度差があるが、諦めずに情報提供していくことが必要。
(会長)
- 冒頭の群馬県青少年健全育成審議会からのご意見でも、団体からの意見聴取が指摘されていた。県においては、産業界を含めた意見を伺う機会をしっかり検討していただきたい。
(委員)
- 基本方針1の中で言及されている、非認知能力育成について、こうした能力がどのような効果をもつのかということまで書いた方がよいと感じた。例えば、将来色々な疾患になったり自殺する可能性が少なく、豊かに生活できるといったことなど。
- また、基本方針3の思春期の問題に関して、思春期のこどもはほとんど身体的には健康であり、よほどのことがない限り病院に受診することはないが、メンタルヘルスの状態をきちんと把握・評価し、場合によっては医療につなげることまで考えてほしいと思う。
(会長)
- 私からは1点質問させていただく。群馬県こどもまんなか推進本部を設置し、子育て圧倒的No.1を目指すとのことだが、こども計画の中でも、群馬ならではの事業をしっかりと進めていく必要があると思うがどうか。
- 本日委員からもご指摘があったが、計画の実効性を担保するには、予算の確保が重要である。
(事務局)
- ご指摘のとおり、「こどもまんなか推進プログラム」という群馬ならではの事業を、予算編成を通じて検討している。こうした新しい事業を、本こども計画を前に進めるための事業として推進していきたい。
(委員)
- 今後のスケジュールについて、パブリックコメントの実施方法が決まっていたら教えてほしい。また、計画に関して、市町村への意見照会の機会はあるか。
(事務局)
- パブリックコメントについては、通常版に加え、計画の概要をわかりやすく置き換えた「こども版」を作成し、こどもからも意見を募集する。
- 市町村への情報提供については、オンライン会議を通じて情報提供し、各市町村が計画を策定する際の参考としていただきたいと考えている。
(2)「群馬県社会的養育推進計画」の素案について【報告】
※資料に基づき、事務局説明
(会長)
- 主な数値目標のうち、里親等委託率のハードルが高いと思っている。群馬県ではピアサポート事業の取組が評価を受けているところだが、里親支援センターの設置についても検討していただきたい。
(委員)
- 社会的養護関係施設においても、国の施策に沿ってどのように施設が機能転換できるのか、考えていく必要があると思っている。里親委託率の目標値が示されたが、施設も施設の持っている機能を果たし、存続し続けるために、こどもの自立支援や、施設を出た後のアフターケアなど、何を施設の機能として専門性を出していけるかが課題。
(委員)
- アフターケアのところで、施設からも大学入学者が増えており、心のケアや情報収集に職員が苦労していると聞いている。職員のマンパワーも大事だと考えている。
(委員)
- 施設においてもこどもをずっと守ってきたという自負があって、その中で里親の推進をどう進めていくか、ご苦労の中で進めてきたと推察している。
- 施設に支えられながら、里親委託やファミリーホームをどのように展開していくかということが課題だと思う。
(会長)
- 高崎市に児童相談所が設置されるが、施設との関係はどう整理されるのか。また、設置時期はどうか。
(事務局)
- 高崎市が、来年の秋に新たに児童相談所を設置することを表明しており、高崎市に所在する児童養護施設や里親は、高崎市の所管になる。
- ただ、施設については、高崎市と群馬県で相互に利用していくという形で話し合いを進めているところ。
(3)その他
(委員)
- ぐんまこどもビジョン2025においてジェンダーギャップの解消や男女共同参画の推進が掲げられているが、群馬県においてはまだ男女別学があり、公立の学校において性別に基づいて分離教育をするのはインクルーシブ教育に反すると思っている。
- 県としてはどのように捉えて、どのように取り組んで行くのか見解を聞きたい。
(関係部局)
- 担当係におって御意見をつなぎたい。
(委員)
- こどもビジョン2025の基本方針1における「遊びや体験活動の推進」の指標案について、例えば県立美術館・博物館等の教育普及事業参加者数、昆虫の森入園者数等が示されているが、これをチェック項目にしていくと、県が目指す施策は入園者数を増やす、ということになりかねないか。
- 本質は、こどもにとってどのような体験活動が重要なのか、遊びとは何を指しているのかという点であり、これらの指摘がないことで、群馬県内の遊びや体験活動が低減していってしまう恐れがあると危惧している。
- もう一点考えていただきたいこととしては、なぜ親が子供と遊びや体験活動を一緒にできないのかということ。週末は疲れていて外へ行く気力がないことや、経済的な問題も考えられる。
- 例えばキャンプ施設をもっと無料で提供したり、アウトドア体験を自由にできるような施設を展開したりといったことも必要ではないかと思った。
- また、保護者によっては行政の活動に頼らず自分たちでイベントを企画してSNSで広めて集まる、といった動きもある。県がプラットフォームを作り、保護者がこうしたイベントをしたいというようなことを気軽に話し合えるような機会があると、自然体験活動につながるようなご意見が出てくるのではと思う。
(委員)
- 先ほど委員からお話のあった子育てにおける企業との関係性は非常に大事だと思っている。基本方針5(2)共働き・共育ての推進について、ぜひ県から企業への案内をお願いしたい。
- 保育園に預けているこどもが熱を出したときに、誰がこどもを見るのかということで夫婦で喧嘩になることもある。そういった時に企業においても突然休んでよいといった柔軟性が持てるとよい。そのあたりの支援策を検討していただきたい。