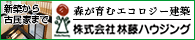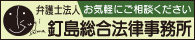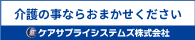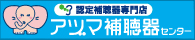本文
令和6年度第2回社会福祉審議会議事概要
1 開催日時
令和6年11月13日(水曜日)午後3時30分から午後5時
2 場所
県庁29階 第1特別会議室
3 出席者
(1)委員
江村恵子委員、大谷良成委員、片野彩香委員、川原武男委員長、杉田安啓委員、須藤英仁委員、田尻洋子委員、永田理香委員、星野久子委員、本間弘子委員(10名、五十音順)
(2)事務局
健康福祉部福祉局長ほか8名
4 議事
(1)「群馬県福祉プラン」の点検・評価について
「群馬県福祉プラン」(令和2年度~令和6年度)において数値目標を掲げる13の取組について、令和5年度の実績、それに対する自己評価及び今後の取組等を事務局から説明し、各委員による審議等を行った。
主な発言内容
●委員
指標の1つとなっている「介護職員数」の目標値40,843人については、何かベースとなる数字があるのか。また、現在、介護職員が非常に少ないと言われているが、現状は「B」(ほぼ達成)の評価でよいのか。
○事務局(地域福祉課)
目標値40,843人については、3年おきに改定している「群馬県高齢者福祉計画」において、厚労省の算定式に基づき需給推計として全国共通のものとして算出しているもの。なお、今年度から計画期間がスタートした第9期群馬県高齢者福祉計画では、「令和8年度に40,423人」に目標を下方修正しており、その点を踏まえ、総合的に勘案して「ほぼ達成」の評価とさせていただいた。
●委員
介護分野は有効求人倍率がものすごく高いと思うが、(介護職員が足りないという)現場の声が反映されているかという点について、県行政でも現場と同じ肌感覚を持っていただきたいと思う。
○事務局(地域福祉課)
現状で十分、ということではなく、今後も取組を継続することを前提に評価させていただいた。
●委員
他の指標もそうだが、達成率の考え方について、現行の算出方法は、現在値を目標値で除して算定しているため、計画策定時点で0%ではなく、いくらか達成率が出てしまっている。本来は、計画策定時の数値と目標値の差を算出し、その差を計画期間中にどれだけ達成できるか、を達成率として捉えるべきかと思うので、次期プランでは検討いただきたい。
○事務局(地域福祉課)
現状の進捗管理において、説明いただいた内容で算定していることは承知。次期計画の策定に当たり、どのような方法で達成率を算出するかについて、いただいた意見を参考にさせていただきたい。
●委員
前回の進捗評価の際、「通いの場」の取組について、コロナ禍前より実績が増えていることに関する質問に対し、回答が留保されていたかと思うがどうか。
○事務局(介護高齢課)
コロナ禍当初において、市町村の実施が中止・休止等された中、だいぶ利用者が減っていることは伺っている。それが復活してきており、コロナが5類へ移行したことを経て「通いの場」の利用者が非常に増えており、そういった機運もできてきているところ。
●委員
「人づくり」の特に12番の「マンパワーセンターの研修参加者数」について、生涯研修課程と福祉マネジメント力を高める研修に関わらせていただいた。生涯研修課程の方では、中堅の方向けを6回ほど、福祉マネジメント力に関しては人材育成担当者の研修をオンラインで担当させていただいた。
昨年度、県社協が実施した人材育成に関する実態調査に携わる中で、職場外OFF-JT(派遣型の研修)に関する課題として、「人材育成関係の研修、マネジメント関係の研修が非常に少ない。専門的な研修は数多く実施されているが、専門的知識だけでは優れた教育者になれるとは限らないのでは」とご指摘をいただいた。確かに、人材育成関係の研修は単発で実施しているものの継続性に欠けている。また、研修カリキュラム全体を見ると、専門性に関する研修は非常に多く、種別協議会や職能団体などでも盛んに行われている。一方で、組織マネジメントや人材育成担当者の育成を扱う研修は、非常に少ない。この点については、県社協でも見直す方向性は出されたが、県でも「人づくり」をテーマに掲げているので、県レベルのキャリアパスモデルといったものを掲げ、「全体としてどういったカリキュラムが必要なのか」、また「そのカリキュラムをどの研修事業実施団体が担っていくのか」という点で官民連携により手分けして、学び手の視点で研修カリキュラムを作っていけると学習効果が高まるかと思う。特に、「実践の場で活かす」ことを意味する『研修転移』という言葉があるが、やはり実践に活かせるような研修プログラムづくりが重要になってくると思うので、特にマンパワーセンターには、そういったカリキュラム構築や研修プログラムの企画に関する力量形成が必要になってくるのではと思う。
●委員
福祉人材の不足が深刻化する中で、人材確保だけでなく、育成・定着を含めたトータルで充実させていかなければならない中、コロナ禍で逆風の状況はあったが、オンラインやハイブリッド形式での研修実施により、遠隔地からも参加しやすくする工夫等をさせていただき、順調に実績が伸びてきたところかと思う。
●委員
「仕組みづくり」の「市町村家庭総合支援拠点」の実績が伸び悩んでいるところ。冒頭で、2060年には、60歳以上の単身世帯が多くなるというお話があったが、介護にお世話にならなくても元気で働ける世帯の高齢者も、おそらくいらっしゃると思う。そういった方たちを何とか子どもたちと接点を持ちながら、居場所づくりなどしていけたらいいなと思う。そういう方たちに、積極的に市町村が実施する事業に参画していただくというのも、1つの方法かと思った。
○事務局(介護高齢課)
御意見のとおり、昔で言えば高齢者を「元気高齢者」と「要介護」と介護されているか否かで分け、要介護の方には介護サービスを提供し、元気な方には生きがいをもっていただこうといった話が多かったが、最近は、自立している方や、65歳、70歳になっても働いている方も多い。これまでのように、高齢者の「余生の生きがい」といった観点ではなく、高齢者の方もどんどん地域に参画していただき、地域支援の担い手の1人として活躍いただけるような取組を県としても進めているところ。
先ほど、子どもとの接点についてお話いただいたが、例えば、高齢者が独居高齢者を訪問したり、若者と高齢者が触れ合うプラットフォームを作るなど、県庁内の様々な所属でそういった取組が進んでいる。これからは、元気な高齢者、自立した高齢者の方々についても、担い手の1人として活躍いただくことを、県としても考えている。
●委員
前回、事務局からも説明していただいたが、「市町村子ども家庭総合支援拠点」については、今年の4月から「子育て世代包括支援センター」と統合した「子ども家庭センター」という形になっている。本計画の目標値としてはどのように取扱うのか。
○事務局(児童福祉課)
今後の目標としては、現在、県の子ども部門の計画においても検討しているところだが、この目標については、「子ども家庭センター」へ見直す見通し。
●委員
「成年後見制度の中核機関の設置市町村数」だが、令和4年度から5年度にかけてかなり伸び、残り5市町村となっている。社会福祉士会としても、残り5つのうち3つの市町村に関わらせていただき、中核機関の設置を支援しているところ。
冒頭、孤独・孤立のお話もあったが、身寄りのない方への支援をどう進めていくかということを考えたとき、市町村の中核機関というものが機能し、そこで、円滑に支援を行うことができるようになり、対象者の生活を守ることができるようになる。中核機関が設置されていない、もしくはあまり円滑に機能していない場合には、個々の支援機関にいる1人ひとりの専門職が頑張って動いている状況。中核機関の設置はもちろんのこと、それがどう機能していくかを考えたときに、社会福祉士が貢献していければと思う。
●委員
中核機関については、社会福祉士にもかなり尽力いただいているところ。令和5年度で30市町村とかなり進んできた実感がある。
問題は、申請数が47都道府県のうち、30番代後半であり、利活用の状況がどうかというところがある。一方で、日常生活自立支援事業については、かなり平均より利用が多く、本来、成年後見制度により支援すべき方が、そこに滞留してしまっているのではと思う。使いやすい、費用が安いということもあるかもしれないが。成年後見制度の利用促進に当たっては、中核機関の設置はあくまで手段であるため、制度の利活用を図っていただきたいと思うがどうか。
○事務局(地域福祉課)
御意見のとおり、市町村における中核機関の設置は、あくまでスタートラインに立ったことを意味するところ。現在、介護サービス・障害サービスを利用したい方が市町村役場へ赴けば、すんなり相談へ繋がることができ、サービス利用が適当であれば支給決定までの道筋が整っている。成年後見制度においても、市町村の中核機関が権利擁護ネットワークの中心となり、制度利用すべき方が円滑に繋がれる体制を整えられれば。
また、日常生活自立支援事業の利用者の中に、成年後見制度へ移行すべき方も一定程度いるであろうという点や、費用負担の面から移行しづらい方がいるであろう点についても、御意見と同じ認識。市町村が実施できる事業に、低所得者へ成年後見制度の申立費用・報酬費用の助成を行う「成年後見制度利用支援事業」があるが、県としては各市町村に対して同事業の実施を支援しているところ。引き続き、県内における制度利用促進に尽力して参りたい。
●委員
こども家庭センターについて。現在、群馬県ではどれくらい設置されているか?また、子育てをしている世帯としては、この「こども家庭センター」というものが、どれだけの方に知られているのか、というところが心配に思われた。周知について、どのように行うのか見通しがあれば。
○事務局(児童福祉課)
11月1日現在、10市町村で設置。新たな種類の施設ではあるが、取扱っている内容とすると、従前の子ども家庭総合支援拠点による児童福祉分野の取組と、従前の子育て世帯包括支援センターによる母子保健分野の取組が統合されたもの。なお、前者については本日の資料のとおり23市町村で設置、後者については、既に全市町村にされていた状況であった。現在、あくまで「こども家庭センター」として確立されている市町村は10か所であるが、ただ、相談対応自体は、どの市町村でも受け付けている。
また、何か大きく変わったことがあるとか、全く新しい何かが始まるといったものではないため、周知については、各市町村において従前どおり努めていただいているところ。
●委員
令和4年度に児童福祉法が改正され、そのタイミングから各市町村において検討が進められているところ。全国的に課題となっており、今年5月の全国調査では、5割程度の設置であると大きく報道された。前身となる子ども家庭総合支援拠点については、市町村で整備されてきた中で、周知については中々進んでいないかという部分もあり、もう少し取り組んでいければ。
●委員
13項目の中には無いのだが、災害時の個別支援計画について、障害者や高齢者にとっては、非常に重要な役割を果たすものであり、東日本大震災でも、健常者に比べて障害者の方が、死亡率が高かったという現状がある。県内では、35市町村で個別避難計画の策定に着手しているが、市町村によっては、まだ策定件数も少なく、着手したといってよいかどうかというところもある。策定が完了しているのは10市町村ということだが、地域共生社会の実現に向けた、包括的支援体制の構築を進める上で、この取り組みを進めることが課題であると思う。県では、どのように進めていく見通しか。
○事務局(地域福祉課)
災害対策基本法の改正が令和3年5月にあり、国からは、概ね5年以内に優先度の高い方の個別避難計画をすべて策定するように示されているところであり、県としては、令和7年度末までに、対象者の計画策定をすべて終えるよう目標を設定している。令和5年度においては、未着手の市町村が14あったことから、個別訪問等を通じて伴走支援を行った。すべての市町村で計画作成がスタートしたところだが、現状、策定率が2割以下という状況であり、取り組みは道半ばというところ。県としては、目標の達成に向けて、市町村の取り組みを加速化させる必要があろうかと考えている。
今年度は、とりあえず1件ないし数件作成した市町村へのアプローチとして、できるだけ効率的・効果的に計画作成を進めていただくため、作成の手法を固めていただくことを目的に、危機管理課と連携して市町村を個別訪問し、必要な助言等を行ってきたところ。加えて、希望する市町村に専門家を派遣して、必要な助言をいただくアドバイザー派遣事業や、担当者向けの研修会等を通じて、市町村への支援強化に努めている。
●委員
令和7年度末までの目標ということで、時間もあまり残されていないが、大きな課題かと思うので、引き続き進めていただきたい。
●委員
高崎市では、市が要支援者名簿を作成し、民生委員に渡しているので、自分の担当地区でそういった方がいることを承知している。ただ、自分の地区は3名の民生委員に対して要配慮者が30人くらいいるため、いざ有事の際に、どれだけのことができるのか見通せないところもある。
●委員
市町村が把握している災害時要配慮者の人数についても、かなりバラつきがあるところ。同じ人口規模の市でも、何百人というところもあれば、何千人というところもある。対象者の把握についても、手上げ方式で実施して「策定済み」とする自治体もあり、捉え方が難しいところ。また、要配慮者に対して支援者を貼り付けることが一番難しい。地域によっては、要配慮者の方が多かったりして、支援者が足りないということもある。
●委員
地域の中で要配慮者を把握するというのは、本当に民生委員さんによる尋常ならぬ努力がないとなかなか難しいような気がする。
もう1つ、施設に対する支援ついて、市町村は施設の所在を把握している訳なので、そこへの援助等については、しっかりしておく必要があるのではないか。施設にはBCP、いわゆるその災害時の事業継続計画を策定するよう国からも県からも要請されているが、では、市町村は何をしてくれるんだ、ということ全然出ていない。例えば、これだけの地震があったときに、食料水はどこへ取りに行ってくれ、といった情報があるだけで全然違う。行政から施設に対する一方的な要請だけではなく、行政は何をしますよということをしっかり出していく必要のではないかと思う。
●委員
能登半島地震においても、施設自体の被災、あるいは職員の方が被災して施設に出勤できないといった厳しい状況があったと聞いているが、施設入所者分の要支援者名簿や個別避難計画については、どのような形で進められているのか。
○事務局(地域福祉課)
個別避難計画については、在宅にいらっしゃる方への災害時の支援となっており、例えば施設に入所されている方、あるいは入院されている方については、個別避難計画の対象外ということで、基本的には施設のBCPや避難確保計画のスキームの中で対応いただく枠組となっている。
●委員
施設間で連携して、被災しなかった施設から被災施設へ職員を派遣していただく、あるいは被災しなかった施設で被災した施設の入所者を受け入れていただく、実態としてはそういった調整を施設間ごとに行っているものと思う。病院についても同様ではないか。能登半島地震では大きな課題がいろいろ出てきていると思うので、そういったことも今後、しっかりと検討していく必要があるかと思っている。
(2)次期地域福祉支援計画について
次期地域福祉支援計画に関する策定スケジュールや計画の方向性等について事務局から説明し、各委員による審議等を行った。
主な発言内容
●委員
先ほど進捗状況の評価を行った現行プランについては、事務局から説明があったとおり、県の総合計画と計画期間を合わせるため、終期を7年度まで延長する予定。また、次期計画の策定の段取りや次期計画で取扱う事項について説明があったが、次期計画への期待・希望等も含め、各委員から御意見があれば。
●委員
今年の年頭のあいさつで、勤労寿命の延伸について掲げさせていただいた。これだけの高齢化社会ではあるが、やはり元気な人には働いてもらう必要がある。私も超高齢者の1人で働き続けているが、やはり働ける人が働くということで勤労寿命の延伸が求められる。そういう意味で、職場での検診や地域での検診を積極的に進めたいということを、しっかりこういうところでも述べたらいかがかと思う。
もう1つ、先ほど成年後見制度や家庭支援センター等色々説明があったが、やはり、どうしたら使い勝手がよくなるか、というところを徹底的に検証して、こうしたら良いのではといった提案をいただければと思う。国の方策と、これを実施する市町村の方策とで、板挟みになって、県は大変だと思うが、ぜひお願いできれば。
●委員
高齢・障害・児童分野でそれぞれ計画があり、それらを統括した計画として現行計画があるのかと思う。また、個々の計画については、それぞれで評価し、こういった協議体で意見を伺っていると思う。
このため、どちらかというと、もう少し範囲を広げ、大きなテーマに沿って——例えば社会づくりや地域創生とか——地域共生社会というものは、正に地域づくりになってくると思うので、「地域共生社会を作っていくにはどんなことに取り組んでいけばいいのか」といった観点や、今まさに包括的支援体制を構築するために重層的支援体制整備事業が進められているが、そういった切り口で計画を作っていけたらどうかという思いがある。目標についても、本日評価いただいた指標以外にも孤独・孤立の問題等が挙げられる。
●委員
計画というとやはりそれぞれのコンテンツに関する数値や年次ということになると思うが、制度の隙間や他の計画では表せない領域、もしくは重複してもいいから福祉として境界領域もきちんとカバーするんだということを、理念・ビジョンだけでなくコミットしてほしい。数値の話だけではなく、そういった視点を盛り込んでほしい。
例えば、今、社会福祉士会ではスクールソーシャルワーカーの活用を様々な方面にお願いしていきたいと考えている。スクールソーシャルワーカーについては、教育委員会や学校現場での話と見られがちだが、実際にお子さんが困っている状況をサポートするために、家庭や地域と関っていった結果、子ども本人というよりはその家庭にすごく難があるようなケースでは、子ども本人に対する支援でなく、別の支援が必要になる。そのため、こういったケースへの支援を分野ごとに区切ってしまうと、狭間に落ちてしまって、救われない方々が生じてしまう。
このようなことは、とても特殊な事情があるようなケースだけでなく、本当にありふれた、学校に通えるか通えないかといった地域で見られる課題から、芋づる式に見えてくるものだと思う。そういったことをきちんとカバーできるような視点を、計画の中にきちんと織り込んでもらいたいと思う。そういったとき、ソーシャルワーカーが色々な分野で、色々なところに横串を刺す人材として活躍しているので、ソーシャルワーカーに限らないかもしれないが、そういった人づくりにも、ぜひ力を入れてもらえたらなと思う。
●委員
本計画では児童分野も取り扱っているが、児童分野については、別途、生活子ども部で主体的に色々な計画を作っていることもあり、福祉プランも若干の縦割り感があるかなと思う。逆に、今発言いただいた教育委員会に関係する部分については、生活こども部の計画でもちょっと薄いかなということを感じている。これからは、やはり大事なのは、子ども、子育て家庭、若者と、教育委員会の果たす役割が重要なのではないかという思いがある。
少子化に関しては、保育関連で色々な事業がこども家庭庁でも進んでいる。しかし、教育の部分で言えば、今、群馬県では、ソーシャルワーカーの数がかなり少ない中、教員が多忙なこともあり、ヤングケアラー等の把握もしづらいという状況が顕著にある。そのため、このプランには、制度の狭間や複合的な課題へのアプローチが求められており、全庁横断的な計画にしていった方がよろしいのかなというところがある。
●委員
福祉と教育の部分というところで、やっぱり教育現場の方たちは福祉のことを、十分には理解いただいてないなというのは、教員の方たちとお話する中で、日々感じているところ。赴任して初めて社会的養護を知るという教員の方も、非常に多いかなと思う。
先ほど、スクールソーシャルワーカーさんのお話があったが、やはり各市町村を回るだけの人数が確保されておらず、我々、社会的養護の関係施設には、色々な問題のある子ども、集団に入れない子どもが多くいる中で、各学校にスクールソーシャルワーカーを配置していただけると、施設と学校の連携も取りやすくなるということを、最近、学校と話したところ。制度の狭間や、複合的な課題を解決するための連携をどうしていけるかについては、この福祉プランの中だけで進めていっても、結びつかない部分は出てきてしまうかなとちょっと感じる。
●委員
高齢者も障害者も該当するのだが、地域で移動するのが非常に困難という話が増えてきている。高崎市では、「おとしよりぐるりんタクシー」といったものができたが、できただけで利用している数が少ないというのは、結局、使い勝手が悪いのだと思う。なので、もう少し利用する人のニーズに合わせた、使い勝手のいい移動方法を考えていかないと、単に走っている車に過ぎない。高齢になれば、免許返納ということもあるし、これからどんどん増えてくると思う。外出するための方策として移動の支援をもう少し県としても積極的に、今よりもさらに使い勝手のいい移動方法に、各市町村ができるように、促していただけるとありがたい。
●委員
高齢者も75歳以上になると、いくらか認知症も入ってくる。移動支援と言っても玄関先に出るまでが大変。高崎市がやっているような巡回バスが来たとしても、玄関先までは来てくれないし、そこまで連れて行く人はいない。要するに、高齢者自身が近所づき合いをあまりしてないということが問題になっているかと思う。支援にあたる住民が、協力的ではないような気もする。また、高齢者に対するボランティアに若い人がいない。
重複障害を持つ方の家族から相談を受けるのだが、「こういう障害はどういう団体に入っていけばいいんですか」と聞かれるものの、なかなか手配ができないことがある。川崎市では、民生委員や福祉関係者の方などとそういった話し合いをしているほか、そういったことをサポートしてくれる医療機関があるので、そこにお願いしたりしている。重複障害の相談に対しては、身障連が関わっている団体に該当するものが無いので、その点でどういう団体に入っていただくか悩みどころ。県として、そういった重複障害の方について、どのような団体があるのか、教えてもらいたいなと思う。
「『人にやさしい福祉のまちづくり条例』適合証の交付数」の指標に関して、条例制定から何件も交付していると思うが、過去に適合証を交付された施設が今どうなっているかということは、調査をしているのか伺いたい。
○事務局(障害政策課)
1度適合証を交付すると、その後、適合しているかどうかの継続的な調査は特にはしていない。ただ、一般的には、バリアフリーの移動用のスロープがあるとか、トイレがどうかとか、避難誘導用の設備があるかどうかとか、そのようないくつかの項目に基づいて整備をしていただいているということなので、そういった設備等に故障等があれば、基本的には管理をされている方が通常修繕等も行い、それが維持をされているのではないかと認識しているところ。
●委員
この指標については、「ほぼ達成」となっているが、厳しい話をすれば、1年で2件しか増えていない状況。最初の100件までは早かったが、その後は頭打ちになっている。事業所としてもハードルが高く、——他県では実施しているが——、バリアフリー化に関する補助や支援もない中、伸び悩んでいるのが実態ではないかと思う。今後、これを増やしていくに当たり、検討している方策等はあるのか伺いたい。
○事務局(障害政策課)
お話いただいたとおり、補助等による支援は特段無いが、法改正により一般事業者に対して合理的配慮が義務付けられた。そういった合理的配慮に対応するために、周知・啓発のための研修会の実施を補助や、簡易スロープの導入に対して一部補助している自治体があることは承知している。県としては、これまでも普及啓発に取り組んできた中で、まずは各事業者に合理的配慮の基本的な考え方を理解いただくことが必要なのではないかと考える。予算をかけて対応するということだけではなく、求められているのは建設的な対話であるので、代替方法がないかということを自らのこととして考えていただくことも大切なのないかということで、様々な機会を通じて周知啓発の方に取り組ませていただいている。
そういった中、新入社員に対して合理的配慮に関する研修会を開催するといった新たな動きも出てきたので、そういった動きを後押しするような普及啓発を中心とした支援が今後必要なのかと考えおり、そういったことは継続的に取り組んでいきたいと思っている。人にやさしい福祉のまちづくり条例の適合証に関して、適合基準の項目が多くあり、その中には非常にコストが掛かるものもある。届出を受けた際に、何が適合基準の項目に適合しているかをチェックさせていただき、「この部分については、さらに工夫をしていただけると適合するのでぜひご検討お願いします」という話をケースに応じてさせていただいているが、件数自体は伸びてないので、引き続きそういった努力を積み重ねていきたい。
また、12月に障害者の福祉週間が始まるが、記念式典では「人にやさしい福祉のまちづくり」に協力をいただいた事業者を表彰している。こういった場を活用し、多くの皆さんに知っていただき御協力をいただければと考えている。
●委員
もう1点、市町村としては色々移動支援を実施しているが、県の立場として何か支援方策等はあるのか伺いたい。
○事務局(介護高齢課)
いわゆる移動支援策については、各市町村において、例えば福祉タクシーの助成をする等、様々な対応をしていただいているところだが、なかなか県として、個々の住民の方々を支援することが難しいところ。市町村が行う事業、特に介護保険制度の仕組みの中では「日常生活総合支援事業」というものがあり、各市町村が地域における高齢者等の移動・送迎の仕組みを、その地域の中で一体として進める場合に、県として支援する仕組みとなっている。また、当然、要介護の方々に関しては介護保険サービスの中で、通院等の際における乗降介助といった仕組みがあるため、そういったことを通じて市町村への支援等を行っていきたい。
●委員
これから高齢者の単身世帯がどんどん増えてくるという中で、こういった足の確保の支援は、今後課題になってくると思う。支援者については、ボランティアの方や民生委員さんのほか、先ほど個別避難計画についてお話したが、地域の方が近所にどんな方が住んでいるかがある程度分かるのであれば、そういった制度から準用というのも、もしかしたら可能なのかもしれない。
●委員
現行計画の基本理念「県民誰もが安心して暮らせる地域共生社会に目指して」という意味では、高齢者、障害者、児童と非常によく網羅していると思う。また、地域づくり・仕組みづくり・人づくりというのも大変よい組み立てと思うが、たしかに縦割りという側面ははあると思う。計画を遂行するに当たって、お金と人が必要になってくると思うが、まず、それぞれ人材育成をしていただいて、できれば横の連絡が密になれるようになるといいなと思う。
成年後見人制度について、今、40代50代で脳血管障害で倒れる方がいらっしゃるが、結構皆さん助かってらっしゃる。例えば、ご家族で面倒を見ていくのだったらともかく、子どももいるのに配偶者の面倒まで見られないからといって親元に返す、というケースが意外と多い。そうすると、いずれ成年後見制度を使わなくてはいけなくなると思う。
中核機関を作ったとしても、それがあるということを周知しなければ、利用者も増えない。例えば、離婚の際の公正証書について、意外と知らない人がいて、養育費がもらえないというような事例も多く発生しているが、それ同様に、やっていることをなるべく県民に広く周知するような形で行っていくといいかなと思う。
●委員
成年後見については、全国的に伸び悩んでいるというのが実態だと思うが、「一旦、制度を利用するとやめられない」、「後見人を代えてもらえない」、「費用がいくらかかるか分からない」と、非常に利用しづらいといった声が上がっており、かねてから、国は、使いやすいように検討するとしているところもう3年、4年経過するが、この点については、進んでないということでよろしいのか。
○事務局(地域福祉課)
まだ結論は出ていないところだが、昨年度の国の検討ワーキンググループにおいて、今お話しいただいた後見人の交代の手続をもう少し容易にする方向性や、特定の事務に限定したスポットでの利用について、参画する委員から意見が出されており、併せて、法務省の法制審議会でも法律面での技術的な検討が進められている。現在、成年後見制度の国の基本計画があり、令和8年度までの計画とされているが、その計画において、法改正も含めた見直しを検討することとされているため、今年や来年に大きく変わることはないものの、見通しとしては、今説明させていただいた方向で進んでいる、というのが現状。
●委員
成年後見制度については、これからますます必要性が高まってくるので、利用しやすい、気軽に利用できる制度となってほしいと期待したい。
●委員
社会的養護の観点からお話したい。今は、措置延長といったこともされるようになってきているが、子どもが自立した後、なかなか自立しきれないという問題があると思う。児童福祉から地域の福祉へつなげていくところを、もう少しシームレスに、みんなが利用しやすいようになっていったらいいと思う。
●委員
児童が18歳になった後の支援に結びつける話をするのだが、児童分野は、自分たちの専門分野については分かるのだが、その先の障害サービスに繋がる経過だとか、正直、社会的養護関係施設の職員や児童相談所のケースワーカーさんでも、意外と分からない方が多いなと、日々感じている。そのため、1から自分たちで勉強しながら支援を行っていくのだが、児童が18歳になって施設を出ると、児相との関わりも終わりになってしまうので、その先に繋げた時の障害者の施設さんなどは、やはり「そこで切られちゃうのですごく大変です」と言われる。
どのように次に繋げていったら良いのか、地元の障害者施設の管理者さん等と相談しながら進めているような傾向があるが、難しさを感じている。
●委員
非常に課題だと思う。県の方でもケアリーバー対策等色々な事業展開されていると思う。
○事務局(地域福祉課)
今ご指摘いただいた自立支援は非常に重要な部分であり、社会的にも非常に注目を浴びているものと思う。現在、県としても、ケアリーバー支援ということで、施設退所者や里親委託による支援が終了した方についても、児童養護施設の皆さんにも力添えいただきながら、18歳を過ぎても、そこのところで関われる、そういった相談をできる場所なども作っている。
そういった形で、18歳だからといって支援を終えるのではなく、ケアリーバー——施設を出た方についても、しっかり支援できるように、取り組みを進めて参りたいと考えている。
●委員
だいぶ、県の方でもその点については予算化され、事業が進められてきており、今後、効果が期待できるものと思う。
県当局は、本日寄せられた意見を参考に、新たな視点で検討を進めていただきたい。
5 結論
議事1 「群馬県福祉プラン」の点検・評価について
「群馬県福祉プラン」の数値目標に関する進捗状況及び自己評価について、出席した委員による点検・評価を実施した。
議事2 次期地域福祉支援計画について
次期地域福祉支援計画について、出席した委員による意見交換が行われた。